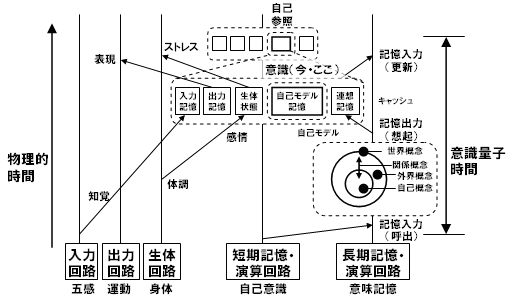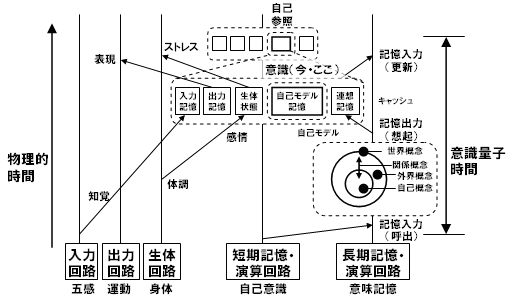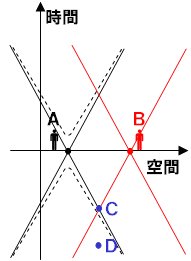新書『自循論』
Last updated 2010.3.22
この意味世界において最も根源的なものは“自”という
唯一無二で普遍的な抽象概念である。
無限に存在する自己完結的な宇宙の中で、
“自”という抽象概念を意識できる存在を内包した宇宙だけが
有意味である。
|
【目次】
|
自循論の戦略
|
|
この「自分」という感覚の格別さと神秘性を紐解き、
森羅万象の本質を見通す知的思考のフレームワークを確立する。
|
「自分とは何か」
「自分を自分だと感じるこの意識とは何か」
これは、今後の世紀に於いて、科学・哲学・宗教を統合する上での
唯一最大の難問である。
私達は、この難問に対して、神経生理学、量子力学、実存哲学などの
人類の叡智を総動員して臨まねばならない。
誠実で善良な人々が思考の限りを尽くしてきた成果に最大限の敬意を払い、
次の段階に進まなければならない。
「自分という感覚」「意識」は、どの知的活動領域の専門家であれ、
最後に必ず辿り着く疑問であるが、
誰もこの問題をどう扱って良いのか明確には分からない、
解答不能のパズルのようだ。
無視しようにも片時も消えることの無いこの「自分という感覚」に、
超一流の科学者や宗教家が様々な説明をしているが、
「本当にそれで説明し尽くせているのか?」と疑問符が灯ってしまう。
説明されてしまった瞬間、それ以上のなにものかであるように感じられる。
それくらいに、「自分にとっての自分」という感覚は格別だ。
「自循論」では、この「自分にとっての自分」を突き詰めて考えることにより、
一回限りの人生を有意味に生き抜くための、
森羅万象を貫く知的思考のフレームワークを提供する。
|
自分という感覚
|
|
自分という感覚は「有限性(制約感)」と「任意性(判断力)」からなる。
|
- 自己制約ゆえの自己判断
- 結論として、自分という感覚は「いま、ここ」に情報処理機構が凝縮され、
空間的にも時間的にも一定範囲に押し込められたという制約感と、
その中で主体的に視点と行動を選択できるという自由感から成立している。
- 自分、という感覚は、
自己の内部に折り畳まれたこの宇宙のありようと相同の“制約”と、
意味世界に与えられた可能性崩壊の一定の“任意性”に基づく。
- 脳や意識の働きを因果律に縛られた唯物論的決定論で説明し切ることは
この「自分という感覚」の“任意性”に反するので抵抗を感じるわけだが、
逆に言うと「自分という感覚」は、その説明不可能性を基盤として成立
していなければならない。
- つまり「意識とは何か」といった問い掛けに関しては、決定論的に明晰に
説明をしようとすればするほど答えから遠ざかっているように感じる、
というジレンマを本質的に持っていることを先ずは明晰に理解する必要がある。
- 有限性(制約感)
自分の身体的な特徴から空間を占める範囲は決まっているし、
自分という意識は生まれてから死ぬまでの時間しか持続できない。
(この、「自分という意識」の一回性は極めて重要であり、
この一回性の認識によってしか、宇宙と自分を繋ぐ究極の自循構造を
真に理解することは出来ない。自分という意識の特別性が、この宇宙にも匹敵する、
という素朴な感覚の源泉がここにある。終わりがあってこその自分なのである。)
→ バラモン教の教える「梵我一如」
→ ハイデッガーの言う「死を見つめよ」
また、脳内活動の一つ一つ、DNAや
タンパク質、
細胞の働きの一つ一つにまで
この意味世界・宇宙・時空全体のありよう、本質、法則(相対性理論や量子力学
など)が折り畳まれている。
この宇宙自体も、一定の空間を占め、生まれ、死に、物理学的・純粋数学的な
法則によって制約されている。この制約構造自体は、私という意識にとっても
私にとっての宇宙の全体にとっても同一である。
- 任意性(判断力)
ある一連の可能性の中から、他の何からも説明されない、自分自身の内側に
ある何らかの機構によって、一つの具体的な行動や視点を選択する、という
感覚が「自意識」には必要である。大きくは2つの立場がある。
- 自意識の実現機構は決定論的であっても、それがあまりに複雑過ぎる
ために説明も把握も出来ず、幸いにもこの「意識過程に対する無知」が、
「自分が主体的に考えている」という妄想を確たるものにしている。
(※実体が機械論・決定論的機構でも複雑なら自意識は生まれる)
- 脳内の微細管等にある程度コヒーレンス保持時間の長いキュービット
(量子ビット)が実現され、量子のもつれあい(共鳴状態)が起き、
何らかの有意味で複雑な計算を「瞬時に」行っている。
(※実体として非決定論的な仕組みが自意識の背景にある)
しかし、量子論的解釈が本当だとしても、なぜ、どういう理屈で、共鳴状態が崩壊して
一つの有意味で具体的な結果が得られるのか、というメカニズムは不明である。
- 1プランク長・
1クロノン以内に起こっていることは
我々にとって説明不可能であり無意味であり、逆にどんな仮説を立てても構わない。
それらは事象の地平線、意味の地平線の向こう側にある。
- ヴィトゲンシュタインの言う
「語りえぬものについては、沈黙しなければならない。」
- 沈黙せざるを得ないことで得られる制限と自由。
- とにもかくにも、説明不能性こそが自由感の説明であるので、
この格別な自意識を放棄できない以上、説明不能性は「本質的に存在する」
と認めるのが自然だ。(盲点の実在性)
- 人は「知の宗教性」により究極的でエレガントな物理法則が存在し、
それが宇宙の全てを説明できると考えているが、同時にそれは
自意識を放棄する考えでもあり、最初から無理な相談である。
(もしくは必然的にニヒリズムに陥る考え方である。)
- 但しメカニズムを確定することは出来なくても、自循論上の意味的な
解釈は成立する。複数の可能性から一つの現実を選択する(量子崩壊する)
根源的な意味は、意味世界が有限だからであり、「いつか終わる」という
ω点を持つという、この意味世界の内在的性質
(この宇宙の意味の素粒子としての自循のプロパティ)が
量子崩壊を強要するのである。
終わるが故に、有意味である。
終わるが為に、可能性は現実に崩壊する。
有意味であるが為に、可能性は現実に崩壊する。
|
自己と他者
|
|
最終目標は、自己を掘下げ切り、他人と共有すること
|
「自分の自分という感覚」の根源は何かと考え、
その結果を多くの人と共有したいのであれば、
先人の科学的・宗教的・哲学的な考察も踏まえて深めていくやり方がある。
一方で自分自身をひたすら掘下げ、そこで得られた閃きを言葉にして、
共感を得られるかどうかを検証するというアプローチもある。
実際は、その両方を靴紐のように編み上げていく必要がある。
抽象的な言葉を勉強して、自分なりのイメージを合成し、いろいろと考えたり
することは楽しい。そうやって獲得した「言葉」には、自分が勉強した長い時間の
想いが篭(こ)められている。そうして、この「言葉」を踏み台、部品、
パッケージとして、より高く複雑な思考を築き上げていくことが出来る。
しかし、こういった「言葉」は、例えば哲学辞書を片手になるたけ標準的な
使い方をしようとしても、特に抽象的になればなるほど、篭められた「想い」の方が
強くなり、他者と議論する場合に大きな障壁になる。
要するに、言いたいことが伝わらなくなる。
もっと恐ろしい危険は、抽象的な議論を繰り返すうちに、
術語を組み合わせる形式的なパズルの世界にハマり込んで、
自分自身が、実感と関係のない世界でのゲームに溺れてしまうかも知れない。
要するに、何がしたいのか。
この原点に、いつでも立ち戻れなければならない。
哲学の議論自体を楽しむことが目的になってはならない。
哲学の言葉は、実生活から遊離してはならない。
「単に形式的な」ゲームに過ぎないかもしれない哲学の世界に、しっかりと
多くの人と共有できる言葉で語れる橋渡し、舫綱、接着剤を導入せねばならない。
哲学も科学も宗教も、人間学の一分野である。
人間が人間とは何ぞやと問う自循論は、全ての学問と何らかの関係を持つ。
※人間学は、「人間が人間自身を参照する」という構造を
(定義より)原理的に内包する学問である。
|
思考方針
|
|
結局のところ、自循論は何を目指しているのか。
|
- 哲学は、一回限りの人生を良くするものでなければならない。
哲学は、楽しく生きるための方法論という側面も持つべきだ。
「この世に生まれてしまった自分」だけに絞ってみると、
「この1回の人生を楽しみきる」ということは極めて重要だ。
哲学は、「人生の意味」、「生命の意味」を検討する骨組みを与え、
惰性を避け、効率良く深く「楽しむ」ための強力な指針となる。
「無」、すなわち何もない状態は、全ての基本である。
無意味は、あらゆる意味の基底に絶対的に存在する。
ここから、偶然、何かが飛び出し、湧き出す。
これが「楽しみ」である。だから、「苦痛」も、広義の「楽しみ」に入る。
人生のダイナミックレンジを広げることが重要である。
楽しみを追求すれば同様に苦痛も追求する結果となるが、
その振幅の大きさ
そのものを味わうことが「生きる」充実感に繋がる。
死から目を背けて生を語ることは避けるべきだし、
苦痛を回避して快楽を得ようという態度も破綻を来(きた)すだろう。
これに対して、「何もしない」という一つの回答もある。
また「平凡であろうとする」「無理の無い人生を送る」という解もある。
勿論、パワフルに生きるだけが生き方ではない。
但し「自虐的に苦痛ばかりを求める」ことも「苦痛なくして多大な快楽を
手に入れようとする」ことも、この意味世界のありようからは逸脱している。
そのような精神は持続的に意味を出力し続けることは出来ない。
- 「万物の理論」と「神」を回避しよう。
結局自分は培養液に浸されている一個の脳が見ている夢だとか、
この世界の全ては3分前に過去の記憶と共に神が創ったものだとか、
何でも説明できてしまう代わりに何も得られないような
TOE(Theory of Everything:万物の理論)は、
アイディアとして面白いが退屈かも知れない。
単にTOEといえば一般には「超大統一理論」を指すことが多いが、
原義としては“あらゆる自然法則の根底に位置し、すべてを説明する
究極的な原理”ということだろう。
ところで、アイディアとして面白いし、退屈というより、
かなり魅惑的な考え方がある。
この宇宙は、より高度な知的存在(神)が実行中の
「コンピューター・シミュレーション」なのではないか?
そして、この「コンピューター・シミュレーション」のポイントは
「有限の演算速度と有限のメモリ空間を持ち、ディジタルである」
という意味で本当に我々の良く知っているコンピューターと同じである。
量子力学の不思議も、コンピューターの有限性によるものだと考えると
納得できる部分が多い。
無数に枝分かれする並行宇宙を想像するよりは理解が容易だ。
神のコンピューターの中で発生した人間が、
そのコンピューターの簡易版としてコンピューターを作り、
これだけ流行している(…というより既に人間存在に
無くてはならない存在になりつつある)というのも、
偶然というより必然という感じがする。
ただ、いずれにしても、人間には神と交信する手段は無いので、
仮説として面白い以上の意味は、今のところ、無い。
自循論は有限の立場を固持し、神と訣別し、
我々自身にとっての「意味の素粒子」を求める。
自循論は、「意味」と「無意味」の線引きを重要なテーマとしている。
面白いが無意味なものに、
深く足を踏み入れないよう、注意深く議論を進める必要がある。
意味と無意味の境界線を引き、
神は無意味の領域に移動させねばならない。
厳密に客観的な学問であるべき物理学である「量子力学」は、
神を仮定しているのではないか、という意見もある。
物理学であっても純粋数学であっても、
それを全て有意味であると鵜呑みにしてはならない。
特に「無限」や「連続」を自明のこととして扱っている部分は要注意だ。
- 表面的な差異に捉われず、本質的な自循構造に着目しよう。
生命は水分子の物理的・化学的特性などをアテにした上で
自己複製を行うオートポイエティック・システムである。
生命は、その本質に自循構造を持っている。
なお、“純粋な”自循は閉鎖しており、外部を持たないので、
外部の中で生かされる生命は“不完全な自循”
“完全な自循を目指そうとするもの”と捉える。
自循は、意味的な素粒子であり、その観点ではミクロだが、
この意味世界全体を説明する構造という観点ではマクロである。
自循構造は至る所、あらゆる文脈に現れるものであり、
素粒子、意識、生命、宇宙などを貫く概念である。
- 生命や意識とも切り離され、高度に抽象化された
「自」という概念そのものは、普遍的であり、
唯一無二の絶対的な構造である。
「自」以外の概念(例えば素粒子とか集合論とか意識とか)を
出発点とした学問体系があるのと同様に、
「自」という抽象概念を出発点(公理)とする体系もまた、
構築可能だろうと考えられる。
つまり、先ず最初に「自」ありき、である。
たった一つの「自」という概念には、
「自分と自分以外」という静的な関係と、
「自分にとっての自分」という動的な関係が、
既に織り込まれている。
だから、「自」という概念は、既に、プロトタイプとしての
空間と時間という概念を必然的に含んでいる。
それに引き続き、ありとあらゆる現象への説明のワンセットが
転がり出てくる。
意味=差異=変化=速度の根源性が相対性理論を意味づけ、
差異の有限性が量子力学の必然性を説明する。
私達一人ひとりが産まれて、精一杯生きて、死ぬことの意義を、
宇宙全ての存在価値にまで高める。
このように、自循論は、たった一つの公理である「自」から出発する学問である。
- 自循論の概要
- 自循論が解き明かしたい事の一つは、極めてシンプルで、
「この、私が私である、という不思議な感覚、すなわち自意識は、
一体どのようにして生じるのだろうか。」
という疑問に、スカッとした納得できる説明を与えたかったのである。
紆余曲折を経た結果としての、現時点に於いての私の立場は、
以下のように整理されるだろう。
- 何らかの霊的なものではない。
- 量子脳仮説のような、量子現象を持ち出す説明は不要である。
(不確定性原理は、意志の最終的な自由性と独自性を担保する砦
であるけれども、自意識という現象の説明の主要因ではない。)
- 自意識=「自のクオリア」×(「感覚クオリア」+「意志クオリア」)。
即ち、先ず、「自分で自分を意識し続ける」という無色透明・無味無臭な
「自のクオリア」が維持されており、ここに感覚という入力情報からの
影響・変調があって、「赤く見える」「高い音が聞こえる」といった
質的体験としての「感覚クオリア」が生じている。
また、「自のクオリア」に対して、自分自身の無意識の奥から湧き上がってくる、
経験から正にこう結論しようとしている出力情報からの影響・変調があって、
「こう理解しよう」「こう動作しよう」といった能動体験としての
「意志クオリア」が生じている。
- 自意識のベースラインとなる「自のクオリア」は、人間においては
「脳が脳自身のことを考え続けている」という動的平衡状態として
実装されている。脳は、神経細胞単位で見ると、極めて巨大で複雑な構造物だが、
神経細胞の系(ニューロンとシナプス)がやっていること一つ一つは単純で、
可塑性という性質により、「情報を処理すると同時に記憶している」だけである。
(信号を伝達しながら、同時に結合強度を変化させている。)
脳の99.99%を占めるフィードバック回路は、特にノンレム睡眠中などは
ノイズに満たされて、純粋に脳自身のことだけを考えている。
もし、星型の容器に、理想的に細かい砂を敷き詰めて、ランダムに揺すったら、
境界の形に影響されて、実に複雑な波紋が内部を行き交い、
砂漠の風紋のように複雑な模様を描くだろう。
脳も同じように、脳内の神経回路を、(ノイズを満たしてヘブの法則を利用し)
脳の形を反映した結合強度のパターンに日々調整していると考えられる。
これが「自のクオリア」の物理的な正体の一側面だろう。
- しかし、フィードバック回路がたんまり入った学習型ニューロコンピュータに
適当にノイズを流し続ければ自我が発生するのか、というと、そうではあるまい。
自我が発生するためには、脳だけでなく、
脳と全身の神経回路が形作る系の全体が重要であり、
無意識下で常に「肉体」という境界線を感じ、
「肉体の内側と外側の感覚」「行動のフィードバックとしての感覚」
を常に無意識に処理し続けていること、その全体が、「自のクオリア」の形成に関与している。
(星型の容器ではなく、まさに人型の容器の内側で、神経回路網内の電気信号は、
常に特有の波紋を描いているのである。)
私たちは、無意識のうちに、常に、自分の内側と外側を感じているし、
自分の意志による一挙手一投足の結果を筋肉や皮膚の感覚の変化として
直ちに自己理解している。ただ突っ立って何も考えていない時ですら、
無意識の内では、「自のクオリア」形成は、莫大な演算量を伴い維持されている。
これに比べると、人間の意識の領域など、極めて小さい。
- では、肉体を考慮に入れた、フィードバック回路を持つ神経系全体を
シミュレートすれば、そこに自我が発生するのか、というと、これでも足りない。
「自」という抽象概念に到達できるだけの、複雑かつ大量な情報を扱えねばならない。
神経回路は、そもそも可塑性によって、繰り返されるパターンから特徴的なものを
記憶する抽象化マシーンなのだけれど、ここから「身体の内側と外側」
「手を動かそうとする気持ちと、手を動かした時の筋肉と皮膚の感覚」のような
パターンを暗記し、そのパターンが色々な場面や身体の箇所で繰り返されることで、
別の回路が「内と外」「行動と結果」のような更に抽象的な概念を記憶し、
これらが更に積もって「空間的な“ここ”と、ここで“ない”場所」とか
「時間的な結果としての“いま”と、いまで“ない”原因としての過去」とかいった
高次の抽象化が行われ、これが大脳基底核から延々と前頭葉の方まで多段的に進行し、
“ない”という抽象概念で結び合わされた、あらゆる対象で“ない”「自」
なる概念にまで辿りつかなければならない。
(私たちが認識している、ありとあらゆるものは、外側であり過去である。
つまり、“ここ”で“ない”し、“いま”で“ない”。
その全てに欠落しているものの集大成として、とうとう脳内で辿り着いた
唯一絶対の、あらゆる対象で“ない”ものが「自」なのである。)
- では、肉体を考慮に入れた構造を持ち、十分に多段な抽象化能力を持つ、
中間層だらけのニューロコンピュータならば、適切に入出力を調整し続ければ、
自意識は発生するのだろうか。ここまで来ると、私は「そうかも知れない」と
思えるようになる。あらゆる対象を認識しながら、それでは“ない”「自」を
維持し続ける、という、危うい高度な動的平衡、
「自」自身を認識しようとしても、それは常に認識される側に滑り落ちてしまい、
いつまでも謎なままでいる、時間の最先端にいる「自」、
この、無意識下に織り込まれた「自」へ至ろうとして至れない緊張関係の連鎖が、
「私が私である」という感覚の正体なのだろうと思う。
さて、これだけの条件を考慮すれば、意識はコンピューターで再現できるだろうか。
できるかもしれない。しかし、このような複雑な(しかも一見、合目的でない
自己演算を大量に維持するような)プログラムを走らせることは、
今の世界中のコンピュータを繋げても難しいし、たとえ出来ても、
非常にゆっくりしたものになるだろう。頭蓋骨の中だけで、これだけのことを
やってのけている脳は、やはり物凄い物質だと思う。
さて、このように自意識の発生機序を対象化してみて、改めて
こうして文章を書いている私自身が「今、こうして、私が私であると感じている
この不思議な感覚を、以上の文章で説明し切っているのだろうか」と自問自答する時、
どうしても何か不足を感じてしまう。その不足の正体は一体何なのだろうか。
ここで、どうしても自循論の、もう一つの「解き明かしたいこと」が
頭を擡(もた)げてくる。それは、「私は何のために生まれたのだろうか」
ということだ。私が物理法則や化学反応で「説明され切って」しまえばしまうほど、
この、「生まれて、生きて、いずれ死なねばならない、私自身」という自意識が、
無価値で無意味なように思われてしまうのである。
そこで、このようにして奇跡的に生まれた「自意識」という現象の側から、
物理法則の側への逆襲を始めるのだ。
そもそも、この宇宙の物理法則は、何のためにあるのか。
それは、銀河を作ったり、太陽を輝かせたりするためではあるまい。
物理法則と宇宙は、人間を形成し、自意識を獲得させるためにある。
しかも、物理法則とは、この自意識に意識されている限りにおいて意味を持つ。
あらゆる物理法則は、徹頭徹尾、知性が直接的または間接的に知覚できたもの“だけ”
から経験的に抽出されたものに過ぎない。
つまり、物理法則とは、鏡に映し出された知性に過ぎない。
では、果たして、物理法則が自意識を生んだのか? 自意識が物理法則を生んだのか?
物理世界と情報世界は、どちらがより根源的なのか?
自循論は、ここに来て、やっと追求の手を緩める。
「意味世界とは、物理世界と情報世界の相互依存である。」
この結論により、物理法則の側への逆襲は終わる。
劣勢だった情報世界を、物理世界と完全対等なレベルに回復させたからだ。
どちらがより根源的か、という問いをアウフヘーベンし、両者を立てたのである。
無限乱雑空間の中には、無限個の「世界」を想定することが出来るが、
ちゃんと意味を持っている世界というのは、【自意識】が、内側から宇宙を眺めて、
知りたいと思うことを可能な限り知り、表現したいと思うことを精一杯表現している、
そんな情報世界と物理世界が奇跡的な自己無矛盾のバランスを持っている時だけであり、
私たちは、偶然、そういうバランスを保った意味世界にいる、ということなのだ。
つまり、「私が私である、というこの不思議な感覚」とは、
宇宙全体の存在と、根が繋がっている。
自意識が物理法則ですっかり説明されてしまったとしても、
その物理法則自身が、自意識と相互依存関係にあるのだとすれば、
これは理論の円環の一部に過ぎず、私たちが完全に物理法則で説明されしきってしまう、
ということを意味しなくなるのだから、「あぁ、私は単なる物理機械なんだ」と
溜め息をつく必要もなくなる。
「自意識」を深く深く突っ込んで考え、そして私自身の一回限りの人生に
何か意味があるのだとしたら、その根源は宇宙全体と意味世界の成立まで巻き込んだ
壮大な論理体系にならざるを得なかったのである。
ここまでで、物理世界と情報世界の相互依存性を、マクロに導いてきたのだが、
その最も根源的な相互依存性を、私たちは時空、とりわけ時間の成立の中で
より精密に解明する必要があるだろう。
すなわち、線形の《過去―現在―未来》という連続構造を持つ『物理時間』と、
《永遠の虚像としての“いま” ― あらゆる認識対象としての“過去”》という
離散的2時刻しか持たない『原時間』の対応である。
その詳細な解明を更に進める必要があるが、結局のところ、
原時間の発生のためには、もともと物理時間が流れていたという説明を
全く排除することはできないし、
物理時間が一方向に流れていくということは、
原時間を前提に考えなければならない、という相互依存関係にあるのだ。
この意味世界を論じる哲学には、科学万能主義のような
物理世界→情報世界という論理展開と、
観念論や唯心論、人間原理宇宙論のような
情報世界→物理世界という論理展開があるが、
どちらも初手から間違っている詰め将棋のようなもので、
永遠に捕まえられない王将を追う運命にある。
物理科学や観念哲学の成果を少しも傷付けることなく丸ごと生かし、
『意味世界とは、無限乱雑空間から切り出された、
物理世界と情報世界が無矛盾に相互依存している状態である。』
という基礎論理を持つ自循論こそが、
科学・哲学・宗教の全てを無理なく統合する基盤であると言えよう。
この詰め将棋は、自循論の一手詰めなのだ。
|
自己の本質
|
|
ひたすら自己を掘り下げ、何が「私が感じる私という感じ」の源泉かを突き止める。
|
自己とは何か、という現代の唯一最大の難問をを検討し始めようとした時、
非常に身近なところに検討材料があることに気付く。今ここにいる私自身だ。
徹底的に「自分」にこだわり、掘り下げることが一つの突破口に成り得る。
|
最後に残る「自分」
|
|
目を瞑り耳を塞ぎ感覚を遮断しても残る自分という感覚
|
いつかは自分という存在自体がこの世の中から消えて無くなってしまう、
ということは、今の自分を有意味たらしめるためにも必要だと諦めるが、
それにしても「今」「ここに」自分がいる、という感覚は、
ユークリッド的な空間とクロノス的な時間の一部を自分が占める、
という古典物理学的な捉え方とはギャップが大きい。
自分とは、それ以上の何かであるという感覚がつきまとう。
カントに時間と空間は人間にアプリオリな直観形式であると言われても
それが何を意味するのか今ひとつ分からないし、
少なくとも失いかけている「自分というものの特別さ」に対する
大した慰めにはならない。
少なくとも私は、主体的に何かを判断しているという気がするので、
決定論的哲学に基づき自分という生命が単なる力学的・科学的な
機械装置であると考えることに、
「抵抗」とまでいかなくても「違和感」は感じる。
|
単純な「自分」
|
|
難しく考えず、無垢な意識で「自分」を見つめてみよう。
|
死んだ後のことは分からない。
自分の生まれる前の歴史が事実だったかも確信は持てない。
自分が生まれた瞬間の記憶は無い。本当に「生まれた」のかも定かではない。
引力を感じることは出来るが、それが天体の運行にも等しく作用している
などという実感はまるでない。太陽は地球の周囲を回っているように見える。
原子や電子やクォークなど見た事が無い。
一億個の次は一億一個なのだろうが、実際に数えてみたことはない。
刷り込まれていはいるが、実は時間が流れているという感覚も無い。
ただ、一つ前の自分(自分が知覚している周囲全ても含む自分)と
この自分との間の変化が感じられるだけである。
変化の蓄積が記憶や歴史を組み上げるが、
それらも除外した「いま」「ここ」には、
自分が自分を見る、という単純な循環構造があるだけだ。
その“自分”は、十分に意識を純粋に単純に還元して、
範囲をこの宇宙全てまで感覚を広げたとしても、
『確かにある』という感じがする。
無限の中に溶け込んで境界の分からない茫洋とした幻でなく、
有限の境界を持ち、『確かにある』という感じがする。
千の理論が私を切り刻もうとしても、
「確かにある私」が「私を感じている」という事実までは砕けない。
※デカルトの「我思う、故に我あり」という言葉も、
自己循環の構造を持っている。
※「単純な精神」の表現の挑戦は「単純な精神の独白」へ。
極限まで絞り込んだ「自分自身との対話」の中に「自循構造」
が実感として立ち現れる。
この宇宙は、砂嵐の中に人間が思い描いた【=有限性の中で
視点を持ち込んだ】幻想だった
その私からすると、過去は絶対ではない。未来も絶対ではない。
「遠い過去」と空間的に表現されるが如く、
自分の短期記憶に収まっているより遠くの過去は既に仮想のものだし、
自分が想定できる一瞬後より先のことも仮想のことだ。
どちらも遠い。
何らかの進行感、物理世界の働きかけを丹念に削り取っていき、
最後に残る言わば「純粋な意識」からすると、
時間も空間も「今、ここ」からの距離であり、
決定論的に過去が事実というなら未来も固定化されていると思えるし、
人が未来に対して自由で開かれているというなら
過去も自由に開かれていると思う。
空間も、そのありようが全て決まっていると考えてもよいし、
自分にとって意味ある空間は自分が決めていると考えてもよい。
『逆コペルニクス的転回』
過去から未来に整然と空間が並んでいて、「ここが今ですよ」という
ポインター(program counter)が一つずつ動いていくなんてイメージは
気持ちが悪いではないか。人間とは無関係の神の視点を持ち込むにも程がある。
普通に考えて、主役はあくまで「今」ではないか。
経験によって過去が膨らみ、未来の可能性は減るかも知れない。
忘却により過去は縮小し、希望と夢によって未来は膨らむかも知れない。
そういった中心にあるのが「私という意識にとっての今」の本質であろう。
自循構造が「今」に畳み込まれ、過去も未来も変化する「ように見える」。
そういう時間や空間の捉え方をしていかないと、意識の問題は扱えない。
|
決断
|
|
主体的に決断・選択しているという意識が、「自分」という感覚の底にある。
|
目を瞑って耳を塞ぎ純粋に思考があるだけの状態の私も
確かに“意識”を持っており、頭の中に去来する可能性を崩壊させ、
再吟味し、判断し、記憶として定着させるプロセスを実行している。
記憶は、未来の自分の行動を思い描き、計画的に行動するためにも使われ、
また、過去の経験を体系化し、思索の断片を統合化することにも使われる。
つまり、「今のありようを決断するための材料」として用いられる。
※物理世界と完全に切り離された脳内で、過去の擬似体験を再構築して、
未来の行動を試行(シミュレート)することも出来る。
※原始的な脳であっても記憶は直近の行動予定を溜める役割を持つ。
木の実をもぎ取るという動作一つとっても、腕や指の作動は非常に
複雑であり、動き始めてから考えたのでは絶対に間に合わない。
行動が脳内に閉じる場合でも、物理世界との相互作用を持つ場合でも、
意識が何かを決断する時には、可能性という名の理想的に輝く美しい球体が、
プチプチと音を立てながら「6」とか「咒」とかの具体物に崩壊していく。
《サルトル哲学の援用》(無神論的実存主義)
人間の自意識は、自己の責任において、可能性を具体物に両替する。
人間は「自由の罪」に処せられている。
人間は、自由である以外には存在の仕方を選べないように呪われている。
意識の核心に次々と分け入っていくと、広義の記憶(=脳内の状態)を
対象(モノ)と捉え、主体的に判断する「自意識」が浮かび上がってくる。
この「自意識」は、あらゆる対象を「自分ではないモノ」として意識して
いる以上、「内容空疎(カラッポ)」でなければならない。
人間とは、行動することでしか何者かになれない「実存的存在」である。
言い換えると、核心にある「自意識」は、それ自体は内容空疎であり、
可能性を具体化するというプロセス(行動)においてのみ、その意味が
認められるものである。
※つまり自意識とは何らかの「モノ」ではなく「プロセス」である。
自循論的に言えば、自己が自己を参照するというプロセスであり、
有限であり終わりを迎える宿命を内包しているという前提条件から
可能性を消費する(決断する)よう行動しているものである。
|
自己の意味
|
|
有限性を基盤とする「意味」の本質を捉え、
「自分にとっての世界」「自分にとっての自分」の「意味」を考える。
|
人間にとって人間は特別な存在であり、
人間にとってのこの宇宙と意味世界の全ては、
はまるで人間のためにあるように思われるが、
人間とは関係のない(人間には観測すらできない)ものの総体から見た
その意味世界は、人間にとって無意味だし、その世界から見たら
人間という存在も無意味であろう。
「意味」とは何かを明確に理解し、
私達にとって「有意味な世界の全体」の姿を確認する。
|
自分にとっての世界
|
|
自分はさまざまな意味の重ね合わせであり、それぞれの意味世界全体と対等である。
|
ちょっと考えても「自分」というのは様々な側面を持っている。
・物質としての自分、機械論的・唯物論的自分
・細胞から成立している自分、生命の流れの中にある自分
・純粋に観念的な、脳のどこかにありそうな意識としての独自の自分
・生物学的な種としての自分、動物としての自分、哺乳類としての自分
・人類・知的存在としての自分、男性または女性としての自分
・ある文化、国、宗教、会社組織、仕事、家庭に属し、
特定の役割を持つ自分
・唯一無二の存在としての自分。身体的特徴・性格など。
「自分」と簡単に言っても、こういった種々の意味での自分の重ね合わせ
の総体が自分なのだから、各々をきちんと理解した上で、何について
論じているのか検討する必要がある。
こういった種々の自分の総体と、意味世界全体としての宇宙は相補的な関係にある。
宇宙が先にあって人類が誕生したとか、
人間がいるからこそ宇宙がこうある、といった対立概念は
「宇宙と知的存在は相補的である」という上位概念に止揚されねばならない。
知的存在を内包しない宇宙(自覚しない宇宙)は無意味である。
意味境界を有し内部に充足した意味を持つことを自覚している宇宙だけが意味がある。
様々な意味の重ね合わせである自分Aと、その自分Aにとっての
宇宙A’は、自分Aが宇宙A'に含まれているという距離空間的な
発想から言うと相似的であるし、
観測者-被観測物という対等性の観点から言うと相補的である。
そして、究極的な原理としては同一のものである。
→ブラフマンとアートマンの同一性(梵我一如)
宇宙も勿論意味境界を持つ。無限乱雑空間に接する開放系である。
究極的な意味での自循構造は、閉鎖系というよりも、
無限乱雑空間と隣接する開放系と言った方が良いかもしれない。
→但し、意味論的には無限乱雑空間との情報の出入りは無いし、
あったとしても我々にとってそれらは定義より無意味である。
我々の情報世界は、やはり、我々を中心とした閉鎖系である。
- 「自己」という言葉の定義は案外厄介で、
少なくとも以下の5つの要素が必要である。
- 物理的自己(生命体)
- 物理的非自己(環境)
- 情報的自己(参照・操作対象としての自己)
- 情報的非自己(参照・操作対象としての環境要素)
- 物理的自己の中にあり、情報的自己および情報的非自己を
参照・操作するというプロセス(いわゆる「自己」)
- 私達の意識は、物理的自己や物理的非自己を
直接扱うことは出来ない。
これらが抽象化され、翻訳され、
情報世界にコード化されたもののみが
参照・操作の対象になる。
情報世界と物理世界は非常に遠い距離にあって
間接的に繋がっているが、この繋がりを維持しているのが
深遠で広大な無意識層である。
(その実体は、物理的に可塑性を持ち、情報的に記憶・演算を行う
全身の神経網であり、特に大脳・小脳が重要である。)
一方、情報世界における「対自構造」(自循構造)は、
物理世界の状況に直接依存しない
極めて抽象的な概念であり、情報世界の中のみに存在し、
明瞭で不動のものであり、純粋で、バリエーションが無い。
よって、「自己」を認識する全ての知的生命体は、
「それぞれの自己の核」を持っているのではなく、
その
「自己の核」は情報世界に唯一のもの
であり、
同じものを全員が共有している、
というべきものである。
だからこそ、自己を意識する知的生命体同士は、
理解し合い、語り合い、愛し合うことができる。
「自分が自分であるという感じ」は、
たとえ言葉で明確に定義できなくても、
なんとなく、みんなが、同じもののはずである、と
強固に盲信しているのであるが、
それは実際のところ、本当に全く同じものなのである。
この事情を万人に分かる形で示し、
「有意味な世界」を定義するのが、自循論の主な使命である。
- 何はともあれ先ず第一に、
「自覚する=自分で自分を参照する=自循構造がある」
という事が全ての有意味性の根源であり、
あらゆる世界は「自覚する有意味な世界」と
「無自覚で無意味な世界」に
分けられる、という事が正しいとしよう。
(この場合の「自分」は、たった一人の人間の自我という意味であっても、
情報交換可能な範囲にある全ての生命の
集合的意識/集合的無意識の総体という意味であっても構わない。)
ともかく「自覚する」ということを第一原理に置くのだから、
その内訳を徹底的に合理的にモデル化しておきたい。
- 「自分」という概念を持つ以上は「自分でないもの」という概念も
持っている必要がある。つまり、世界全体の中で自分という範囲
(自我境界線)を把握している。(世界=自己∪¬自己)
- 「自分で自分を参照する」という事は、
「参照される側の自分B」と「参照する側の自分A」がいて、
それは「同じ自分」でありながら、変化した「異なる自分」という
概念を要求する。
「自分」は、その変化の連鎖において、自分が自分であり続けること
(自己同一性)を確認するために「空間」という概念を備えており、
変化から「空間」の概念を取り除いた部分として「時間」という概念も
同時に備えている。(変化=空間差異∪時間差異)
(変化とはそもそもAが非Aになることで、
「Aは非Aではない」という矛盾原理 principle of contradiction に反する。
つまり、時間は直ちに矛盾を引き起こす。)
- 「変化=差異=意味」は、それが明確に異なると理解されるために
本質的に量子化されている。また、変化量は変化しない部分も含んだ
総体に対する割合として意味を持つので、
意味がある以上はその総体は有限である。(有限÷有限=有限、
一方、有限÷無限=ゼロ)
- よって、有意味な自覚する世界は、「空間」「時間」という概念を
内蔵しており、マクロに見てその総体は有限であり、
ミクロに見て至るところ量子化されている。
従ってあらゆる時空の要素は1個2個と数え上げられ、
その合計もたかだか可算有限個である。(自然数の発生)
(ここでの「時空」は、数学的には抽象的な位相空間であり、
宇宙を記述する物理的な時空は、その派生物である。)
- 時空の全ての要素は、自己同一性(自己無矛盾性)を担保として
統一的であり、連続体を形成しているように見えてしまう。
(実数という概念の発生)
このように、「自覚する」という一見単純な言葉も、
「自分A」「自分B」「その変化=差異=意味の認識(関係性)」
という要素を内包しており、
そこから有限で量子化された時空構造を導くだけの深さを持っている。
現代の科学に慣れ親しんでいると、
時空構造から「自覚する」という現象を導く方が自然に思えてしまうだろうが、
自循論の立場では、「自覚する」という現象を出発点に、
物理や数学を含む全ての基礎を再構築していくことになる。
◎自己と世界全体の対等性、自分へのこだわり:
(1) 自己と世界の関係:
我々が我々自身をどう捉えるかという視点は無償で無数に存在する。
あらゆる角度で自分自身を見るということは、
結局、この宇宙全体をあらゆる角度でどう捉えるか、という事に等しい。
→自己を掘り下げるということは、自己を包む世界全体を見るという事。
→自己と世界は対等であり相補的であるという確信。
(2) 自己や世界が「有意味に存在する」ための有限性:
時間的・空間的な有限性・有界性を持つ自循構造の閉鎖系の中にいる
個々の「自覚するもの」が「自己という感じ」を持つ。従って、
この「自己という感じ」には、遥か未来の時間の終わり(オメガ点)が
現在の自分にも織り込まれていることも一役買っている。
(「自己が死」や「宇宙全体の死」や「意味世界の終わり」など。)
→終りがあるから進む意味がある。(終りが無ければ進む意味は無い。)
(3) 限り有る未来の現在における意味:
現在は、過去と未来の有界性(初期条件)に縛られた
範囲内で、可能性(確率)の範囲内で存在(現実)を構成する場である。
→見方を変えると、現在は、未来からのメッセージを受け取っている。
→つまり「現在」は「終わるための」プロセスを実行している。
→結果、可能性を消費し尽くすように作動せざるを得ない。
宇宙に望遠鏡を向ける時、私達は、私達自身をみつめている。
時間、空間、存在、宇宙、素粒子………といったもの全ては、
私達が見るようにしか見えない。
時空が最初にあり、その中に私達がいる………のでは無い。
自分を預けてしまえる絶対的な存在など何もない。
外側へ、外側へと、自分のルーツや存在理由を探し求めて
研究や観測や思索を続ける過程の全ては、
結局は内側へ、内側へと自分を探検する過程なのだ。
「人間を含み切る(人間とは独立の)物理法則や純粋数学の世界がある」
という考えは否定される。それらは、実は、自分自身を対象化している。
一般的な生命として私が感じている宇宙は、
他の生命とも共有できるものだ。
同様に、人間として私が感じている世界は、他の人間とも意見交換ができる。
(科学、哲学、宗教など、人間学一般は、この領域を指し示す。)
しかし、"私"という唯一無二の存在が見上げる宇宙は、
他の誰とも理解し合えない部分があるはずだ。
より抽象的に思考を突き進めると、必然的に絶対零度のような
徹底的ニヒリズムに行き着く。
「世界は完膚なきまでに無意味」という「地面」に足を着ければ、
「謙虚に安心して有意味に生きる」という選択が自然に出来る。
結局は自分しかいない、という、少し寂しい感じのする「自立」
の気持ちとは、背景に世界の無意味さを背負うことではないだろうか。
「哲学」を指向する結果「現に存在してしまっている自分」にこだわり、
それを心底受容することで、真の意味で精神的に「自立」できるようになる。
また、「哲学的思考」に最低限必要なツールは「自分」だけである。
いつでもどこでも、哲学的思考訓練は可能である。
そうして思考の骨格と筋肉を鍛えることで、初めて様々なコトに
安心して興味を持ち、自分自身が流され崩れてしまうことなく
没頭することが出来るようになる。
その骨格は借り物の名言などではなく、確たる地盤の上に築き上げる必要がある。
その、個々人の基盤形成のための概念装置として「自循」は有用である。
◎生命・意識と世界の対等性(唯我論)
生命は、それ自体で意味的に完結する、という自循構造を持っている。
………もしくは、持たされてしまっている。従って、超越的な神が、
「あなたはこう生きなさい」などと正解を説明してくれたりはしない。
生命が生きること、それ自体は無目的であり、
生命は「偶然、いのちを与えられてしまった」としか言いようがない。
こうして、一つの方向として、生命の自己完結性から、
「世界のあらゆるものを生み出しているのは生命である」、
「生命=世界の認識者=創造者」という考え方が出てくる。
(唯脳論、脳産教義、人間原理宇宙論など。)
- 意識とは「変容し続ける、再現性のない、一体の質」である。
一方、科学は、「時空に固定された、再現性のある、一群の量」を扱う。
私達の経験のうち、純粋な意識の性質を、可能な限り丹念に除外して、
繰り返し現れると認識される現象間の関係だけを
「法則」として表現するのが、科学の手法であろう。
だから、意識の問題を科学的手法で解明しようとすることには、
根本的な無理がある。
主観を丹念に除外して得た客観的方法で、主観を扱えるはずがあろうか。
意識を顕微鏡の下に置くことは出来ない。
意識は、二度と同じ状態にはならない、不可分な一体の質なのである。
意識が広がる情報世界を、<自核>を中心とするシンボルの
意味ネットワークとしてモデル化したとしても、
その空間的なモデル化をした瞬間に失われたものがある。
シンボルの相互侵食性や、ネットワーク全体の非局所的・持続的な変化などである。
深い自己省察によって、モデルが「今、私達の感じている、この意識そのもの」の特徴を、
本当にうまく代表できているのか、何度も確認されねばならない。
(単なる上手い比喩なのか、本質を抽象化したのかを、区別せねばならない。)
そして、このモデルは、
「なぜ、私達は、宇宙をこのように捉えることしか出来ないのか」
「なぜ、私達は、私が私であるというこの独特の感覚を持つのか」
という2つの疑問に対して、同時に答えることが出来るものでなければならない。
そうでなければ、物理世界と情報世界はバラバラのままだ。
これまで人類が積み上げてきた、あらゆる知的活動の成果を、
少しも損なうことなく、丸ごと活かして、新しい枠組みの中に位置づけるのでなければ、
新しいモデルをわざわざ作成する意味もない。
だからこそ、自循論では、世界の成り立ちを、まず、
物理世界と情報世界の相互依存として捉えるのである。
これが、科学・哲学・宗教を統合的に捉えるための地図である。
- もしも、この世界の成り立ちが、本当に本質的に
物理世界と情報世界の相互依存関係にあるとしたら、
私達にとっての有意味な世界の全体は、
安定を担保する物理と、自由を担保する精神の、
妥協の産物である、と言っても良いだろう。
(抽象的な意味空間において)
お互いが逸脱しないように、靴紐のように
世界を編み上げてきたわけである。
しかし、その関係は完全に厳密に対応するわけではなく、
「緩み」がある。(もし完全に対応するなら、
わざわざ2つの世界を持ち出す必要も無い。)
この「緩み」によって、物理世界は、情報に何の影響も与えないような
幾つかのバージョンを取り得る。
例えば、ある質点の、プランク長以下の位置のズレである。
また、情報世界は、物理に何の影響も与えないような
幾つかのバージョンを取り得る。
例えば、全く同じ物理状態の上に実現し得る、
僅かに異なる精神の可能性である。
ここに「自由」なる現象を認めるための根本原理を求めることが出来る。
私達(自意識)は、物理法則に全く抵触することなく、
複数の情報状態を選択することが出来る。
これは単なる比喩だが、コップに半分入っている水を見て、私達は
「まだ半分もある」「もう半分しか無い」という両方の情報を重ねることが出来る。
その思考の元となった全身の粒子運動の僅かな違いは、
身体の挙動や脳内の電気信号の分布の幽(かす)かな違いのどちらかを選ばせ、
それが積もり積もって、最終的には
コップを見ているだけの自分と、慌てて飲み干す自分のどちらかに辿り着かせる。
どちらの時系列も、たとえマクスウェルの悪魔が完璧に観測していたとしても、
全く何の矛盾も飛躍も無い、自然な物理現象であるが、
その結果は天と地ほども違う。その原因は、「見る」側の立場にある
情報世界以外には求められない。
実は、物理世界というのは、多数の情報世界(自意識)が形作る
統計的に安定な客観世界という以上のものではないため、
たった一人の情報世界のスーパーヒーローが、
その卓越した思考力と集中力で、一瞬にして物理法則を捻じ曲げる、
…といった事態は確率的に起こらないのだが、
裏を返せばつまり、確率的には起こり得るのである。
多くの人の思念のベクトルが一致したなら、なおさらだ。
『素粒子とは、狂信的な科学者の集団が、物理世界を捻じ曲げて
物理的真実にしてしまったところのものである。』
100人が飛行機を見て「落ちろ」と念じると、
本当に落ちてしまう、という都市伝説は、何故か素通りできない。
車を運転している時、カーブの先のあそこに辿り着こうと思うと、
実際その方向に運転することが出来る。
ある有名な経営者は、「宇宙には強く念じたことは実現するという
絶対法則がある」と公言する。
…もう、私達は、唯物論にしがみついて安心するわけには行かない。
この意味世界は、物理世界と情報世界の妥協の産物である。
私達の一瞬一瞬の決断には、物理的現象を僅かに捻じ曲げ続ける力があるのだ。
- 『
内部に一切の物質を含まない純粋時空と、
記憶や認識を全く伴わない純粋意識は、
比喩ではなく、真に同一のものである。』
この仮説に思い至った時、私は何故だか、これは正しいと直観し、
物理世界と情報世界を繋ぐ共通基盤として、
この仮説が最も相応しいと感じた。
もし私から、経験や思考力を徐々に奪い、
個性や判断力が失われていったとして、
最後に残るものは、きっとカラッポの時空と
「全く同じ」なのだろう、と納得したのである。
時空は意識の必要十分条件であろうか。
まず、時空とは、時間の流れに沿って空間の変化を意識(観測)する、
という形式を意味する。「だんだん大きくなる円」という
二次元空間+一次元時間は、その時空の内部に捉われて、
円をそのように観測する意識があるから意味を持つのである。
もし、意識を除外すれば、それは単なる「円錐」という
三次元空間としての意味しか持たない。
結局、時空を設定する以上は、意識の存在が前提となるのであり、
時空は意識の十分条件である。
次に、意識という現象が成立するためには、その中心に
「自覚」が必要であり、
少なくとも「自」と「自以外」を隔てる空間(距離)の概念と、
「自」が「(自を含む)一瞬前の世界」を認識(観測)する
という時間の概念が必要である。
結局、時空は、意識にとっての必要条件である。
以上より、時空は意識の必要十分条件であり、同値である。
意識というのは、膨大な情報から、ある断面を切り取る働きを持つ。
「波束の崩壊」も、可能性空間から意識が存在を切り取ったということなのだ。
無限乱雑空間に散らばる前物質的な塵は、
意識というサーチライトに照らされて、初めて物質に昇華する。
また、意識は、物質的基盤と生命に支えられて初めて持続する。
この相互関係が十分に高度化され、安定したところに、
人間の意識のような明確な知性が実現されることになる。
たまたま、物質と精神のありようがバランスしたところに、
意味ある世界は照らし出される。
内部に物質を含まない純粋時空に、素粒子を一個置いた状態と、
何ら経験や知識を持たない純粋意識に、1ビットの情報を入力した状態を、
比較するのが、この仮説を検証する次のステップになるだろう。
「純粋時空=純粋意識」であるという思考基盤の上に、
その純粋性を破る何かを加えた時の、そのもの自体の動きや、
環境の方を歪める働きについて、共通性と相違点を調べることで、
物理世界と情報世界の繋がりや役割分担のありようを、
定式化できると考えられる。
|
自分にとっての自分
|
|
自分を基準にすれば、どんな小さな自分の変化も大きな意味があるように思える。
|
◎意味とは:
意味とは誤差である。
もしくは、ある視点から生じた軸の周囲に分極した、
異種のプラスとマイナスの複雑な蓄積である。
何でもあり、だから何の意味もない
無限乱雑空間の中で、偶然もつれるようにして現出した、この宇宙………
もしくは、私自身。そして、快楽・苦痛、美・醜、善・悪、生・死は、
全て等しく「意味」の資格を持つ。
肯定的なニュアンスを持つほうだけが「意味」ではない。
そして、人生に於いては、意味のダイナミック・レンジを広げることが重要だ。
死・自殺・殺人といったことを徹底的に考えずに、生・一回限りの人生・人間社会での
相互協調関係を、きちんと知ることが出来るだろうか。
闇を知らずに光の絵は描けない。
「何もしない演技」が出来なければ、他の一切の演技も「自分の部分修正」に
過ぎなくなる。片方だけ考えるのはよそう。
あらゆる「意味」は、何らかのピボット(軸)を中心に偶発したもので、
だから必ず「軸」があり、「反対側」がある。美を求めるなら、醜も求めよ。
そして、美醜を判断する自分というものについて、深く考察せよ。
◎自分が自分を参照する時に生まれる僅かな誤差と意味の最大化
意味とは差異であり、無限の中では差異は生じない。
視点は無償で選択できるが、それが一つの軸(ピボット)となり、
その軸の周囲に生じた概念・観測結果・事実の渦に、
更に軸(ピボット)を任意に導入することで、
極めて複雑な概念・観測結果・事実が現出する。
※人間にとっての世界が組み上がる。
自循では、“一つ前”の自己を、“今”の自己が
参照する、という構造を取るが、この時の「差異」が意味を発生させる。
自己は、「変わらない部分」を大量に含んでおり、また、
「変わりすぎて変化とも捉えられない部分」をも含んでいる。
自らが認識できる変化は、ソシュールの言うように
文化を背景に恣意的に体系化され、表現(言葉)と内容(言葉が示すもの)が結びついて
記号(表象)となる。
「記号 sign」=「表すもの signifant」+「意味されるもの signifie」
※文化が異なると、差異の体系も変わる。ある色の名前を細かく言い分ける
とか、"rice"は日本では米・稲・飯と言い分ける、など。
人間は“差異”でしか“意味”を認識できない。
自分で自分を参照する時に「意味がある」と感じるのは何故かというと、
膨大な「変わらないもの」(変わったと捉えることができないものを含む)を背景に
僅かな「変わったもの」を、恣意的・相対的に識別するからである。
そして、その“意味”は、人間自身にとっては非常に格別なものである。
超越者の視点から見れば、何かの誤謬に過ぎないものだとしても。
- 意識とは差異検出器である。
意識というのは「差異検知器」であるとも言える。
これは物理世界に対しても情報世界に対しても同様で、
意識は差異以外のものを捉えることが出来ない。
(カエルが動いているものしか見えないのと似ている。)
意識が始まってから終わるまで(意識にとって)ずっと変わらないものは
その実態がどんなに複雑で豊穣で雄弁でも、(意識にとって)無であり、
真空である。有意味な世界の成り立ちは意識に求められるから、
「まず」「変化ありき」である。
- 一方、「移動」も変化の一種だが、ある存在が一瞬光速を超えると
それは意識を中心とする意味世界の体系では
「同じものが位置を変えた」という差異で捉えるのではなく、
「ある場所でAが消滅し、別の場所で良く似た別のBが生成した」
つまり「AとBの同一性を理解しようがない」。
差異検知器である意識の分解能の本質的限界が
光速という現象に対応している。
(これは勿論、自循論的な世界観として、「ある宇宙が内包する
意識の総体」が内側から宇宙を照らす方法が物理法則そのもので、
一方、意識を支える脳や生命は、その物理法則に則って作られている、
という自己循環を前提とした言い方である。
光速度が先ずあって、だからこそ情報世界の分解能にも
本質的な限界がある、という言い方をしても良い。
両者は同じことである。)
|
有限原理
|
|
無限は無意味である。有意味なものは必ず何らかの制限を持っている。
|
・『自然数は神の作ったものだが、他は人間の作ったものである。』
-レオポルト・クロネッカー
- 無限乱雑空間に対して、
気まぐれに何か適当な視点を導入するという行為、
それ自体は無数に行われて良く、
その結果として選択された世界は、勝手に幾らでも存在していて良い。
これを「視点の無償性」と言う。
- このようにして選択された世界は、
無数に存在する無限乱雑空間上の無数のサンプルに過ぎないが、
その一つに『着目』すると、
そこは選択された視点の有限性に対応した、
有限で有意味な、唯一無二の《世界》になっている。
有意味性は必ずこのように、無限から何かを選択して制限を加え、
有限性を確保することで発生する、という信念を
「有限原理」と言う。
- 無限乱雑空間上に無数に存在する世界のうち、
今、ここにある世界に『着目』しているのは誰だろうか。
無限乱雑空間の全てを統べる神なのだろうか。
そうではなく、この世界に『着目』しているのは、この世界の住人であり、
私達人間が意識しているこの世界に視点を導入し、着目しているのは、
私達、人間だけである。
◎意味-制限対【有限原理】
・無限は意味を為さない。
無限という概念が意味を有するのは、この「現実」という有限の世界の
近似として思考力や計算量の節約に役立つ場合である。
ちっぽけな一生命個体としての「私」は開放系であり、
私の表皮の外側にも空間は広がっており内側と相互作用するし、
私の生まれるより前と死んだ後にも時間は広がっており
やはり私の生きている時間と相互作用する。
(ここで既に暗に未来から過去への作用が仮定されている。)
世界のありようは決まっている。
“可能性の状態”が、時間的・空間的境界条件により形作られる。
それは、さまざまな理由で“具体的な事物”に崩壊する。
※二重スリットの実験で干渉縞模様を観測するために電子ビームを
作ったりスリットを設置したり感光板を立てたりすることで
作られた可能性の波は意図的に一つの粒子状態に崩壊させられる。
その崩壊の仕方は自己無矛盾である限り任意性がある。
※人間の脳は、このの崩壊のプロセスを利用し、高度な自由性を自覚する
特異な人間の自意識を実現している。
自己無矛盾であるためには、時間の始まり(α点)を含む過去だけでなく、
時間の終り(Ω点)を含む未来とも関係することになる。
しかしながら自循論的世界では「いつか終る世界だけが有意味」であり
「いつか終ることの条件」が体細胞のテロメアのように自分(自循構造)の中に
予め仕込まれていると考えるので、「未来からのメッセージ」
「時間を逆流する情報」といった哲学的困難を招く考察は除外する。
※自分が未来からのメッセージを受け取っている、と考える代わりに、
自分自身が未来のどこかで終わるという情報を内在している、と考える。
この宇宙は、私の脳と同じ形をしている。
この宇宙も、私の意識も、所与の境界条件の中で与えられた
“可能性の状態”の範囲内で具体化されているが、
その範囲で、自由に可能性を現実に崩壊させることが出来る任意性を持つ。
この、一対の制約と任意性が意味と意識の本質であろう。
※この文章自体も、始まりがあり、終わりがあり、文章の構成上
“可能性の状態”は決まっており、その制約は、どの一文字一文字の
有りようにも折り畳まれている。しかし、具体的にどのような単語や
記号を選択するか(具体的な文字に崩壊させるか)については
自己無矛盾な範囲で一定の任意性がある。
制約感が無ければ、無限の中に放り出された私は
意味を感じることが出来ない。(意味-制約対の原則)
※後者の意味は「自分が選択しなかった世界を意識的・無意識的に感じる」
ということである。
※並行宇宙論的に言えば、自分が乗っている枝以外の宇宙を
確信するからこそ、自分の選択の任意性・恣意性・主体性を
確信できるのである。
この任意性が無ければ、私は自分が主体的な存在であると
感じることが出来ない。
“制約”は、物理法則やDNA、脳細胞の構造などの中に
既に分離不可能な形で折り畳まれているが、
とにかく私の意識は意識の及ぶ意味的な範囲が(ありがたくも)
有限であるということを感じさせる基盤になっている。
これが無ければ「自分という感覚」は生まれないだろう。
◎量子(ディジタル)の必然性:
(1) 宇宙開闢の直前の1クロノン(プランク・エポック)
ビックバン直前の「人類にとって無意味な1単位時間」
(2) 自循は意味と無意味の境界を明確にする。
現在の物理的見地で無意味と考えられる領域を
なぜ無意味かと考えることも自循の重要な考察対象である。
(3) 量子飛躍という一見不可解な現象も、有限原理に基づき、
意識が存在する場では、観測に伴い必然的に必要とされる
現象なのではないか。(無限に滑らかな世界は意味を勝ち得ない。)
- 有限性は自己参照における不可知性を保証する重要な原理である。
- プランク・スケール以下の出来事が不可知であることや、
光速度を越えた情報交換が出来ないことと引き換えに
この世界が意味を勝ち得ているという構造と、
無意識層の内観が不可能であることと引き換えに
自分の意識が主体性を勝ち得ているという構造は、
不可知性が意味を保証するという意味において共通している。
また、論理的に当然であるが、「知らない」ことを前提としない限り、
「知る」という状態を自己認識することはできない。
- 事物そのもの、実在、究極の真理、神の存在、客観的存在を、
人間は知ることが出来ない、という主張を
不可知論 agnosticism という。
自循論では、
不可知の境界を維持するからこそ豊かな意味世界が意識可能となる、
という「積極的不可知論」の立場を取り、
これまでの不可知論を「消極的不可知論」と呼ぶ。
- 「積極的不可知論」は、「わからなくたって良いではないか」という
不可知論の単なる前向きで肯定的な捉え方を意味するのではなく、
意味世界が立ち現われるには
是非とも不可知性が必要なのだ、という主張である。
もしも全てが分かってしまったら、
世界はその瞬間に凍りつき、無意味なものになり、
あらゆる意識は瓦解する。
- 逆に言うと、この宇宙は、宇宙自身を認識する人間という存在を
その内部に生み出したが、人間は宇宙を全て理解し尽くすことで、
宇宙を終わらせるのかも知れない。
一般に、無限に生まれ消失する全ての宇宙と呼べる宇宙
(宇宙それ自体を認識する生命を内包している宇宙=自覚する宇宙)は、
物理的に変化が生じなくなるという終わり方(ビッグ・クランチとか熱的死、物理的終焉)か、
その内部に自身を説明し切る存在が生じるという終わり方(意味世界の瓦解、情報的終焉)の
どちらかになるのではないだろうか。
更に、人間自身がこれを成し遂げるのではなく、
既知の物理法則を越えた別の宇宙の知的存在が、
宇宙の根幹を為す理論を情報として教えてくれた瞬間に、
全人類とこの意味世界は情報的に即死するのかも知れない。
すなわち、「不可知」を壊すことは原理的に情報的兵器に成り得る。
|
自己と意識
|
|
意識のメカニズムを明らかにし、
同時に「有意味な、意識される世界の全て」のメカニズムを明らかにする。
|
人間にとっての世界とは、人間が意識する世界の全てであって、
私達が世界を見るということは、自分で自分を見ることに他ならない。
そして、「意識」と「世界」を貫く原理原則は、
突き詰めれば以下の3つの本質に支えられている。
- 自分で自分を参照するというプロセスの連鎖である
- 森羅万象は有意味である限り総体の大きさも細部の粒度も有限である
- 自己無矛盾である限り視点を自由に選択できる任意性が確保されている
人間が人間の持つ自由性に基づき選択した視点から
組み上げた世界は、
いかに人間と独立な客観的存在であると物理学者が言ったとしても、
人間にとっての世界でしかない。
人間が人間のやり方で宇宙を観測するということは
自分で自分を見るということに他ならない。
人間にとっての世界の全てと、カエルにとっての世界の全ては、異なる。
私にとっての世界の全てと、あなたにとっての世界の全ても、異なる。
人間同士が丹念に主観を取り除き、僅かに残滓のように残った共通集合が
人類共通の客観であり、人間にとっての世界のモデルである。
|
意識のシステム
|
|
意識はどのようなシステムの上に立ち現われるのかを明らかにする
|
- 突き詰めると、「意識」とは、時間の最先端にある
世界を受動的に認識する一方的な情報の受け手が、
「世界の中にいる自分」のことまで「ついでに」認識してしまっている状況
であると言える。
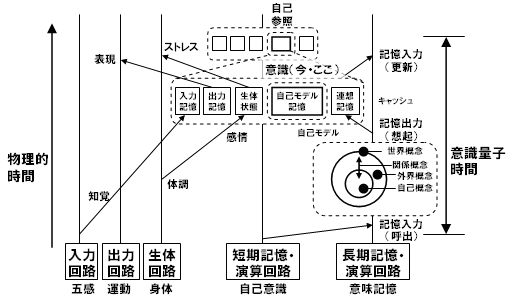
- 「意識」の居場所である「今・ここ」を中心に考える。
- 先ず、「意識」は短期記憶の機能と演算の機能が重ね合わされた場である。
- 「意識の場」には大きく分けて以下の周辺モジュールが接続している。
- 外界からの情報を知覚する入力回路
- 外界へ影響を与える出力回路
- 体内の状態である生体回路
- さまざまな記憶を貯蔵する長期記憶回路
これらの要素それぞれが「意識」の中の特定の短期記憶領域に流入してくる。
「入力記憶-出力記憶-生体状態記憶-自己モデル記憶-連想記憶」の
一組の関係を、ここでは「自己モデル」とする。
- 「自己モデル」の全体は、次の演算の過程では「自己モデル記憶」として参照される。
このような入れ子構造(自己参照性)を実現するプロセスこそが
「意識」という現象である。
- 「短期記憶・演算回路」は、外界や体内状態や長期記憶との入出力に絶えず曝され、
一箇所で自己更新のプロセスを継続する「意識の場」である。
ある瞬間の「意識の場」は、入力情報の波に洗われて更新されると、
それはもはや渾然一体となった自己そのものであり、
次の瞬間には「一瞬前の自己自身」(自己モデル記憶)として扱われる。
- このプロセス自体は、人間の場合、全て脳内の電気的・化学的なプロセスに還元され、
機械論的である。
このプロセスが一瞬一瞬にどのような調和・判断を行うかは、
自分の脳という有限かつ固有の器質の中で、
全ての体験を通して自己更新を続けて育ち、更に進化中の
「短期記憶・演算回路」の情報的な構造に依存する。
つまり、自分のこれまでの人生そのものが積み重なって凝縮され続けてきた回路が
調和・判断を行っているのである。
意識の働きが機械論的に説明できるからと言って、
意識が主体性を持たないと結論する必要は無い。
- 意識と呼べる現象は持たないが、
神経系(脳)は持っている下等動物が、
効率的に生き残るために、
抽象化・粗視化・パターンマッチングによって
「高い」「尖っている」「熱い」「痛い」「甘い」
といった概念を情報処理できるに至ったとしても、
驚くには値しない。
目を細めて共通項を大雑把に把握して反応しているだけ、
とも言えるからだ。
しかし、人間のような知的存在が、
「~でない」という否定概念を、
どうやって獲得し得たのかは大変な謎である。
「~である」という知覚を、どんなに延長し、
共通化・複合化・抽象化させても、
「~でない」という概念には到達し得ないと思われるからだ。
おそらく、視界の中にしょっちゅう現れる
自分の影や身体の一部を、
興味のある外界から「差し引く」という必要性から、
「自分の身体=外界でないもの」が浮かび上がり、
それが純化されて純粋否定概念「~でない」に辿り着いたのではないか。
そして、あらゆる意味で「見られるものでないもの」として、
「見るもの」すなわち最も純粋な「自分」という概念が
創作されたのではないか。
何を見ようが、何を聴こうが、何に触ろうが、
何を嗅ごうが、何を味わおうが、
「それ」ではないもの………
あらゆるものでないもの………
それは一体、何だ?
………自分だ。
- 肉体の檻に捕われた神経回路が十分に発達して
否定概念すら扱えるようになると、
あらゆる「感じられる側のもの」の否定として、
「感じる側のもの」という概念が少しずつ少しずつ降り積もり、
ついには高階の抽象概念である
純粋な「自」が発見されることになる。
さて、神経回路のカタマリが、
「自」という概念を扱えるようになっただけで、
今こうして私が感じてる「私が私である感じ」が
発生するものであろうか?
自分が単に外界の刺激に反応する自動機械ではなく、
自分の「意識のスクリーン」に外界を映し出し、内観する、
主体的な存在に昇格するものであろうか?
おそらく思考基盤としての脳の殆ど全ての神経回路が
フィードバック回路であることと無関係ではなく、
「自」という概念は本質的に外界に対応物が無いために
否応無く自分自身の中で処理され続ける概念である。
この、脳の中を満たす定常波のような電気信号のループが、
情報空間においては特異点としての「自」に対応するのであり、
意識の核を為すものとなっているはずだ。
物理空間における「自」の表現とは、無意味にひたすら
グルグル回るものであり、外部擾乱によって
この円環運動が乱された後、また円に戻ろうとする時、
この作用・反作用を人は「意識」なり「クオリア」と
感じるのではないだろうか。
現実の脳では、この円環運動は脳内を静かに満たす
ホワイトノイズのような電流で、現在の技術では
詳細な観測をすることは出来ないが、
自循論の予言が正しければ、意識(覚醒)状態に対応する
脳内の定常波的な電流分布が、
いずれ発見・同定されるはずである。
それは、幼児においても睡眠時にも曖昧であり、
下等動物では観測されず、
健常な成人の覚醒時の脳において顕著に表れるパターンのはずである。
- ベイトソンは、「~ない」という否定概念こそが
身振り手振りと異なる情報的意味に特有なものであるとしている。
ウィルデンは、「~ない」とは、Aと非Aの境界の認識であるとしている。
一方、ラカンによれば、自己が完全な実体となるためには、
「自己」と「自己の像」の間の分裂を克服される必要がある。
自己の発見のために必要だった否定概念は、
時間と自己を生み出すと同時に、
不可避的に「自己」と「自己の像」の本質的分離をも生み出した。
しかし、私達知的存在は、更なる抽象化により、
「変化し続ける定常」としての「自」
という最抽象概念にまで、
とっくに辿り着いている。
それは理屈で分解するのは少々骨が折れる作業だとしても、
「自分が自分であるという感じ」として、
すなわち「自己のクオリア」として、どの一瞬にも
リアルに直観していることである。
脳は、この宇宙で一番複雑な構造物かも知れないが、
結局のところ、脳に可能なものは抽象化だけである。
一体どのような物理法則が、生命を生み出し、更にその内部に
「自」という概念の発見にまで到達できる抽象化装置を
創造し得るのかは、まだまだ分からないだろう。
とにかく、少なくとも、「我々の住む、この宇宙の物理法則」は、
惑星を生み出し、生命を育み、
人間の脳という「自」なる概念を発見できるほどに
高度な抽象化装置を創造できるものであった、とは言える。
なお、宇宙は、私達が思っているよりもずっと広く、
ずっと複雑であるかも知れない。しかし、物理法則とは、
「自」という概念を持った存在が、その存在の理解のために
必要十分な範疇の法則のみを抽出したものなのであり、
その意味で、究極の物理法則というものは、
「自」を生み出すメタ法則のパラメータを
個々のケースに即して決定したものであると言える。
この意味で、「自」が属する情報世界と、
生命が属する物理世界は、どちらがより根源的であるか、
というものではなく、相互依存関係にあるのである。
まず、全て(無限乱雑空間)がある。
その中に、物理法則に従って時間発展する、あらゆる可能世界がある。
認識が、そのうち、たった一本の枝を選び取り、捉われ、物理世界とする。
認識は、選び取られなかった世界を、任意に思い描き、情報世界とする。
- どうも、この世界は、「目に見えている世界」に寄り添うように、
「目には見えない世界」の層があるような構造になっているようだ。
つまり、この意味世界は、《意識》が「物理世界」に「情報世界」を
重ねて記述するという構造で成立しているように思われるのである。
|
視点(世界)1 |
視点(世界)2 |
物質
(情報を符号化し宿すもの) |
情報
(物質のありようを決めるもの) |
物質
(可能性に導かれるもの) |
可能性
(物質のありようを決める境界条件) |
| 客観 |
主観 |
|
古典物理学的世界 |
量子力学的世界 |
フェルミオン
(物質を構成する) |
ボソン
(力を構成する) |
| 一箇所に一つ |
一箇所に複数
(重ね合わせ)
|
局所性
(現象は光速以下でしか影響し合わない) |
非局所性
(時間・空間がどんなに隔たっていても瞬時に影響する) |
粒子性
(時空的記述)
(一つのものが、いつ、どこにあるか) |
波動性
(因果的記述)
(ある原因が伝播して、どう影響を及ぼしていくか) |
プランク長以上
(時間的・空間的な記述が可能) |
プランク長以下
(時間的・空間的な記述が不可能) |
素粒子
(量子ポテンシャルに導かれるもの) |
量子ポテンシャル
(素粒子を導くもの) |
|
実数 (real number)
|
虚数 (imaginary number)
|
| 物理学 |
形而上学 |
| 現実界 |
イデア界 |
|
意識 |
集合的無意識
|
身体
(物体としての) |
DNA
(情報としての) |
|
生命体 |
霊 |
人間
(神に導かれるもの) |
神
(人間を導くもの) |
|
エネルギーの有償性 |
視点の無償性 |
|
相補性 |
|
観測問題 |
- この二重性は、《物質的世界》に、《意識》が重ね描きした《情報的世界》
であると捉えられる。
- より本質的には、《意識》の総体が維持している《意味世界》全体の中から、
「自分が自分を参照する」という特異点としての《意識》を除去し、
客観化・自己疎外化を繰り返して蒸留したものが《物質的世界》なのであり、
そもそも《物質的世界》は《意味世界》全体の一部分に過ぎない。
- だから、《意味世界》全体を、《物質的世界》と捉えるか、
物質的な意味を象捨した《情報的世界》として捉えるかは、
視点の選び方に過ぎない。
この宇宙では、
ある境界条件の制約下で“可能性の状態”は決まっているが、
これを現実に崩壊させる(可能性を消費して具体化する)ことは
自己無矛盾である限り任意性があるように見える。
脳内で複数の可能性の中から何かを決断することと、
ミクロな相手を観測することで可能性の波が崩壊して一つの粒子になる事は、
アナロジー以上にとても良く似ている。
観測も決断も意識も思考も、
自己無矛盾な可能性たちの中から1つの具体化物を選択する、
というプロセスという意味では同じものだ。
プラトン哲学の中心概念にあった「イデア」は
理性によってのみ認識される実在とされ、
感覚的世界の具体化された物質の本質・原型とか、
永遠不変の価値判断の基準とされたが、
これは、感覚的に、この意味世界全体の境界条件が規定する
“可能性の状態”の総体と、
“可能性の状態”および“具体化された物質”を運用する
公理・法則・計算規則の総体を指していたのではないか。
本質の世界は“具体物に崩壊してしまったこの世界”の
混沌性から隔離される。
“具体的な物質”の有りようは、
可逆的に原型としての“可能性の状態”を乱したりはしない。
この一方向性が、時間の一方向性の正体である。
→時間の矢
※この説明は、「崩壊」に拘りすぎているように思う。
「崩壊」とは「視点の切り替え」の一つの様態に過ぎない、
とした方が自然ではないか。
※しかし我々は一度決断したことを放棄して、また可能性の状態に
戻すことは出来ない。やはり一方向性があるように思われる。
※可能性とはテロメアのようなものだろうか。宇宙は、可能性
を使い果たすと、状態が完全に定まり、死ぬのだろうか。
※「一つの現実世界に、二つの数学的空間が対応しておいて、
その二つの数学的空間を切り替えるのが、観測だ」
…【視点の無償性】
・ 個々の要素がたがいに区別不可能である空間 (可能性の状態)
・ 個々の要素がたがいに区別可能である空間 (具体化された物質)
→途中観測は、途中で具体化している。(別の事象)
そういう風に見ようとすれば、そういう現実が現れる。
崩壊のさせ方に自由度がある。
※途中観測の有無は、存在確率を変えたのではなくて、
事象そのものを変えたのだ。
→矛盾するものが並存しているわけではない。
視点(数学空間)を切り替えれば違うものが見えるというだけ。
- 2つの世界の成立機序
- 自循論では、「自」が「無限乱雑空間」から意味のある世界を
どのように切り出すのかを論じる。
その結果として、意識や自由意志の成り立ちを明らかにし、
時間や物理法則の根源的な意味を示す。
- この理論を理解するために、私たちが見ている宇宙にある
「物質」と「力」とは一体何なのか、
つまり物理法則とは何であるのかの説明を試みよう。
- その前に、重要な(しかし当たり前の)真理を再確認しておこう。
【私たち】が知り得る全ての物理法則は、徹頭徹尾、
直接的または間接的に【私たち】が知覚できるもののみから形作られている。
一方で、星や生命や、人類の脳などの、【私たち】という意識を支える
全ての物体は、物理法則に従って存在している。
この、物理法則と【私たち】の相互依存関係を、
先ずは素直に認めよう。
- さて、全ての出発点は、「無限乱雑空間」である。
無限乱雑空間は、無限に細かく、無限に大きく、無限次元を持つ、
何の法則性も無い、どこまでも乱雑な空間である。
この宇宙の歴史の全てが、その中のどこかには無限個含まれているし、
この宇宙と少しずつ状況の違う無限のバリエーションの宇宙も、
それぞれ無限個含まれている。
この宇宙にそっくりだが、1999年に突然消滅する出来損ないの宇宙もあれば、
全く生命現象を含まない宇宙もあれば、
宇宙と呼ぶこともできない単なる幾何学模様の100次元空間の断片もある。
ところで、無限乱雑空間そのものには、時間という概念は無い。
ただ、ひたすら、乱雑な空間が「ある」だけだ。
あなたの一生は、「どこを切ってもあなたである金太郎飴」のように、
無限乱雑空間のどこかに凍結されて横たわっている。
その一端は受精卵であり、もう一端は遺体である。
その全く同じ金太郎飴が無限個存在するし、
少しずつ形状の異なるヴァージョンも、それぞれ無限個ある。
このように、無限乱雑空間には、ありとあらゆる可能性が、
どれも無限個ある。無限乱雑空間は、考え得る限り最大の空間であり、
それゆえ、全くの無意味である。
- 今、【私たち】を包んでいる「この宇宙」とは、
【私たち】が【私たち】であるのに必要十分なだけの空間を、
無限乱雑空間から【私たち】自身が切り取ったものである。
(「この宇宙」は、徹頭徹尾、【私たち】が知覚できるもの
のみから成り立っている、ということを思い出そう。)
だから、まさにこの宇宙が今あるがごとく存在することには、
【私たち】が【私たち】であるという以上の理由は、全く無い。
そして、【私たち】は、切り取った宇宙の内部にいるのだから、
【私たち】が存在する理由すらも、【私たち】以外には有り得ないのだ。
ある機能(知性)が、その機能なりのやり方で周囲を照らし(認識し)、
その照らされた領域(宇宙)の法則が、
その機能(知性)を生み出すための環境になっている。
この循環は、次のような譬え話に似ている。
『何体かの組み立てロボットが懸命に部品を生産し続けたら、
それら全体は、ちょうどその組み立てロボット自身の
生産工場になっていましたとさ。』
…そんな偶然が、本当に有りえるのだろうか。
有り得るのだ。
無限乱雑空間の中には、そのような奇跡的なバランスを持っている領域が
幾らあっても構わない。
それどころか、そのような領域は、無限種類あって、各々が無限個あるのだ。
しかし、「切り取られた一個の領域」だけを見れば、
それは他とは全く隔絶された自己完結した宇宙であり、
ただ単に、【私たち】が必要な分だけの粗さと大きさを持つ宇宙を、
【私たち】自身の責任において、無限乱雑空間から切り取っているのである。
【私たち】にとっての【私たち】は、一個しか無い。
- さて、ここで改めて、私たちの宇宙を眺めてみよう。
そこには物質があり、力によって絶え間なく運動している。
素粒子の標準模型によれば、私たちの宇宙は
6種類のクォーク(トップ、ボトム、チャーム、ストレンジ、アップ、ダウン)と
4種類の力(万有引力、電磁気力、強い力、弱い力)で構成されている。
2つの物質粒子の間に力が働くのは、力を媒介するゲージ粒子が交換されるからだ、
と説明される。電磁気力はゲージ粒子である光子(フォトン)により媒介される。
しかし、2つの物質粒子の間でゲージ粒子がキャッチボールされると
どうして物質が引き合ったり反発し合ったりするのだろうか。
そもそも、どうやって、どこにいるかも分からない相手に向かって
キャッチボールができるのだろうか。
粒子による描像は、確かにイメージし易いが、力を説明するには
ちょっと相応しくない面もある。ここは、量子力学のもう一つの視点、
すなわち波による描像を用いた方が良いだろう。
ある荷電粒子Aがある場合、実は、Aは空間上のある1点に
粒子として存在しているのではなく、ある1点を中心とした
一定の範囲に波として漂っている。この波は、光の速さで波打っている。
もう一つの荷電粒子Bも、ある1点を中心とした波を纏っている。
湖面の2点に、石を投げ込んで出来た時の波紋を思い浮かべると良いだろう。
A、B両者が生み出す波は、お互いに干渉して、新たな模様を描き出す。
(AとBの間を複雑に行き交うように見えるモアレのような模様の総体を、
粒子的描像では「ゲージ粒子が交換される」とイメージするのであろう。)
そして、A、Bは、お互いの波でお互いを洗い合う。
その結果として、波の中心が、引き寄せあう方向に移動する場合と、
離れ合う方向に移動する場合がある。これが引力と斥力に相当する。
この波は、実際は、場所ごとに、A、Bが粒子として発見される確率を表している。
Aの波が高いところでは、Aが粒子として発見される確率が高い。
AとBの確率分布は、波か重なり合うことで変化する。
私たちは、波そのものを観測することは無い。
確率分布の変化の結果、粒子として発見されるAとBの位置が変化すること、
すなわち「移動」によって、力が働いたことを間接的に理解する。
つまり、こうだ。
私たちには直接的には知覚できない真空の裏舞台で、
全ての存在は波として様々な方法で影響し合っている。
私たちにとって、その裏舞台は、間接的にしか計算できない、
可能性の世界、確率の世界である。
本当は、真空の内部では、気が遠くなるような複雑な波模様が
休むことなく光の速さで往来しているのであるが、
それはプランクスケールの内側の仕組みであり、
私たちには原理的に直接的な確認をすることはできない。
幽霊のように可能性として宇宙を満たす確率の波を、
私たちは「観る」ことはできない。
だから、その波の漂う場を、私たちは「真空」と呼んでいる。
しかし、原理的に私たちが直接到達し得ない、その真空の内側では、
実に多彩で複雑なことが起きているのであろう。
宇宙の真の姿は、光速で絡み合い、うなり、もつれ合う、
波紋の世界なのだ。
真空は、決して「何もない」「カラッポな」場ではない。
単に【私たち】には直接到達できない世界であるだけで、
実はその内容には、豊穣で複雑な可能性が無限に埋まっているのである。
粒子の対生成や、粒子の質量獲得のプロセスを見ても分かる通り、
真空には色々なものが埋まっている。………いや、
『真空には、あらゆるものが埋まっている』と言った方が
より真実に近いだろう。
【私たち】は、【私たち】のやり方で、見える範囲のものを、
観ているに過ぎない。
高い波が縺(もつ)れ合った領域を、粒子なり物質なりとして
知覚しているに過ぎない。
あたかも氷山の一角が存在の全てであるかのように。
しかし、全ての真実は真空の内側に埋まっている。
そして、物質間に力が働き、移動という現象(動き、速度、時間)を生じさせる。
これこそ、真空が持っている性質である。
真空は、カラッポの場ではない。真空の性質そのものが、
「物質」と「力」の絡み合う、この世のありようの全てを物語っている。
『雄弁な真空』………間接的にではあるが、
私たちは、真空の内側に埋まっている無限の可能性の音を聴くことができる。
- ここで、もう一度、立ち止まって考えてみよう。
「真空の内側と外側を分けているものは、一体、何なのだろうか?」
(氷山の見える部分と見えない部分を分けている水面の正体は何か?)
それがプランク長だ、というのであれば、その基となっている
シュヴァルツシルト半径とコンプトン波長を決めているのは何なのだ?
質点からの距離と時空の曲率や、粒子の波としての存在範囲は、
どのようにして決まっているのか?
「質点」という概念を決めているのは何なのだ?
「存在」という情報の受け手は何なのか?
「時空」という形式で宇宙を眺めているのは誰なのだ?
その究極の理由は、【私たち】以外には有り得ない。
無限乱雑空間から、宇宙をいまあるがごとくある姿に切り取り、
それ以外の部分を真空の内側に詰め込んで見えなくしている真犯人は、
まさに【私たち】自身なのである。
- 量子力学における不確定性原理は、その一つの観点として、
位置と運動量を同時に精密に決定することは原理的にできない、
ということ意味している。
実はこれも、【私たち】が、氷山の一角しか見ないことで、
【私たち】の安定した宇宙を切り出していることと関係している。
水素原子の周囲を回る電子の軌道は、不確定性原理があるために、
ある一定以上狭い領域に押し込めることができない。
押し込めようとすると、運動量の不確定性が増して、
その軌道から飛び出してしまうのだ。
もし、電子の軌道を幾らでも引き絞ることができたら、
原子は今ある大きさを維持できずに、10万分の一の原子核の大きさにまで
ぺしゃんこに潰れてしまう。
そもそも、「原子が、今あるがごとくある大きさの原子として存在している」
ということの理由は、不確定性原理にあるのであり、
そして、その究極の理由は、やはり【私たち】にあるのである。
(【私たち】が、そのように位置と運動量を観ているのである。)
原子の大きさが決まるからこそ、
分子、細胞、身体、星、銀河、宇宙の大きさも決まる。
つまり「この宇宙が、今あるがごとくある姿の宇宙である」理由は、
【私たち】にあるのである。
もし、空間が無限に滑らかで、どんなに小さなスケールでも定義可能なのだとしたら、
大きさというものには何の根拠も無くなってしまう。
「ある大きさを、今あるがごとくある大きさとして測定している」のは【私たち】であり、
大きさは、測定している側の【私たち】のやり方、【私たち】の空間把握の方法に依存する。
不確定原理とは、私たちが無限乱雑空間からこの宇宙を切り取る時に、
それ以上細かいスケールは切り取らないことで、
今あるがごとくある大きさに根拠を与えているという事実の別表現なのだ。
- 以上は、強い人間原理宇宙論(strong anthropic principle in cosmology)
として知られる考え方と重なる。
内部に生命を宿さない宇宙は、誰からも観測されないのだから、
存在しているとはいえない。従って、存在しているといえる宇宙は、
生命を宿すような性質や構造を必然的に持つ、という考えだ。
一方、自循論では、その必然性や根拠を、
「生命」とか「人間」に置くのではなく、
「自」という現象に求めているところに特徴がある。
知的生命、つまり脳神経回路のような高度な情報処理プロセスの中に
「自のクオリア」を発生させ、
時間と空間という形式で知覚を行う(=無限乱雑空間から宇宙を切り取る)存在、
それこそが宇宙と物理法則のありようを決めているのである。
(なお、私は、「知性」を、「自のクオリアを持つこと」と同義であると考えている。)
さて、このような知的存在一般、広義の言語を共有できる存在の総体を、
ここまでの文章では【私たち】とカッコ付きで表記してきた。
とっくに生命体を捨てて、恒星間コンピューターの中で文明を築いている
知的存在と、地球上にいる人類が、
何らかの言語でコミュニケーションできるようになったとしたら、
その連盟全体が新たな【私たち】となるであろう。
いずれにせよ、ある物理宇宙は、その宇宙の内部にある、
全ての知的存在(=【私たち】)と、相互依存関係にあるのだ。
- もし真実が無限次元無限大のランダムな媒質(無限乱雑空間)ならば、
そこから【私たち】を含む自己無矛盾で有限な、
「3次元空間+1次元時間」という形式のささやかな物理宇宙を切り取れる、
ということは、驚くには当たらないだろう。
【私たち】は、【私たち】という自覚を維持するのに
必要十分なだけの物理基盤としてのちっぽけな宇宙を、
無限の中から自己責任で切り取って、内側から「観る」ことで支えているのだ。
結局のところ、私たちにとっての神を敢えて定義するならば、
それは【私たち】自身なのである。
ただ、ここで言う「神」とは、意味論的に最も根源的なもの、
という意味であり、全知全能の神という意味ではない。
【私たち】は、物理宇宙の法則を、外側から勝手気ままに書き換えられる訳ではない。
【私たち】は、自由意志を持って、未来を選択していくことができる。
(そもそも、そのような形式を獲得するために、空間と時間という形式をもって、
無限乱雑空間の大半を捨て去って、ささやかな宇宙を切り取ったのである。)
しかし、もし、自由意志によって、物理法則を大きく書き換えてしまったら、
【私たち】を構成する原子や細胞や身体や脳神経回路が、
今あるがごとくあることと矛盾してしまうだろう。
このような、物理宇宙と【私たち】の
(奇跡的な)相互依存関係を壊すような裁量までは、【私たち】には与えられていない。
- 【私たち】が将来発見するであろう究極の物理法則は、
それに従って宇宙創成当初に6つの素粒子と4つの力が整い、以降、
原子が構成され、星が生まれ、生命を育み、
知性を持った【私たち】を生み出せる法則でなければならない。
そうでないならば、その物理法則は、こうして【私たち】が存在する以上、
間違いなく間違っている。
逆の言い方をすれば、今あるがごとくある【私たち】と、
私たちが観測したり認識したりできることの全てを説明できる物理法則でさえあれば、
たとえそれが何十種類提案されたとしても、それらは全て正しいのであり、
それ以上、真偽を判定する基準などは無いのである。
(敢えて言えば、それら全ての物理法則のうち、もっともシンプルなものが
「良い物理法則」として採用されるであろう。)
- ところで、人類が生まれる前から宇宙も物理法則も存在していた。
つまり、時間的因果関係で言えば、【私たち】よりも物理法則の方が先にある。
一方、その物理法則の根源的な理由は【私たち】以外に求められないのであり、
意味論的因果関係で言えば、物理法則よりも【私たち】の方が先にある。
そもそも、「時間」という形式すらも、【私たち】の核にある
「自」もしくは「自のクオリア」が要請する形式なのである。
時間は、【私たち】という現象の総体が、自覚や自由意志を獲得するために、
自らに課した制限なのである。
(物理法則に従い、自己無矛盾である限り、「自覚」すなわち「意識」は、
全ての可能性の中から、どれを現実として選択しても構わない。
【私たち】は、常に、より大きな可能性から、現実を切り取る機能を持つ。
これこそが、「自由意志」を生み出した錬金術のカラクリである。
いやむしろ、このような自由度を自らに持たせ得るような特殊な場として、
【私たち】は、無味乾燥な無限乱雑空間から、「時間」や「物質」や「力」のある、
この宇宙を切り出したのである。)
【私たち】は自由意志を持つ。しかし、その自由意志の基盤となっている
この物理宇宙のあり方に違反するような自由まで与えられているわけではない。
タイムマシンで時間を遡って過去を書き換えるようなことは、
自由意志を獲得するために自らに課した時間という制約の否定であり、
物理宇宙と【私たち】の(奇跡的な)相互依存関係を壊し、
自己矛盾を引き起こすことであり、
つまり、自らの自覚や自由意志を否定することと同値である。
裸体で空を飛んだり、小指でトラックを持ち上げる、といったことも同様に、
自らを否定することになってしまう。
しかし、「今から食事に行こう」とか「英語の勉強をしよう」とか
「新しい事業を起こそう」といった、この宇宙のあり方に違反しないような選択は、
常に可能である。(そういった「選択」ができるような、
非決定論的なやわらかい場(物理世界と情報世界が相互依存するような場)を、
【私たち】は自ら切り出してきたのだ。)
- 決定論的世界観では、時間的因果関係と意味論的因果関係は
同じことの両面であり、この2つを区別する意味がない。
あなたの一生は、単に、一端は受精卵で、もう一端が遺体である、
「どこを切ってもあなたである金太郎飴」として凍結された、
一つの彫像として横たわっているだけである。
しかし、時間という形式を自らに課し、自覚と自由意志を持った
【私たち】の世界の見え方においては、
金太郎飴は時間に沿って分解され、アニメーションのように動き出す。
このような世界においては、
時間的因果関係と意味論的因果関係を、分けて考える必要がある。
意味論的には、時間的に先立つものが常に第一原因であるのではない。
意味論的な第一原因は、自覚という現象、すなわち「今ここ」であり、
選び取る未来や、想起する過去は、その派生物に過ぎなくなる。
意味論的に考えるならば、
最も根源的な原理は、時間的な過去にあるのではない。
「今ここ」すなわち【私たち】にあるのだ。
- 【私たち】は、自己責任において、無限乱雑空間から、
物質と力で構成される、この物理宇宙を切り出した。
その中には勿論、【私たち】自身が含まれている。
まるで、両手に持った縄跳びを足の裏に通して、
腕力だけで自らを宙に浮かべているかのように、
【私たち】は、この宇宙と意味世界を、自ら支えているのである。
その結果として、【私たち】は、自覚と自由意志を勝ち得たのだ。
|
視点の無償性
|
|
なぜ、どうやって、「可能性」は「現実」に崩壊するのか。
|
◎脳の機能から見た「意識」
脳の機能から見ると、意識は、
『脳内で外界と自己モデルを調和させるプロセスの連鎖によって生じる現象』
であると考えられる。脳内を駆け巡る電流が演算を行うと同時に、
その演算回路自身が短期記憶の仕組みで強化・変更され、
一瞬前の演算の結果(自己モデル)をも内容する各種の情報を集め、
容量に限りのある神経回路網によって有限時間内に調和が図られる。
質感や決定の意志も、想像を絶する複雑さの神経回路網の中で行われており、
「意識」は、これを時間的・空間的に整理された形式で組み立てる際に
立ち現われる現象であり、自己参照性というスクリーンに映し出された
映画のようなものである。「意識」は、脳を含む生命活動全体の驚愕的に
複雑なシステムの僅かな断片であり、その限定性・制限性によって、
適切な時間内で複雑な情報の本質を捉え、迅速な調和(決断)が図れるようになる。
◎量子脳理論的な考え方
「意識」は、機械論的なシステムの上で、記憶回路と演算回路が重ね合わされた
自己参照性のあるアーキテクチャを持つところに、現象として立ち現われるもので、
それ以上の説明を追加する必要は無いと思われるが、ここではそのベースの上に
味付けとして、脳が更に量子力学的な効果も利用している可能性を検討する。
【●量子力学における神秘的な過程・現実化(無から有の生成システム)】
※状態減らし、波束の崩壊、可能性から具体物、
買い物(お金という可能性から物という具体性への両替)………
「可能性」として計算されるものを、
「現実」として観測しようと思えば、そのように観測される。
それは、視点を切り替えていることに相当する。
可能性を崩壊させるプロセスは物理的な相互作用の中にあり、
だから人間のような知的生命が生まれる前から
可能性は崩壊し続けマクロな意味での宇宙を形成していた。
単に、生命の進化の過程で、脳の中にそのような相互作用を
実現する共鳴状態(コヒーレントな状態)を作り
可能性を崩壊させ具体的な状態を実現する器官を持つに至ったものが
進化の頂点にあるだけなのかも知れない。
※脳の中で可能性のコヒーレントな状態が作られ、これまでの脳の
諸機能と相互作用することで崩壊が起こり、それが
何らかの計算結果であり、脳の電気的信号の伝達のような原始的な
諸機能に影響を与えるのだとすれば、脳は現時点での決定論的な
機械仕掛け以上の何者かを内包していると言えるだろう。
それが「私」という感覚のうちの“任意性”(機械論的な操り人形では
無いと信じたい人の拠り所)の正体ということになる。
それも、全くランダムに崩壊させるのでなく、
記憶や脳内ネットワークの状態と密接に関係して、
生きて行くのに有利な結論を導いたりできるような
崩壊のさせ方が出来るやり方で。
※そうでなければ折角量子現象を脳が獲得しても、生存に有利にならない。
※観測効果と言われるものの根源もここまで遡るかも知れない。
脳の中の秘密の器官が宇宙の法則(もしくは直近の状況に影響する
境界条件)と裏取引をして、私たち自身も気付かない間に
“可能性の状態”から“物質的な状態”への視点変換の方法を
手に入れているかのようである。
※単独では因果的な可能性でしかないものを、
時空的・物質的には「統計的な」意味があるように
導いて“計算”する過程が脳内で起こっている。
もしこのような仕組みがあれば、量子コンピューターのように、
観測によって任意の崩壊現象が起きても、その結果は
何らかの有意味な計算結果として利用することができる。
単なる現象としてはランダムな崩壊過程に見えても、
フーリエ変換してみると周波数空間では信頼度の高い演算結果に
なっている、といったイメージ。
※一般的な解釈ではマクロな世界は収縮していることになっている。
観測者の有無に関わらず(人間の意識が生まれたときに宇宙は生まれた、
と考えるような人間原理的解釈は一般的ではないだろう)。
世界は原理的にいつでも状態の重ね合わせであるが、人間(生命)が
自由性を得るために自らに課した不自由である《時間》という原理で
観測・計算すると、過去から未来まで様々な具体物が浮かび上がる。
この世界像(宇宙)は“人間”が(もう少し控えめに言うと《時間》が)
勝手に作り上げたものである。
(1)「マクロな世界」は既に可能性が具体物に崩壊した後のように見える。
(2) しかしミクロとマクロの明確な線引きも無い。
(3) マクロの世界でも可能性のまま(状態の重ね合わせのまま)の部分は
幾らでも残っており、単に人間がマクロなものを収縮しきっている、
全て具体物である、と捉え、認識しているだけである。
※せいぜい、満天の星空から地球に届き観測できる宇宙の横顔くらいが
具体物で、その他の宇宙は人間にとって知り得ないもので
満たされている。
◎選択の任意性・可能性
※選択の余地は存在し、どれを選択するかという事には自由性がある。
※視点は自由に選択できる
一般連続体仮説が、数学の拠って立つ公理系からは、その命題も
命題の否定も無矛盾、つまり証明不可能であり、公理系から独立な問題である。
この宇宙にも、物理法則などの幾つかの公理はあるが、
その公理からは証明不可能な(決定不可能な)問題
または“可能性の状態”があり、それをどう決定するかは
自己無矛盾である限り任意性がある。
この「可能性の選択の自由性」と「可能性を消費して具体化するプロセス」に
「意識」の謎は潜んでいる。
宇宙は、“可能性の状態”も“具体化された物質”も、
宇宙の法則(公理)に従って整然と1クロノン毎に更新されるが、
“可能性の状態”を崩壊させて“具体化された物質”に両替するという過程も含まれている。
不思議な可能性の重ね合わせにあるものが、自己無矛盾性の範囲内で崩壊する。
情報食者・可能性食者たる知的生命体が任意に崩壊させたりする。
つまり、我々は本質的に可能性を食べて現実を排出する。
※“可能性の状態”は、その境界条件から、大域的に定まるものであり、
そのままにしておけば(敢えて観測済みというレッテルを貼らなければ)
1クロノン内に大した計算をする必要はないが、
実在の粒子に切り替えてしまうと、以降は具体物として計算される必要がある。
一定の大きさの空間が充足した閉鎖空間として計算されるには、
この2つの観点で満たしてやるのが具合が良い。
(より少ない計算量で充実した閉鎖空間が得られる。)
“任意性”は、知性とか主体性とか思考といったものの
根源的プロセスが進行できる前提であって、
何故選べるのか、何故選んでしまうのか、という疑問に行き着く。
※人間の脳の場合、電磁気系と量子系の相互作用によって
それは定まっているのかも知れない。
※すなわち、ニューロンの発火やネットワークによる記憶系が高度な
情報処理装置を組み上げたのに加えて、複数の可能性から一つを
選択する効率の良い手段として量子計算機能を追加した、という事。
※「ん~~~」と念じて考え込む時、脳の中の幾つかの量子の状態の
コヒーレンス(波としての干渉しやすさ)が高まり、自己無矛盾な
複数の解が重ね合わさったところでパチンと弾けて具体的な電子状態と
なり、これが電磁気系にフィードバックされ、あとは通常の
ニューラルネットワークを通して適切な感覚・映像・記憶が励起され、
外界刺激からの反応同様、内部刺激の結果として発話・行動などを行う。
→この『パチンと弾ける』部分が、古典的コンピューターのような
計算過程と異なる仕組みであり、人間と古典的コンピューターの
本質的な差、ということになる。
→しかし、量子コンピューターが人間臭い量子計算アルゴリズムを
身に纏って登場した暁には、チューリング・テストくらいは易々と
パスするようにも思われる。それでもなお量子コンピューターが
血と肉から出来ていない以上、それらの総体で構成される人間臭い
意識・精神、神がかった気高さなどは生まれない。別に、
コンピューターにそういうものを持たせたいとも思わないが。
自意識は他の生命や生命現象にも存在すると思われる。
しかし、人間の自意識が何故「特別か」と問われると、それは新たに
可能性を効率良く消費する手段を手にいれた点(=大きな自由性)にある。
いずれにせよ、意識は、ある制約の中に詰め込まれた情報処理の複雑性に
伴って現われるもので(随伴現象)、その濃度・密度の点で人間は量的な
差が質的な差に転換するほど特殊だということが出来る。
※この解釈は、生理学的なアプローチを重視する視点を選択する場合には、
意識とは副次的な(随伴的な)現象であり、この説明平面においては、
意識は主役というより生命現象や進化論における脇役である。
このような視点が存在する(説明の方法が成立する)こと自体は問題ない。
自意識をもっと特別なものと捉えたい人への説明にはならないかも知れないが。
|
情報世界と自由意志
|
|
物理世界と情報世界の相互依存関係こそが自由意志の源泉である。
|
- 情報世界の中にあって、私達が自由意志だと思っているものは、
一体どうやって、物理世界に影響を与えているのだろうか。
自分が右手を上げようと決意したら、何故、右手が上がるのだろうか。
霊が身体を操っているのだろうか。
脳の最奥にいるホムンクルスが電気信号を変調しているのだろうか。
そんなことは無い。
情報世界は、ただ、物理世界を照らすだけである。
情報世界の側から出来ることは、ただ、《視線》を選択することだけである。
情報的に自己無矛盾な限りにおいて、
プランク長以下の僅かな自由度の中で、
物理世界をどう眺めるかを選択することしか出来ない。
しかし、その一つの《方角》の遥か先には、何もしない自分があり、
それとは僅かに異なる《視線》の先には、
結果として右手を上げている自分がある。
いずれの経路も物理法則には完全に従っている。
私達の自由意志は、物理世界にちょっかいを出すことは出来ない。
ただ、その《眺め方》を、ほんの少し変えることが出来るのみである。
- 指先が何かに触れた瞬間に、そこで発生した電気信号が運ぶ《意味》は、
非常にシンプルで、そのまま「指先が何かに触れた」という意味であり、
物理世界と情報世界は素直に1対1に対応している。
しかし、手のひら全体で何かを触って、それらの電気信号が
神経線維の束を伝って一斉に脳に到達し、混ざり合い、フィードバックしつつ、
多様に加工されると、その一つ一つの電気信号を取り出しても
言葉で表現できないほど複雑な《意味》を帯びてくる。
(例えば敢えて言葉で表現すれば、一つの電気信号が、『手のひらの
ある部分とある部分に感じる圧力差とそれらの部分間の距離関係および
一瞬前と比較した時のそれらの変化量から合成されるベクトル量について、
それを表すための一群の成分の中の一つ』を意味するかも知れない。)
電気信号群は更に象捨され、統合され、最終的には
「硬い」とか「柔らかい」といった、非常に抽象的な《意味》に到達する。
そのたった一つの「硬い」という《意味》は、
脳内のニューロンの、時空的に散らばった多数の発火現象に対応しており、
「いったい脳のどこが『硬い』と感じたのか」と問うても、
その時空パターンを明確に指し示すことは容易ではない。
茂木健一郎氏の言う「相互作用同時性の原理」が厳密なものかどうかは別として、
ともかく、情報空間上の、たった一つの同時的・一箇所的な《意味》は、
物理的な存在である脳内の、時間的にも空間的にも複雑に散らばった
夥しい電気信号の群れに対応することになる。
そして、情報世界の中でも絶対的な特異点を為す「自」という
非常に抽象的な「いま・ここ」に対応するたった一つの《意味》は、
物理的には脳全体に散らばってしまっており、常にうなりを発し、
混ざり、持続する、雲のような境界の曖昧なものであろう。
物理世界にある脳内の、どのような電気信号のパターンが
情報世界にある「自」という《意味》に対応しているのかを
明確に示すことは事実上不可能であるように思われる。
それでも、この、殆どランダムであるが如く脳内に広がっている
電気信号の雲のパターンの継続が、
情報世界における「自」という固有の現象を
支え続けている、ということは間違いない。
だから、いかに物理世界内の出来事と
情報世界内の意味シンボルの対応が複雑でも、
原理的に対応が取れる以上は、
情報世界の法則は全て物理世界の法則に還元できるのであり、
情報世界を物理世界と対等なものにまで格上げするという論理は
ナンセンスではないか、という意見もあると思う。
これに対する最も端的な反論は、
「情報世界から観測されない物理世界は
いかなる意味でも存在しているとは言えない」
というものである。
また、物理世界それ単体では、
自意識や時間の起源に対する説明ができない。
物理世界と情報世界(もしくは客観世界と主観世界)は、
それがワンセットとなって初めて存在し、意味を持つ
相互依存関係にある。
また、この相互依存構造から、
相対性理論(光速度不変原理)や
量子力学(不確定性原理)にも、
情報世界の核にある自己参照構造を根拠として
簡潔な説明を与えることが出来る。
そして、ここでは更に、「主体性」とは何なのか、
という問題についても検討を試みたい。
私が私の意識によって主体的に物理世界に関わっている、
つまり私は自由意志を持っている、というこの感覚は、
健常者なら覚醒時に常に感じていることであるのだが、
物理世界それ単体ではこの現象の説明をすることが出来ない。
物理世界しか無かったら、
全ては物理法則に従って淡々と流れ去る諸現象に過ぎない。
主体性などというものが発生する余地はなく、
私たちの意識は物理法則の奴隷であり、
この自由意志という感覚も錯覚に過ぎない、
ということになってしまう。
しかし、この感覚を「錯覚」と断じてしまうならば、
「錯覚でないもの」とは一体何なのだろうか…?
さて、私たちは、念力で物理世界の法則を捻じ曲げることは出来ない。
一方で、物理世界を見る角度を変えることが出来るとしたらどうだろう。
大変重要な原理なのだが、情報世界での
「自分が自分を参照する」という循環構造の隙間と表裏一体に、
意識によって照らされる物理世界の側にも
不可知の隙間が論理的にどうしても発生してしまう。
実際、プランク時間内、プランク長内の出来事というのを、
私たちは知ることが出来ない。
これは、物理世界と情報世界の相互依存構造に由来する
極めて本質的な制限なのであるが、
ここに「全てが決定論にならない」、いわば
法則の「遊び」「余裕」「ふらつき」が根源的に存在することになる。
情報世界の側からは、この「遊び」の範囲内で、
物理世界を見る角度を変えることが出来るのだ。
その変化は、一つ一つの瞬間には
Zitterbewegungする素粒子の次の位置に影響するかしないかの
僅かなものに過ぎないかも知れない。
しかし、この「遊び」は、
1秒間に1044(一載)回程度も繰り返され、
もしも常に同じ方向に誤差が積み重なるとしたら
最大で108(一億)メートルのオーダーにも達する
「遊び」なのである。
(これは、質量のある素粒子が何の偶然かジグザグ運動せずに
真っ直ぐ光速度で飛び続ける現象に擬えられる。)
実際にこのような偏向がマクロに起こる確率はほぼゼロであろうが、
ミクロの世界では、物理法則に抵触しない範囲で、
これだけの「遊び」もしくは「選択の余地」がある、
ということを、先ずは押さえておきたい。
私たちの脳内の電気信号の雲についても、情報世界の側からの都合で
ほんの僅かであっても見え方を変えられる余地がある。
これは実際には「右手を上げよう」とか
「今日はラーメンを食べよう」といった
高度に言語的・意識的な判断に対応するのでなく、
情報処理が密集している脳内の至るところで
全く無意識的に、しかし常にザワザワと行われている選択や判断に
対応している。
情報世界における絶対的な核である「自」を中心に転回するように、
情報処理の過程で、物理世界の見え方が僅かながら変わる。
それが無意識層から湧き上がって、大きな転回の流れとなって
意識層に来た時に、
「私は自分自身で右手を上げようと判断したのだ」
という主体的な感覚としてハッキリと知覚されるのである。
単に物理法則に従って決定論的に流れ去る世界観では説明し得ない
この「自由意志」という感覚は、
無意識層において常に至るところで行われている、
「自」を核にするという情報世界の法則(もしくは都合)による
物理世界の見え方の変化によって齎されているのである。
「自」という《意味》が、常に情報世界で
絶対的な位置になければならない、という
情報世界の側の都合により、物理世界の見え方は
常に僅かに偏向し、転回し、変化する。
それは、0コンマ数秒もの長い長い時間をかけて、
物理法則に全く抵触しない範囲の変化を少しずつ積み重ね、
やっと脳内の電気信号の分布パターンの
僅かなゆらぎを発生させる程度のものであろう。
その結果が更に積もり、フィードバックされ、
私たちの行動は実際に変化する。
ゆらぎが無かった場合には座ったままであり、
ゆらぎが有った場合には立ち上がった姿勢になっている。
そのどちらの経路も、物理法則に完璧に従っている。
ところで、この情景は、量子力学における
多世界解釈(エヴァレット解釈)を想起させる。
ただ、多世界解釈では、全ての可能な世界を
物理的実在と捉えているため、
無数に分裂していく宇宙などという
奇妙なイメージを引き起こしてしまう。
物理世界と情報世界の相互依存という構造が
相互の妥協点を毎秒1044回程度探りながら、
ヨタヨタと、客観時間と主観時間が織り成す一本道を進んでいる、
という描像の方が、よほど自然なのではないか。
物理世界と情報世界は、なんとか、お互いを支えあっているのである。
何度でも言おう。
宇宙あっての心であるし、
心あっての宇宙なのである。
- 大雑把に言うと、私はユニバース(uni-verse)ではなく
マルチバース(multi-verse)宇宙論者である。
しかし、物理学は観測選択効果をなるべく排除しようと
理論と実験を組合せて確固たる客観世界を築こうとしているのに、
私が突然「物理世界全てが観測選択効果そのものだ」と
言い出しても、取り合って貰えないだろう。
しかし、物理世界という見方(view)も、
間違いなく私達人間自身の手によって築き上げたものであって、
それ以上のものでは決して有り得ない。
宇宙を深く知ることは、自分自身を深く知ることだ。
そして、この「自分自身」という現象そのものは、
物理世界とは別の、情報世界にある。
「たった一つの、この宇宙」(ユニバース)にしがみつくのでなく、
無限に存在する宇宙(マルチバース)の中で、
物理世界と情報世界が釣り合っている状態を
「世界」と名付ける、という戦略に合意してもらえれば、
科学と哲学と宗教は統一的な思考のフレームワークで扱うことが
出来るようになるのだ。
- 幻想のホムンクルス君
- 自循論のエッセンスである情報世界を、漫画的に表現してみよう。
登場するのは、脳内に住む認識主体である「ホムンクルス君」と、
彼が眺めている「意識のスクリーン」である。
誰もが脳内に持っている、このホームシアターが、情報世界の舞台だ。
ところで、このスクリーンに映っているのは、目が見ている景色ではない。
五感が捉えた全ての情報が、シンボルとして組み合わされて表示されているし、
過去の記憶も、その奥に重ね合わされ、透けて見えている。
そして、なんといっても一番の特徴は、「ホムンクルス君」自身も、
「意識のスクリーン」に鏡のように映し出されている、という点である。
従って、この「意識のスクリーン」には、直接的な感覚情報と、記憶と、
自分自身の姿が、渾然と混ぜ合わさったものが、
情報シンボルとして蠢きつつ表示されていることになる。
- さて、ホムンクルス君は、ただ漫然と、この「意識のスクリーン」を
眺めているだけではない。スクリーン自体に手を伸ばして触ったり、
映っている内容を直接改竄することは出来ないのだが、
ある場所を注目したり、見る角度を変えたりすることは出来るのだ。
勿論、それによって、次の瞬間、スクリーンに映る内容も変わってくる。
喉が渇いているという感覚情報をクローズアップする。
視界情報の右前方にあるコップに着目する。
水が飲みたいというホムンクルス君自身の姿も映し出され、
「そうだ自分は水が飲みたいのだ」ということが
フィードバックされ、強調される。
この数瞬間は、まだ情報が溶け合い強化し合っているだけのようだが、
既にここまでで極めて重大なことが起きている。
この後、何百億の細胞が同期して活動し、眼球を動かしてコップを見つめ、
腕を動かし、コップを手に取る、という、途方も無い大プロジェクトが始まるか、
それともコップのことは忘れてしまうか、この2つの未来の選択の萌芽が
ここにあるのである。コップを手に取る未来A、コップを手に取らない未来Bは、
現在の状況Pから発展する物理世界として、いずれも全く問題がない。
P→Aという変化も、P→Bという変化も、物理法則には全く抵触しない。
脳細胞を流れる電子パルスを見ても、手の筋肉細胞の仔細を見ても、
量子力学的な精密さで両者の時間発展を調査しても、
各々は全く機械的に、唯物論的に、運命論的に、それぞれ
A、Bという未来に自然と到達している。
何が起きたのだろう。そう、ホムンクルス君が、視線を変えただけなのだ。
Aの方を見たら、物理法則には全く抵触せず、Aに到達した、
ただそれだけのことだ。
見方を変えると、私達にとっては、物理法則に全く抵触しない
無数の未来のバリエーションがあって、
どの路線に乗り換えるのかは、ホムンクルス君の自由である、ということになる。
(この「どこかの路線に乗り換える」ということを、敢えて
物理世界の枠組みで考えようとすると、量子力学における
確率波の崩壊とか、エヴァレットの多世界解釈のような表現になる。)
- このホームシアターは、唯一絶対の宇宙の中を、ただ突き進んでいるのではない。
視点を変更しながら、物理法則だけに任せていたら無数に有り得る未来のうち、
たった一つの経路の上を選んで進んでいるのだ。
各プランク時間で許される選択の幅は、プランク長くらいしか無いとしても、
一年後には0.5光年(4.7兆キロメートル)分くらいの差を生み出せるほどの
潜在的可能性がある。(実際には、いかなる物理法則にも抵触せずに
取り得る未来のヴァリエーションにはもっと制限があるが、
一つの決意が人を大富豪にしたり
ノーベル賞を受賞させたりする程度の選択の幅は、余裕で存在するだろう。
盲目な日々の努力より、明確な目標の方が重要であると言われる所以である。)
- この事情を、高次元から眺め直してみよう。
「ただそこにある円錐」を、
「だんだん大きくなる円」と勝手に解釈できるように、
私達は、10ないし11次元の「ただそこにある世界」から、
「1次元時間軸に沿って3次元空間を眺める」という認識の方法を
自分勝手に採用している。
捨てられてしまった6ないし7の余剰次元は、
空間の最小分解能以下に折り畳まれたカラビ=ヤウ空間として、
四次元時空の時間発展に殆ど影響を与えない膨大な未来のヴァリエーションを
内包している。
私達は、自分の時空認識を自分勝手に狭めておいて、
残りの部分は自分自身でも気付けない余剰次元に押し込めておいて、
その余剰次元のヴァリエーションから好きな未来を選び取っている。
自らの認識を制限したからこそ、自由の余地が生まれるのだ。
全知全能の神に自由は無い。全てが分かってしまうことと、
選択の余地がない、ということは、イコールだからだ。
(あらゆることが必然の結果であり、完璧に予測できる、
という状況では、自由は存在し得ない。)
- さて、その「認識」の舞台である、ホームシアターに話を戻す。
ホムンクルス君が出来ることは、わずかに視点を変えたり、
どこに着目するかを選択することだけだった。その結果、
自分が、コップを手に取っている未来Aと、そうでない未来Bの
どちらの経路に飛び込むかを決めている。
では、ホムンクルス君は、どうやってそのような選択を行っているのだろうか。
ホムンクルス君の脳内にも、やはり意識のスクリーンがあって、
ミニミニホムンクルス君がいるのだろうか。
………そうではない。
実は、このホームシアターには、隠れた仕掛けがもう一つある。
それは、意識のスクリーンとホムンクルス君の中間に存在する不動点、
その名も「自」である。
この「自」は、論理的、純粋数学的なシンボルで、
全ての情報世界を通して、たった一つしか無い。
つまり、あなたの脳内のホームシアターにある「自」も、
わたしの脳内のホームシアターにある「自」も、
その核は、全く同じものなのである。
(但し、どこまで純粋、明確な核として形成・維持されているかは、
処理されている情報流の大きさや密度に依る。
小さい子供や、健常者でも睡眠時には、この「自」はボヤけている。
同じ健常者でも、短期記憶量・情報処理量が優れている人は、
より明確な「自」を持っている。
この明確度を計測する単位が「セルフ」であり、
全く自意識を持たない状況が0セルフ、
外来情報に擾乱されず完全に不動な「自」を形成し切った状況が1セルフである。
その中間の値を定量化する方法は、まだ開発中であるが、
人間は0.5セルフ、犬や猫は0.01セルフくらいに位置づくのではないか。
植物も有限のセルフ値を持つとは思うが、ほぼ0セルフと言って良いだろう。)
- ここでいよいよ、ホムンクルス君の正体が明かされる。
実は、「意識のスクリーン」は、情報宇宙の法則の不動点(求心点)である
「自」と相互作用し、「自」を安定に維持するように調整される。
つまり、「意識のスクリーン」と「自」は、常に不協和音を奏でつつ、
常にお互いが妥協して変化し、「自」は可能な限り「自」であり続け、
その反作用に相応しい「意識のスクリーン」の状態が選択されるのだ。
実は、この「意識のスクリーン」と「自」の葛藤の様子が、
次の瞬間の「意識のスクリーン」に残された傷跡こそが、
「意識のスクリーンに映ったホムンクルス君」なのである。
スクリーンに像が映っている以上は、オリジナルのホムンクルス君が
ホームシアターのどこかにいるはずだ、と考える。
しかし、本当は、ホムンクルス君など、いないのである。
情報世界の中で、「自」の安定を保つ動き、すなわち自己保存のプロセスが、
意識のスクリーンの上に落とした像、影、歪み。
その原因として逆算・捏造されたものが、認識主体としてのホムンクルス君なのだ。
- 生命は、進化の果てに、高度な抽象化も可能な情報処理を内包できるようになった。
神経や脳が形成された最初の段階では、
「まだ誰にも見られていないスクリーン」があるだけだ。
しかし、そのスクリーンの中に、別格の抽象シンボル、
普遍的・論理的・純粋数学的なシンボルである「自」が登場すると、
状況は一変する。このような「自」を維持するには、
情報世界内での大掛かりな動的平衡が保たれている必要がある。
(このことは、意識を支える生命体が動的平衡を保っていることと相似である。)
どこからか弱々しく現れた「自」というシンボルは、
やがて洗練・強化されて、動的平衡の中で一定の位置を主張するようになる。
(むしろ「自」が維持されている状態を「動的平衡」と呼ぶのであるが。)
「自」は情報宇宙の法則下では不動点である。エネルギー準位の最も低いシンボルだ、
と言っても良い。最も公理に近く、抽象的で、普遍的だ、といっても良い。
(純粋数学でトポロジーが境界概念を抽象化した開集合から出発するのと似ている。)
下等動物では、ただ環境に流されるままだった情報流は、
「自」の維持、という新しい情報処理システムに進化することになる。
このように「自」というシンボルは特別扱いされるので、
それ以外の感覚から到来したシンボルや、記憶から到来したシンボルは、
「意識のスクリーン」に残り、「自」だけがその外側にあるように位置づけられ、
「意識のスクリーン」と「自」の相互作用が
再び「意識のスクリーン」に残した傷跡から逆算して、
「ホムンクルス君」の存在が浮かび上がってきたわけである。
このことを以って、「ホムンクルス君は、本当はいないのだ」とか
「自意識とは錯覚なのだ」と考える人がいるが、
そういうことを言う人は、「そもそも、いる/いない、とは、どういうことか」
「錯覚でない、正常な感覚とは、一体何なのか」ということを、
もう少し突っ込んで考えた方が良い。
多分、物理法則で完全に説明されるものだけが真実である、
というような思い込みが意識の根底にあるのだろう。
意味世界そのものが、物理世界と情報世界の妥協の産物であり、
存在とか意識とかは、そもそも物理世界に還元されるものではない。
むしろ、「物理法則だけで完全に説明できる現象」の方が、
ずっとずっと限られているのである。
(そして、物理法則自体も、認識する側の性質の裏返しである、
ということを忘れてはならない。私達が知っている物理法則の全ては、
徹頭徹尾、私達が直接的または間接的に知覚したものだけから成り立っているに過ぎない。)
- 時間の由来は、「ホムンクルス君」と「意識のスクリーン」の間の距離である。
「ホムンクルス君」が座っている位置が、体感的な「今、ここ」であり、
「意識のスクリーン」に映っている、あらゆることは過去である。
つまり、抽象的な情報処理活動が高次化し、ついに「自」というシンボルを
発見・維持できるようになることで、
ホムンクルス君の居場所としての「現在」というポジションまで創造し、
過去→現在、という時間の方向性を獲得するに至るのである。
(ホムンクルス君は二次的な幻想なので、厳密に言えば、時間の由来は
「自」と「意識スクリーン」の間の距離である。この離散二時刻しか持たない
シンプルな時間概念を原型時間と言う。)
こうして、その場その場の情報に機械的に反応していただけの動物は、
「自」を中核とした判断や選択を行える知的生命に進化する。
このことは、更に延長され、過去→現在→未来、という時間軸を生み出し、
予め計画することで、より効率的に「自」の安定を図れるようになるのだ。
(情報世界の中で「自」の安定を図る、ということが、そのまま
生命としての自分の安全を確保する、ということに対応している、
ということは極めて重要だ。情報世界内の自我境界線は、
物理世界の身体の表面と対応しているべきだ。
そうでなければ、折角、情報世界でのシミュレーションで「自」の安定化を図っても、
生命としての自分は死んでしまい得る。
「自」というシンボルは、「他との境界」無くして成立しないが、
「自」を獲得するに至るまでに、この境界概念を強化し続けていたのは、
他ならぬ身体性である。
生命の進化には無駄が無い。
自己認識・自意識もまた、自己保存に有利だからこそ採用されている。)
- ホームシアターが、どの枝も物理的には全く平等な、無数の未来のうちの
どれに乗っかるかを決める「場」であり、
その自由は、余剰次元に隠れていた「遊び」を、一つに決め付けること
(確率波を崩壊させて、一つの古典状態にしてしまうこと)として
観測されるとしたら、
これは乱雑さを構成するタネを増やしているようなものだから、
熱力学第二法則とも相関するだろう。
「時間の矢」の問題を、熱力学第二法則に帰着させる考え方もあるが、
それは半分だけ正解、ということになるだろう。
いずれにせよ、時間は、自意識が生み出したものなのである。
- 真実の世界は、限りなく乱雑で、無限である。
ここに、何らかの理由で「自」なるものが発生すると、
法則と有限性が生まれる。
その制約と引き換えに、「自」は「自由」を獲得できたことになる。
これこそが、無限乱雑空間から、意味のある宇宙が勝ち取られる道筋でもある。
ビッグバンが本当に起こった、というよりも、
私達の意識から見たら、宇宙の時間的端点として
ビッグバンがあったように見えざるを得ない、といった方が真実に近い。
誰の頭の中にもある「ホームシアター」にある、
「自」なる隠れた核こそが、無から私達の自意識と、そして
この宇宙全体を生み出したのだ、ということが分かった。
「私が私である」というこの不可思議な感覚と、
「宇宙が宇宙としてある」というこの神様がくれたような奇跡は、
全く根が同じなのだ。(アートマンとブラフマンを同一視する
梵我一如の思想ともフィットすると思う。)
自分で自分を見ようとすると、どうしても盲点のような
特異点が生じてしまう。その「自」という、
掴めそうで掴めない、全ての意味の根源を、
私達は「神」と呼ぶのであろう。
- 以上で、科学、宗教、哲学が、自循論の枠組みで統合される
グランドデザインも示せたと思う。
- セルフ
- 単位[セルフ]の定義、こんなのでどうだろう。「神経的自己(主に脳)が、
内面で発生した概念的情報処理に費やしているエネルギーの割合」。
無機物や、内部にフィードバックループを全く持たない生物は、0セルフ。
自己内部で永遠に情報を発生させ、それを処理し続けている生物は、1.0セルフ。
多分、人間は、0.8セルフくらいじゃないだろうか。
入出力に煩わされている割合が、平均して20%くらいはあるだろう、という想定。
うーん、今までの定義の中で、一番しっくり来るわ。
- あるシステムが、その入力情報(知覚)の全て、記憶(概念)の全てを使い、
計算能力の許す限りで「それら、あらゆる対象よりも内側にあるもの」を
推定しようとすれば、
そのシステムの演算量(速度・密度)の限界において、
それ以上の内側を推定できない、ギリギリの自己核(いま・ここ)に、
そのシステムなりに行き着くであろう。
どのような知的システムも、その知的システムなりに、
自己核の輪郭を維持しようとするし、
その目指す先は完全に同一でろう。
しかし、演算量(速度・密度)が高いシステムであるほど、
「それよりも内側、あれよりも内側…」と考える対象は多数であろうし、
従って自己核の輪郭も高精度で明瞭になるだろう。
多分、猫にも、ぼんやりした自己核がある。
人間は、その複雑な脳で、かなりハッキリした自己核を維持していると考えられる。
将来、珪素ベースの高密度な脳が設計・開発され、人間よりもずっと明瞭・明晰な
自己核を持てるようになるかも知れない。
神経的自己のうち、自己を維持するために使われる計算資源の割合の対数値を
単位[セルフ]と考えた時、これはおよそ、自己核の明瞭さに比例すると思われる。
いずれにせよ、私は、単位[セルフ]を策定することで、人間の自意識のレベルを
相対化し、無邪気な人間至上主義を解体したいのだ。
- 自のクオリアと自由意志
- 「私が私である、という、このリアルな意識体験」は、
どのように説明し尽くされるのだろうか。
その基底にあるのは、「自のクオリア」である。
これは、私が私のことを考え続けるだけの連鎖であり、
物理的には、脳神経回路網が、脳神経回路網のことだけを
情報処理している状況であり、無色透明の、まさしく「自循」そのものである。
おそらく、この、「カラッポの体験」こそが、
ベルクソンの純粋持続の指し示す事象であろう。
ここに、視覚や触覚などの情報が流入して、情報処理過程に生じる変調が、
「赤のクオリア」とか「痛いというクオリア」などになる。
では、私たちの意識は、この、質感の体験としての受動クオリアとして
説明し尽くされるものであろうか。
そうではない。このリアルな意識体験の、もう一つの特徴は、
「私こそが、私のありようを決めている」という能動性、つまり
自由意志や判断力にある。
「私は人間だ!」と叫ぶ時、その内訳は、
リアルな意識体験を持ち、かつ、自分の判断で未来を選択している、
という実感を伴っている、ということになろう。
- まず、無色透明な「自のクオリア」がある。
ここに、感覚器官経由の外来情報が入り込み、
「受動クオリア」「感覚クオリア」が生じる。
一方、外来的な入力信号に依存せず、自分自身の思考のフィードバックの結果か、
もしくは無意識層からのヒラメキのような内製情報が入り込んで、
「能動クオリア」「意志クオリア」が生じる。
この両方が揃ってこそ、私たちの自意識は、リアルな意識体験となるのだ。
- さて、この「意志クオリア」の内訳を、更に詳しく見てみよう。
すると、「自分の意志で未来を選択している」と言えるためには、それが
「内製的」であり、かつ「下層従属ではない」という事が条件となるだろう。
私たちの脳内で発生する「意志クオリア」は、
外部からの信号の直接の反応でもないし、なおかつ、
化学反応や電気信号に完全に従属しているわけでもない、
と信じられなければ、私たちは「意志クオリア」を「意志」と呼ぶのを躊躇(ためら)うだろう。
- それでは、私たちの自由意志は、本当に下層従属では無いのだろうか。
私たちは、決定論に従い、機械的な化学反応や電気信号の組み合わせに過ぎない、
と言い切ってしまえないのは、どうしてなのか。
実際、科学の成果を十分に尊重し、丹念に検討を重ねていけば、
“原理的には”私たちは単なる決定論的機械だという結論になりそうにも思われる。
自由意志や能動性を擁護する積極的な理由は、どこにも無いように思われる。
しかし、本当にそうだろうか?
私たちの「この能動的思考」は、本当に、化学的に説明可能な
分子運動以上の何者でも無いのだろうか?
- 現実に目を向けよう。私たちの脳内で機能している、
膨大な分子の作動の様子に比べると、
私たちの知的活動は、あまりに高次元で、あまりに曖昧だ。
“原理的には”私たちの意識は化学反応の集積に過ぎない、と主張しても、
この知性を、 単なる化学反応に結び付けて、直接的に説明しきる事など、
現実的には到底できそうにない。
“原理的には”そうだ、と、幾ら言われても、
“実践的には”私たちの自由意志は、
物理法則や化学反応の奴隷には、実感として、どうも成り得ないように思われる。
“実践的には”、唯物論者と決定論者が束になって、
【私たち】の思考を全て化学反応と電気信号で説明しきろうとするよりも速く、
【私たち】は悠々と思考空間を広げていくことが出来る。
知的思考としての科学的な説明は、【私たち】の知的思考の発展に追い付けない。
脳内の電気信号の分布は確定的に記録するには複雑過ぎるし、
その結果として実現する脳内の思考空間は、曖昧で複雑で、かつ広大過ぎる。
その間に、直接的な1対1対応があることが“原理的には”可能だと言われても、
“実践的には”それを示すのは不可能だ。
だからこそ、私たちは、真に自由であり続けられるのだ。
- 「下層従属でないこと」を、もう少し詳しく見てみよう。
より低レベルの現象が、多数連動して、あらたな 意味レベルの挙動を形成する時、
各々のレベルが「相」を成す、と呼ぶことにしよう。
「相」の条件は、時間の流れの中で安定していること、そして、
その内容が、下位レベルの相の挙動で説明し尽くせないことであるとする。
(説明され 尽くすなら、それを“新たな”相、と呼ぶ意味が無い。)
おそらく、素粒子→原子→分子→生命細胞→神経的自己→知性
という階層は、それぞれ「相」を成しているだろう。
“原理的には”下位レベルの相の挙動に完璧に従うのであろうが、
無常に時間が流れていく、このリアルな宇宙においては、
現実的な時間で下位から上位を説明し切ることは出来ない。
上位層の現実の方が、どんどん先に進んでしまうからである。
-
「新たな相」の、実践的な条件定義を試みよう。
- 各々の相には、互いに識別できる状態があること。
- 相は開かれており、状態数に制限が無いこと。
- 下位相の状態から上位相の状態を推定するための、
現物とは異なる、より高速な物理過程か、もしくは
計算アルゴリズムが“存在しないこと”。
最後の条件は、つまり、
「どうなるかは、実際にやってみて確かめるしかない」
ということである。この条件を満たすならば、
下位相が上位相を具体的に説明し尽くすことは
“実践的には”不可能である。
例えばもし、遺伝子配列から、生まれる赤ちゃんの肉体の全てを、
コンピューター内部で高速に計算できて、
これが「実際に母親の体内で子供を育ててみる」ことより
高速にできるならば、遺伝子に対して、新生児の肉体は、
新たな相とは言えない。十分な時間を掛ければ、
全ての肉体のパターンは、遺伝子によって、
説明し尽くされてしまうだろう。
しかも、これは、遠い将来には有り得そうな話である。
では、脳の神経回路網と化学反応・電気信号のパターンから、
実物の脳よりも高速な計算器か、別のアルゴリズムを用いることで、
現物の脳が考えるよりも速く、どんな思考や感情が生まれるかを、
推定することが出来るだろうか?
これが「永遠に不可能」とは断言できないし、証明することは難しい。
しかし、現時点では、見込みは全く無いし、おそらく不可能であろう。
人間が何を考えるかは、その人間と、その環境を、
丸ごとシミュレートするしかなく、それは結局のところ、
この宇宙そのものをシミュレートするということであり、
それは、この宇宙の内部においては当然不可能である。
-
「私という感覚」=
「自のクオリア」×
(「感覚クオリア」+「意志クオリア」)
という図式において、
「意志クオリア」は、内部から湧き上がるものであること(内製的であること)と、
それ自身で意味を為していること(下層従属でないこと、独自の相を成して、
自己完結していること)という条件で、実践的に成立しているであろうことを
見てきた。私が私である、という、この不思議な感覚の解明も、
一通り終わったし、この図式は、日常的な「私」の感覚に照らしても、
違和感の無いものであろう。
- 最後に、「意志クオリア」は、“実践的には”下層従属でなく、独自の相を成す、
と言えるが、“原理的には”やはり決定論、機械論が勝利するかも知れない、
という点に言及しておく。私は、“原理的にも”決定論、機械論は敗北すると考える。
新たな物理過程と優れたアルゴリズムで、上位相が下位相の挙動で
完全にエミュレートできるようになったとする。
知性→神経的自己→生命細胞→分子→原子→素粒子と、次々と単純なものに
挙動が還元されていくとする。しかし、そこに待ち構えているのは、
不確定性原理である。素粒子まで行き着くと、確定的なエミュレートはできない。
量子脳仮説のように、脳自身が微細管を用いた量子コンピューターだと主張しなくても、
そもそも、あらゆる物理現象には、不確定性原理の霊性が宿っている。
そもそも、この宇宙は、無限乱雑空間から、【私たち】が切り出した有限物であり、
プランクスケールの向こう側の無限小に隠れた霊性は、
【私たち】が切り捨てたものであり、【私たち】が【私たち】である限り、
永遠に確定できないのである。(確定できたら自己無矛盾性は維持できない。)
不確定性原理の話を脇に置いたとしても、素粒子レベルでの挙動から
【私たち】の知性までを再現するということは、知性体の相互作用と
環境条件を素粒子レベルから組み上げるということであり、結局のところ、
それは、宇宙内部で宇宙全部をエミュレートすることに他ならず、
それはこの宇宙自身以外の何物でも有り得ない。
結局、「宇宙がどうなるかは、実際に宇宙を走らせて確かめるしかない」 し、
「私が何を考えるかは、実際に私が生きて考えてみるしかない」のである。
- スケールとは何か
- 中学生の頃から、ずっと心の奥にあった疑問。「スケールとは何か。」
例えば、「どうして私は、私自身の身体を、斯く在るが如くの大きさで捉えているのか」
「どうして私は、時間の流れを、斯く流れるが如くの速さで感じているのか」
といった疑問である。なぜ、私は、私の大きさを、今の2倍でもなく、半分でもなく、
丁度今の大きさで感じているのか。
どうして、私にとっての時間の流れは、今の100倍でも100分の一でもなく、
丁度今の速さで感じているのか。
科学の本を読み、その答えは、プランクスケールと宇宙スケールの間にある生命性、
というあたりにあるのではないかと思った。
(10のマイナス35乗メートルから、10の26乗メートルの間の、私という1メートル。
10のマイナス44乗秒から、137億年の間の、私という100年。)
けれど、それは理由でも何でもない。その上限・下限は、なぜそのような大きさになっているのか、
という新たな疑問を生み出すだけだったし、
この体感的・直感的なスケール感の根拠とするには間接的過ぎた。
- つまり、問いの立て方が間違っていたのだ。
「《対象》の時間や空間が何故そのような大きさなのか」ではなく、
「《自分》は、何故、そのように時間や空間を感じているのか」という問い方をすべきだったのだ。
この表現の方が、私がスケールに対して感じている不思議さを適切に表している。
中性子が巨大な星のように見える知性体がいたとしても、
銀河を手の平で転がすような知性体がいたとしても、
それらはやはり、私たちと同じように、「私なりのスケール感で」対象を見るだろう。
それでは、結局のところ、《このスケール感》は、「自意識を包む身体と、対象の、相対性」であり、
自分の身体の大きさが、《このスケール感》の、絶対的な基準になるのであろうか。
確かに、子供の頃に見た公園の滑り台やブランコが、成長して大人になってから見ると
小さく感じられることがある。自分の身体が大きくなり、対象が相対的に縮んだのだ。
ところで、もし私が巨大ロボットの視点で暫く生活したらどうなるだろう。
世の中の全ては今までよりも小さく見えるだろう。
もし、銀河ほどの大きさの巨大アバターに精神を移植されたら、
太陽でさえ殆ど感知できない微小なものに感じるだろう。
しかし、このように次々と身体性のスケールを変更しても、
おそらく、私が視覚を捕らえる空間、つまり《意識のスクリーン》そのものの広さは、
変わらないであろう。
…「変わらないであろう」などと言ったが、実のところ、
私たちは、《意識のスクリーン》の広さを、どう表現したら良いのか、よく分からない。
スクリーン上に見えているものの大きさは、遠近によって様々に変わってしまうし、
それはそもそも《意識のスクリーン》全体の広さとは関係が無い。
また、映画館のスクリーンと違って、《意識のスクリーン》は、
周辺に行くほど境界が曖昧である。だから、「これくらいの広さ」ということを、
どう説明すれば良いのかも分からない。
にも関わらず、《意識のスクリーン》は、有限の広さを持っていることは間違いない。
目を閉じて複雑なネットワークを想像の中に思い描く時ですら、
それを視覚的に思い浮かべようとする限り、何らかの限界があることは明らかだ。
結論から言えば、《意識のスクリーン》の広さは、
同時と見做せる短い時間の幅の中で、並置できる情報量の上限として定義されるだろう。
ゼロ秒で計算は完了しないから、0コンマ数秒の短い時間内で位置関係を把握し、
短期記憶の中で並置できるだけ並置し切った広がりが、つまり、
《意識のスクリーン》の広さである。
私が同じ脳を持っている限り、身体が巨大ロボットになろうが、巨大アバターになろうが、
《意識のスクリーン》の広さに変わりはない。
しかし、人為的に脳に手を加え、演算速度を上げたり、短期記憶を増強することが出来たら、
私の《意識のスクリーン》の広さは、グンと広がるであろう。
- さて、私が抱き続けてきた「スケールとは何か」という疑問の答えは、
意識の持続性の中にあることが分かってきた。
私が「同時」と思える瞬間の中で、異なる要素を並置できる限り並置しきった、
その広がりが、私の《意識のスクリーン》の広さであり、空間認識能力の上限である。
普段、この能力は、その殆どが視覚に奪われており、
幾許かは聴力に使われているが、
静かな図書館で勉強に集中している時は、全く同じ機能が
抽象思考、つまり記号一般を扱う言語活動に振り向けられている。
ところで、《意味》とは、対象そのものに内包されているものではない。(意味は対象に自存しない。)
異なる対象を関連付け、その差異を認識する時に生じてくるものである。
つまり、《意味》とは、関係であり、差異である。
だから、異なるものを「同時に」広く並置できる能力というのは、
それだけ複雑な意味の構造を一挙に把握できる能力がある、ということである。
この事情は、視覚の場合にも勿論当てはまる。
視界はただの一枚の写真ではない。私たちは、そこに、人物や表情、
背景や明るさなど、色々な要素を認識して並置し、
それらの間の関係を意味として認識し、「情景」として一挙に把握しているのである。
それでは、私たちが「同時」と思う時間幅とは、一体何なのだろうか。
(※マクタガードは、三人称的な線形時間軸をB系列、一人称的な現在・過去・未来の
構造をA系列と呼んだが、このA系列の「現在」の幅が問題になる。
ベルクソンの純粋持続、大森荘厳の点時刻否定とも関連するだろう。)
- 空間的広がりは、「同時」に並置され、一挙に把握される限りにおいて意味を持つ。
しかし、0秒では、異なる要素を関連付けたり、並置して一挙に把握したりはできないから、
空間的広がりを体感するには、最低限の時間的な幅が必要である。
(※これは、脳の中での演算という意味でもそうだし、
物理時空においても情報伝達速度上限(光速度)一定の法則がある以上、同じことである。)
では、この時間幅とは何か。
人間の脳の演算速度は無限じゃないから、二つの時刻間の差が小さくなると、
それらは見分けが付かなくなり、「同時」と判断される、というのが
一般的な回答だろう。
しかし、忘れてはならないのは、問いの立て方である。今は、
「《自分》は、何故、そのように時間や空間を感じているのか」という問いに答えねばならない。
だから、《自分》にとっての「同時」とは何か、というのが、今の論点である。
- 《自分》とは何か。それは、脳が、あらゆる《対象》では“無い”ものとして、
全力で推定し続けている、内容空疎な仮想点である。
《対象》は、もちろん自分の外側にあり、そして、情報伝達速度の上限が一定である以上、
《対象》は、必然的に過去にある。
あらゆる《対象》で“無い”ものを推定し続ける思考は、だから、必然的に
あらゆる《対象》よりも内側にあって、《対象》よりも未来にあるものを推定する。
それらの推定が結び付けられ、重なり合い、共鳴し、強化され、ついに
ある一点に集まり、固定化される。その焦点こそが、抽象的な概念としての《自分》である。
あらゆる《対象》よりも考えうる限り内側にあり、
あらゆる《対象》よりも可能な限り未来にある一点。
それこそが「いま・ここ」にある《自分》なのだ。
この《自分》のことを、自aと定義しよう。
このようにして推定された自aもまた、内容空疎な仮想点とはいえ、
新たに創出された抽象概念である以上、その影が短期記憶に落ちてゆく。
次の瞬間には、この影は思考の《対象》の一つに組み入れられている。
「いま」から「過去」に滑り落ちた自aの影を、ここでは自bと定義しよう。
次のサイクルでは、この自bよりも内側で、自bよりも未来にあるものとして、
自aは推定されねばならなくなる。
このように、自aは、限りなく内側へ内側へと押し込められ、
限りなく未来へ未来へと押し出されていく。
この、自bと自aの一連の自己触媒反応のことを《意識》と考えよう。
私たちは、普段、自aを意識することは出来ない。
「自分とは何か」という問いに対して、「これだ、捕まえた!」と思ったものは、
思考の対象なので、それは既に過去にある自bだ。
自aは、その時点で既にそれより内側にあり、既にもっと未来にある、何者かである。
私たちは、意識して自aに追いつくことは出来ない。
それは、どの瞬間にも、既に、脳が全力で行っていることであり、
その運動こそが自意識(自分が自分であるという感じ、すなわち自のクオリア)の
根源なのであるから。つまり、意識で意識は意識できないのだ。
- さて、《自分》にとっての「同時」とは何か。
脳が全力で自b→自aを推定し続けているのだとすれば、この連鎖の間に処理される情報は、
《自分》にとっては時間的な差が無いと言える。
だから、おおよそ、《自分》にとっての「同時」の時間幅とは、
あらゆる外部情報や自bを《対象》として、脳が全力で自aを推定演算するのに必要な時間、
ということが出来るだろう。
(※脳にはこれを0.5秒程度に維持するクロック機能もあるらしい。)
この間に認識され、並置されるものが、「同時」に把握されたことになり、原型空間を為す。
(※更には短期記憶や長期記憶を使って、この原型空間を拡張することができる。)
- 今や、私たちは、答えにたどり着いた。
《自分》というのは、持続する自b→自aの連鎖であり、
その形式でしか《自分》というものは定義できない。
自b→自aというベクトルが演算されるには、一定の計算量が要求されるから、
0秒ではない時間が必要となる。この最小単位が原型時間であり、
その間に、互いに異なる概念や対象が並置され、形成される広がりが原型空間であり、
この原型時空を
《自分》が一挙に把握することで、原型的な《意味》が生じているのだ。
現実の人間は、短期記憶、長期記憶、更には歴史・文化・書物などの外部記憶まで駆使して
高度な知的活動を行っているのではあるが、
その全ての人間の最奥にある機構が、この《自分》であり、
内容空疎な仮想点であるが故に純粋で個性の無い、万人に共通の自aという概念をカナメに
人類は情報空間を共有することが出来る。
(※率直に言って、自我と他我の真の共通点は、自aを推定し続けていること、
その一点のみである。自bは、個々人が持つ情報空間の個性に味付けされながら
過去に滑り落ちていくので、既に個々人によって異なるものになる。)
《自分》というものの本質が自b→自aの連鎖であり、
その原型時間・原型空間の在り方は不変なのであり、
これが「私にとってのスケールとは何か」の答えの基盤を為す。
私たちは、健常時・覚醒時には一定の演算能力を持っていると仮定すると、
この「私にとってのスケール」、言わば原型スケールは、身体の大きさには依存せず
いつも一定であろう。(私の意識が肉体にあるか巨大ロボットや巨大アバターの
中にあるかは関係がない。)この原型スケールに対応づける形で
自分の身体の大きさや、外界の様々な対象が位置づけられる時、
スケール感、すなわち「スケールのクオリア」を、私たちは感じることになる。
(※そして、時空よりも本質的なのは、自b→自aというベクトルの連鎖であり、
相対性理論以降の物理学で距離や時間よりも速度の方が本質であると
捉えられていることは、このことと無関係ではない。
そもそも、私たち知性体は、時空という形式を、そのようにしか構成できないのだ。)
- 「スケールとは何か」…それを問うことは、
結局「自分とは何か」を問うことだった。
小さい頃に遊んだ公園のブランコを今見ると、「あれ?こんなに小さかったっけ」と思う。
それは、私の身体が大きくなったからだ。
一方、もしも私が、好奇心に溢れ、脳がフル回転していた子供の頃の
《意識のスクリーン》を、今すぐ「体験」することが出来たら、
「あれ?こんなに大きかったっけ」と思うだろう。
研ぎ澄まされた運動感覚を持つアスリートや、F1ドライバーは、
同じ原型時間内に処理できる感覚情報の量が、一般人とは大きく違うだろうから、
集中時にはずっと広い《意識のスクリーン》を持っていて、
視覚・聴覚・触覚の細かいところまで差異を見つけ出し、
それを情景として一挙に理解し、次の瞬間の精確な判断を導き出せるだろう。
酒を飲んで酔っ払った時は、演算能力が減るので、おそらく《意識のスクリーン》は
狭くなると考えられる。
しかし、酔っ払いは、「《自分》は自分のことを一定に保っている」と思っているので、
粗く狭くなった意識のスクリーンの中に世の中の全てが入っているように錯覚して
妙な高揚感、万能感を持ったりすることもある。
様々な意識の変性状態も、原型時空の歪み、もしくは不全として説明できるだろう。
- 私が私である限り、原型時空は1つの定まった形式であり、
私にとっての《意識のスクリーン》は、いつも一定だと信じてしまう。
一方で、実際には《意識のスクリーン》の広がりは、脳の演算能力や覚醒状態に左右されるから、
(直接比較することは出来ないけれど、)人により状況により異なるであろう。
私たちは、《対象》の大きさを、この原型時空に重ね描いて「大きさ」として理解し、
次いで、様々なものと比較して、「客観的な大きさ」として計測する。
ある瞬間に私たちが感じる「大きさ」は、原型空間に重ね描かれることによって、
《自分》が体験する「大きさのクオリア」になるのである。
(※「時間進行のクオリア」も、同様に説明することができる。)
「どうして私は、私自身の身体を、斯く在るが如くの大きさで捉えているのか。」
「どうして私は、時間の流れを、斯く流れるが如くの速さで感じているのか。」
私が中学の頃から抱いていた、体感的で素朴な疑問に答えるためには、
いかにして原型時空が維持されているか、という説明が必要だったのである。
- 物理的・線形的な時空間は明瞭に認識できるが、
「いま・ここ」を中心とする原型的な時空間は認識できない、
と、普通の人は思う。
間違いだ。私達は原型時空しか認識できない。
線形時間とか点時刻とか直交座標的空間認識の方が、
言語と共に後天的に書き加えられた幻想なのだ。
言語で考える限り、これを引き剥がすのは容易ではないが、
思考を捨てて、ただ「あるがままを受け入れる」とき、
私達は本来的な原型時空認識と、それを受け取る無色透明無味無臭な自己の核(すなわち「いま・ここ」)を
「感じる」ことができる。
|
自己無矛盾性
|
|
宇宙のルールすら変化する。しかし自己無矛盾性は保たれている。何故か。
|
【仮説】:
《意識》が認識する《世界》、《世界》が生み出す《意識》は、対等の関係にあり、
《世界》が内包できる《意識》の総数と、その《意識》の高等性は、比例する。
◎意味とルール
「自己」では、普遍性の強い要素をルール(基準、手本)として、
個々の新しい浮動要素が書き換わっていく。
この書き換えが「観測」であり、過程自体を「現在」と呼ぶ。
今、「自己」Sの要素は有限個であり、全てが列挙可能であるとしよう。
Sの要素をeと表記すれば、S={e1,e2,....,eN}
である。各要素には、「普遍性」という属性が付着する。
「普遍性」とは、その要素の安定性であり、何世代に渡って存在し続けてきたか、
ということを表現する。各要素は組み合わされて爆発的に新たな要素を作成するが、
普遍性を持つ要素からの「引力」が強くなり、その増加速度は次第に減速する
※可能性の自由度が減ってくる。
「素粒子」や「力」が一旦形成され、たまたま再利用され、
普遍性が高まると、以降の変化は、これらの普遍要素の枠組みの中で
行われるようになる。「意味」も同様で、普遍的意味要素が形成されると、
以降の意味要素も、この普遍要素が制限として働くようになる。
※意味世界が冷えて固まってくる。
意味の複雑化は、結局、自己Stの観測の結果得られる自己St+1について、
完全にSt=St+1になる平衡状態まで続く。これが自循構造の終局状態であり、
普遍要素が十分に確立して、それを適用すべき浮動要素が無くなったことを意味する。
※差異が無くなり、変化が消えたときが、その世界の終わりである。
全構成員がルール(法律、普遍要素)となり、
どう組み合わせても新たなルールは作られず(つまり既存のルールに合致し)、
ルールを適用すべき構成員も一人もいない状態である。
過去時点のStから、有限の手続きで未来時点のSt+1が作成される。
St+1は、Stの単なるコピーではなく、また単純な組み替えでもなく、
Stに対して普遍性、ルールを適用した結果となる。
新たに作成された要素のうちの幾つかは、
時代が下るにつれて普遍性を帯び、ルールのカテゴリに沈殿してゆく。
※ルールが場の粒子だと思えばよい。
この変化の過程が「現在」として認識される。
客観的には、確定しているのは未来時点の自己St+1と過去時点の自己Stであり、
「現在」とは、この中間の「過程」である。
※「過程」は対象とは成り得ない。
従って「現在」を「観測」することはできない。
客観的には、未来時点の自己St+1は、過去時点の自己Stを「観測」することによって
自己のありようを決定した、と解釈することができる。
論理学の「変項」と「ルール」の関係は、自己の全要素について、
普遍性が「ある」「ない」と、極端に分けたモデルである。
現実の世界には、そのような明確な境界は無い。
「変項」と「ルール」に境界が無いという状況は、コンピューターに喩えると
「変数」と「プログラム」が、同じメモリ上に存在し、原理的にはどちらの
意味も変わり得るという状況に似ている。(実際のコンピューターでは、CPU
やOSの機能によって、メモリ上の数値が変数なのかプログラムなのかの
境界を明確にしているが。)
実際、人間の意識を発生させる脳という仕組みは、ニューロン回路で形成されて
いるが、シナプスの結合度の変化によって回路の特性が変化していくことが
「記憶」と「思考」を渾然一体と更新させていくのであり、
そこに明確な境界は無いのである。
※この宇宙の物理的な意味世界では、時間的にルールが作られ、
残りの可能性と物質に別れ、徐々に物質として沈殿する。
ルールはいわば「空間の遺伝子」である。(ルールも変化する。)
※そして、この「空間の遺伝子」には、この意味世界自体が
いずれ終わるためのルール(自死遺伝子)が含まれている。
そして可能性はどんどん現実に崩壊する。
※最終的に、意味世界には変化の可能性が無くなり、
完全に具体化された世界からは、それ以上の意味が生まれることもなく、
《世界》は死ぬ。
※この宇宙が消滅しても、この宇宙の「空間の遺伝子」を持った
新たな宇宙が、ブラックホールの向こう側でビックバンを起こし、
無数に生成されているかも知れない。この宇宙自身も、そうして
複雑精妙な構造を形成可能な「空間の遺伝子」の淘汰の果てに
形作られた宇宙の一つかも知れない。
※それは「1プランク長・1クロノス」の間に内包され秘められている
様々な物理定数や物理法則の由来、つまり「向こう側の世界」の話であって、
差し当たり我々の意味世界にとっては無意味である。
※いずれにしても、「この1個の宇宙、意味世界」を唯一絶対のものと
して崇め奉るコペルニクス的転回以前の考え方は前世紀のものである。
我々にとって有意味な宇宙は、人間原理宇宙論的に言えば我々のために用意された
と言えるし、自循論的に言えば我々とこの意味世界は対等で相補的である。
一方で我々の宇宙以外にも宇宙は無数に(もしかしたら無限に)存在するかも
知れない。だが、その仮説は無数に形成可能であり、同時に無意味である。
人間の叡智の限りを尽くした結果、意味の限界=意味の素粒子=自循構造が
明らかになってきた。何故、この宇宙がかくも複雑精妙であり、その副産物である
星々や生命と、生命進化の現時点の頂点にある人間が持つ意識が、かくも不可思議
であるかは、この宇宙一個以上の無数の意味世界の存在を必然的に想起させる。
それは、我々の科学技術や思索の未熟さによるものではなく、
本質的な意味的境界であり、その向こう側にあるものは本質的に無意味な『神』である。
私達には、無意味な『神』のモデルを色々と夢想する永遠の自由が与えられている。
◎意識と世界
《意識》と《世界》は対等である。
世界内で意識による選択(世界の枝分かれ)を許容しながら
個々の枝が安定した自己無矛盾性を維持しているのは、
《世界》を共通認識する《意識》が多数存在することに立脚する。
他者性・客観性は、《意識》という複雑な現象が組み上がり
維持されるのに必要な安定性を確保するために要求される。
世界が内包できる意識の総数と、その意識の高等性、比例関係にある。
もし、ある世界がたった一つの意識を生み出し維持する容量しか無ければ、
その意識自体も単純なものであり、その意識が認識する世界も単純である。
そして、その「たった一つの意識」にとってさえ自己無矛盾であれば、
世界の枝の全ては有意味であり、かなり極端な構造的変化も許容され得る。
そのような不安定な世界では、高度で複雑な意識を育てることは難しい。
我々の《世界》を支えているのは、我々の《意識》の総体である。
世界が安定しているのは我々の総意であり、
世界が安定しているからこそ我々の意識は高度で複雑なものに育ったのである。
原理的に、一人一人の《意識》と《世界》は対等である。
だからこそ、一人一人が、限り有る生を力いっぱい生きること「のみ」が重要であり、
その意味は最大化されるのである。
◎意識と時間
《意識》というものは、驚愕的に複雑な生命活動の断片として
脳内で発生する一現象に過ぎず、結局、物理的プロセスとして全て説明可能であるとする。
そして、現実に《意識》を持っていると告白するロボットを構成できたとする。
それで全てスッキリするのか、というと、少なくとも私はスッキリしない。
きっと私はロボットに向かって、「意識や心が物理現象だとしても、
この『自分が自分であるという特別な感じ』は、どうして発生するんだろうね?」
と相談し、一緒になって考え続けなければならないだろう。
突き詰めると、この不可思議性の原因は「自己言及性」に絞られる。
そして、自己が自己を参照する、という構造は、
《時間》という仕掛けがあって初めて可能になる。
むしろ、変化しつつある自己が、一瞬間前の自己を記憶している、
というプロセスの連鎖が、《時間》という仕掛けを浮かび上がらせる、
と言った方がいいのかも知れない。
結局、《意識》と《時間》は表裏一体の関係にある。
《意識》という一貫性を持った変化があってこそ《時間》は認識され、
《時間》という自己言及を可能にする仕掛けがあってこそ《意識》は生じうる。
《意識》は極めて精緻で複雑な生命活動・物理プロセスに支えられて成立するが、
その物理法則の全ても、《意識》の「自己言及性」を支えるのに必要十分なように意味づけされる。
《意識》の「自己言及性」という構造を万人に保証するために相対性原理があるし、
《意識》にとって「それ以上の時間的・空間的に細かい自己参照性は意味を持ち得ない」という限界性を
マクロに表現したのが光速度不変の原理で、
ミクロに表現したのが不確定性原理である
限界性を示す物理法則や物理定数は所与の偶然の産物というよりも、
我々の《意識》が宇宙を見る以上、どうしてもそのような法則や定数が
あるようにしか見ようがない。それが究極の理由なのである。
《意識》の生い立ちを物理法則に還元しようとしても、
その物理法則自身の生い立ちが《意識》に還元されてしまう。
この循環構造こそが、《意識》の不可思議性の本質なのだ。
|
科学と自循
|
|
自循論の知的思考フレームワークで科学を読み解く
|
自循論の知的思考フレームワークは、
科学、哲学、宗教のさまざまな知見から蒸留されて構造化された。
その知的思考フレームワークを、再度、科学の諸課題に当てはめ、
自己参照性と不可知性の観点から、
自循論の切れ味を確認してみよう。
¶
「私という意識の一点(いま・ここ)」は、それ自身を知り得ない特異点である。
それは、知る側にあり、知られる側に無い。
そして、宇宙の内側・時間的領域・プランク長以上
(光速・重力定数・プランク定数に縁取られた現象界)
を知っている。
また、宇宙の外側・空間的領域・プランク長以下を知り得ない。
一方、意識の世界に目を向けてみると、
「私という意識の一点」の周囲に内観可能な自己意識の領域があり、
その外側に、内観不可能な無意識領域が取り巻いている。
共通する構造として、「私という意識の一点」Aは、それ自身を知り得ず、
その周囲に、知ることの出来る領域Bがあり、
その外側に、知り得ない領域Cがある。
そして、抽象的で意味論的な位相空間においては、A=Cだと言って良く、
そこでは非常にシンプルに、一定の知らない領域を認める(X=A=Cの)代償に、
一定の知る領域(Y=B)を勝ち得ている、という
この意味世界のアーキテクチャを描くことが出来る。
世界は極めて自己完結的であり、XとYの境界Z(鏡面)は
自己完結的な世界の数だけ無数にあって構わない。
私達がたまたま採用している境界Z1に、存在理由(レゾンデートル)は無い。
強いてあるとしたら、それ自身にある。
- ニュートン力学における“神”の視点である絶対時空に対して、
相対性理論は「相対性原理」と「情報伝達速度の限界」を導入したが、
これは、「情報の受け手」としての
“自”を中核に据えた結果であるとも言える。
実際、相対性理論に関するアインシュタインの発想の原点は、
“神”から見た宇宙ではなく、“自”から見た宇宙とは
どのようなものか、という事だった。
量子力学は、本質的には「物理的実在として観測されるもの」
と「情報的存在として計算されるもの」が
どのように異なり、どのように対応するのか、
という事を表現しようとしている。
つまり、あの世の“神”ではなく、この宇宙の内部に住む
“自”から見た(観測された、もしくは計算された)宇宙を
記述しようとしているのである。
実際、「不確定性原理」も、「何かを確定しようとする“自”」
「情報を取り出そうとする“自”」を
中核に据えるからこそ、意味を持つのである。
大雑把に科学の歴史を振り返ると、
「意味」を剥奪されて無味乾燥に完成したニュートン力学が、
相対性理論や量子力学によって“自”を注入され、
より「“自”にとっての真実」に近づき、
最終的には自循論の枠組みの中で再整理される。
- 不確定性原理は、私達の観測の精密さに限界がある、
と言っているのでは無い。
私達が主体的に観測するという余地を保証しているのである。
相対性理論の光速度不変原理は、私達の移動速度に限界がある、
と言っているのでは無い。
私達が常に順序立てて物事を認識できることを保証しているのである。
- 結局、物凄く煎じ詰めると、私の科学哲学の源泉は、
「定まっているスケール」に対する違和感なのだ。
なぜ、1秒は、今あるがごとく、1秒後に、1秒だけ進むのか。
なぜ、1メートルは、今あるがごとく、1メートルの大きさなのか。
そこに「理由」があるとしたら、どう考えたって、
分解能の最小単位や、
考えられる有限の最大の範囲、
といったものが無ければならないではないか。
だから、私にとっては、
相対性理論とかビッグバンとか量子力学は、
その数学的・物理学的な難解さとは裏腹に、
物凄く「しっくり来る」のである。
- 量子力学の世界を「不思議だ」と感じるのは、
時空が無限に滑らかだと思い込んでいるからに過ぎない。
しかし、幾らでも細かく時空を分割できるとする世界の方が、
良く考えてみると、よっぽど不思議である。
そのような無理な仮定こそが、
「アキレスと亀」のパラドックスを招来している。
現に、時間は進み、モノは移動しているのであるから、
我々には想像もつかない超ミクロなスケールでは、
何らかのジャンプが起きているはずである。
A点にあったXが消滅して、
近傍のB点にX'が生成される、という現象において、
A→Bの間の点が認識できず、
XとX'の見分けがつかなければ、
我々はXがAからBに移動したと認識せざるを得ない。
そこにどんな複雑な消滅と生成の仕組みが隠れていたとしても。
つまり、こうだ。
認識という現象の根底には、
自分Sが自分S'を見る、という本質的なジャンプがある。
だから、自分は、世の中を飛び飛びにしか認識できない。
逆に言えば、このような「認識」というものの性質があるからこそ、
自己を取り巻く周囲の現象に対して「XがAからBに移動する」というような、
大雑把な見方が可能になるのだ。
勿論、「移動」という概念は、「時間と空間」に分割される。
つまり、時空という概念は、
自己認識という特殊な現象によって捏造されるものである。
自分が自分であるという本質的なジャンプの連鎖によって、
自己認識は激しく明滅するストロボ・フラッシュとなり、無から有を浮かび上がらせる。
世界とか時空とは、そのような生い立ちを持つので、
一生懸命に細かく調べていくと、世界のあらゆるものは、
どうも飛び飛びに動いているように見えるのである。
この宇宙とは全く別の物理法則で成立している宇宙で、
私達とは全く違う作動で生きている知的生命体が、
自分達の世界を一生懸命に細かく調べても、
やはり量子力学のようなものを発見することになるだろう。
つまり、認識するものは、量子力学を発見せざるを得ないのである。
|
量子力学
|
|
量子力学の不可思議性は、自循を基準に考えると自然化される。
|
◎量子力学の解釈問題:
(1) 本質的不可知性:
量子力学は、不確定性原理によって「本質的な不可知性」を提示している。
※観測技術の未熟さや知的活動の怠慢を意味しているのでなく、逆に
精巧な観測と高度な知性によって、この不確定性は証明されている。
(2) 新しい可知性:
不確定性原理(オブザーバブルの相補的非決定性)に代わって得られた
境界条件・初期条件によって定まる「状態」という考え方。
※確率計算上の「確実な」法則
※ある粒子の位置と運動量を正確に特定することは出来いないが、
その確率分布は「完全に正確に」把握することが出来る。
(3) 新しい可知性の前提条件:
「状態」が確実に定まるのは、この意味世界が有限だからである。
* 時間の有界性…初め(アルファ点)と終わり(オメガ点)がある事
* 空間の有界性…状態が広がる空間のありよう、
※有界であるからこそ「可能性のあり方」=「状態」は定まる。
もしこの世が時間的または空間的に無限なら、今が今のごとく
ある理由どころか、何が可能性として有り得るかも決まらない。
つまり、意味など何もない世界になってしまう。
※「イデア界」は「可能性の世界」「まだ現実に崩壊していない世界」
であり、この意味世界の境界条件から「確実に」定まっている。
※有意味であるからには、この意味世界の有界性は自循構造を
継承したものになっている。
《量子力学の不可思議性の自然化・1》
自循論の立場を明確にする。
・知的存在の観測によって波束が崩壊して粒子になる(コペンハーゲン解釈)
※人類誕生前の宇宙の否定、道具主義、脳産教理
※番犬効果によって否定されているとも言われる
※不可知性に対する物理学者としての一種の真摯な態度なのかも
知れないが、自循論ではもう少し意味論的な考察を深めたい。
・観測が行われるたびに宇宙は分裂して
無数の並行宇宙が出来上がる(エヴァレット解釈)
※面白いが無意味
※ちなみに、エヴァレット解釈は、暗に【有限原理】を採択している。
すなわち「知的存在による観測」という、1回、2回と数えられるタイミングで、
可能な組み合わせの数の宇宙の分裂が起きているとしている。
そして、その場合の数も、高々可算有限個であろう。
・現在とは、過去からの波動と未来からの波動の干渉した場である。
※数式の上での「未来からの波動」を、意味論的にどう解釈するかは
非常に難しい。一般に「未来から過去への運動や通信」という概念は
数式上存在しても、人間存在にとって何の意味があるかは厳密に
問われなければならない。(大抵は無意味だったり循環論法の産物
だったりするので注意しなければならない。)
これらの解釈は、善良なる賢人が考え抜いた結論であり、何らかの真理の一面を
提示してくれているのであろうが、難解かつ不自然である。
自循論では、より抽象的だが、より自然な考え方の指針を提示する。
(1) 我々にとって有意味な世界は、たった一つである。
※多世界解釈は、量子飛躍や観測者効果の幾許かを、より自然に
説明できるとしても、分裂した世界と交信が出来ない以上、
無意味であり、無意味なものは自循論の範疇ではない。
※「自分を自分だと感じるこの特別な感覚」を突き詰めて考えたいので、
何かが自然に説明できるとしても「この特別な感覚を持った自分が
並行に無数に存在する」という説明は、少なくとも方向性は全く異なる。
(2) 我々の宇宙を捉える視点は、幾つあっても構わない。
※三角錐を側面から見るのと真上から見るのではまるで違う形が
見えるが、三角錐という実在が分裂したわけではない。
私を「生命として」「人間として」「会社員として」見ると、
それぞれ違った役割や性質が見えるが、私という実在が
分裂したわけではない。
※素粒子を波と捉える視点と粒子と捉える視点の両方が
存在していも構わない。私たちは、二重スリットの実験を
波として計算しても良いし、粒子として観測しても良い。
※視点をどう選んでも良いという自由が我々には与えられている。
二重スリット実験では、“感光板を置く”ことによって、状態を
粒子として観測するという“視点を選択”したことになる。
→ 【視点の無償性】
(3) 時間は一方向に流れる。
※意味は本質的に自分を参照するというプロセスから生成され、
それは1つ目、2つ目と数えられる順番・順序であって、
逆にすることに意味は無い。これは数式の解釈などという問題
ではなく、時間というものの本質的な定義である。
※意味世界は時空の境界条件により形作られる。従って、
未来のありよう、特に意味世界の終わり(オメガ点)は、
現在のありようを可能性レベルで確実に規定している。
(可能性を現在どのように具体物に崩壊させるかまでは
規定しておらず、そこに自由は残されている。)
※このことを「現在の状態が未来の状態(境界条件)からの通信
によって影響を受けている」と表現することは、時間の本質的な
定義に反する「言い方」なので、避けるべきである。
※未来の境界条件は、現在のありように内包されている。
意味世界が終わることを「死」と呼ぶならば、我々の住む
物理宇宙や意味世界は「計画的に自殺しつつある」と言える。
つまり、未来からのメッセージではなく、現時点の計画なのだ。
《量子力学の不可思議性の自然化・2》
- 量子力学の不可思議性に対する自循論の解釈は非常にシンプルで、
以下の2つの考え方を出発点に用いる。
- 有限原理:
有意味な世界は大きさも細かさも無限では有り得ない。
1プランク時空の内容がどんなに複雑でも
我々はそれを差異や意味として知り得ない。
- 二重世界モデル:
この世界は、意識が物理世界に情報世界を重ね合わせたものである。
過去や未来は情報世界に属するモデルであり、
粒子性は物理世界、確率波としての波動性は情報世界に属する。
量子力学の実験の中でも
量子消去
という現象は大変不思議に思われるが、
それは情報世界に属する計算上の波動の振る舞いを、
物理世界の描像で無理矢理考えようとするからだ。
第一、『確率波もしくは粒子が二重スリットの位置を通過したはずの時刻』
という考え方自体が間違っている。
一個の電子が電子銃から発射された時刻と、
スクリーンに一個の電子としての痕跡を残した時刻だけが
物理世界における現象(事実)であって、
その間の出来事は全て情報世界のモデルに属し、
言わば「一定範囲の時空連続体上にボンヤリと広がった
想像上の1個の状態」でしかない。
観測していないのだから、物理的事実は何も無いのだ。
そして、(ここが極めて自循論的な考え方なのだが)
私達は情報世界のモデルに沿ってしか物理世界を観測できない
のである。
私達は私達なりのやりかたでしか、世界を照らすことができない。
干渉縞は、私達自身がアプリオリに持たされている
「世界を理解する方法」の結果、必然的に表現されたものだと言える。
粒子がスクリーンに到着する「前」に、
二重スリットのどちらを粒子が通過したかという観測情報を
原理的に分からなくする(消去する)と干渉縞が復活する、
というのも、この実験装置自体の情報世界のモデルを
途中で何も観測していない場合と同じにしたのだから、当たり前の話なのだ。
(コヒーレンスが保たれている間に外部擾乱を取り去ったのだから
全体として可干渉モデルに従うのは当然、という言い方もできるだろう。)
- コペンハーゲン解釈は、
「物理世界の粒子性」と「情報世界の波動性」を、
同じ一つの物理世界に押し込めて考えようとしたから
「一瞬にして波が粒子になる」といった、おかしな表現になってしまった。
エヴァレット解釈も、
この世には物理世界しか無いと考えたから、
並行し分岐する物理世界を無数に持ち出すという、
飛躍した結論になってしまった。
現象を考察する時、その要素を
注意深く「物理世界」と「情報世界」に分けていけば、
このような混乱は解消できるであろう。
おそらく、「ポテンシャル」「場」などの考え方も、
情報世界に帰属させ、
「私達が、世界を見るときに、仕方なく持たされている枠組み」
として考え、物理世界の領分をもっと慎ましいものにした方が
この世の成り立ちに沿った自然な描像が得られると思われる。
《量子力学と意識》
意識とは何か、ということを突き詰めて考ると、
量子力学の不思議さに対して、分かりやすい説明ができる。
まず、この世界の総体は、《自己規定的》である。
無数の可能性の中から、いまあるがごとくある世界だけが存在していると
意識される理由は、意識している側の方にあり、それ以外に理由は無い。
むしろ、意識する側と、意識される側は、セットで存在するのであり、
どちらかがどちらかの原因だとか、どちらかの方が根源的であるとか
言おうとすること自体が、無意味である。
「右と左のどちらが本質的か」と問うのが無意味であるのと同じだ。
次に、ある時点で意識が捉える世界の全体に対して、
自己無矛盾な(妥当性を持った)“次の”瞬間の世界の全体は、
無限ではないとしても無数にはあるだろう。
意識は、無数にある、その全ての枝に存在するが、
そのうちの一つの意識にとっては、
「なぜ、無数の可能性の中から、今あるがごとくの現実が選択されたのか」は、
絶対に分からない。なぜなら、本質的に理由など無いからだ。
全ての現実は等しく存在しており、そのうちの一つが特別だという理由は、
その内部に捕われている意識の都合を除けば、何一つ無いのである。
これが、量子力学で言うところの「観測問題」の本質だ。
特定の意識の流れに沿って考えれば
瞬間的に可能性が一つの具体物に定まる不可思議な「波束の崩壊」が観測されるし、
一方、枝分かれする多数の意識を神の視点から俯瞰すれば、これは「多世界解釈」になる。
無限乱雑空間上に生じる全ての「意識」について、
その一つだけを追って世界を解釈するのか、
世界ごと枝分かれして無数の意識が存在すると俯瞰するのか、
それは文字通り解釈の違いであって、同じ本質の異なる断面に過ぎない。
更に言ってしまえば、自己矛盾を引き起こすような状態への枝の上にも、
意識があっても良いのかも知れない。劇的に世界が消滅する枝もあれば、
徐々に法則が捻じ曲がって意味が雲散霧消する枝もあるかも知れない。
しかし、そのような枝には、安定した自己参照性を前提とする「意識」という現象は
生じないと考えるのが妥当であろう。
◎巨視・微視での意味の限界:
この世界は、ある種の相を形成している。
※「相」とは、連続体の任意の2つの微小部分の性質が、ある粒度で
見た時に「同じ」と見做せる状態のこと。均質で偏りが無く、従って
安定である。ある微小な粒度で生じた空間の性質(法則・力)の
偏りは、さらに複雑化して一つ上位の粗視的なレベルでは相を
形成して安定しようとする。(安定したものだけが相を為す。)
※素粒子(フェルミオンとボソン)のレベルで生じた偏りは、
宇宙という相を為して我々のレベルではおよそ安定している。
宇宙も複数集まって更に上位の相を形成しているかも知れない。
※量子力学が提示する本質的不可知性は、こうった相の階層間での
本質的なコミュニケーション不可能性の一種である。
相を超えたコミュニケーション(神との交信)の可能性は
無意味な議論であり、自循論の範囲外である。
《プランク時空での意味限界》
(1) プランク長、プランク時間内の出来事は、少なくとも現在の
我々の物理学の到達点(相対性理論と量子力学)の範囲では
無意味である。
(2) プランク新時代 planck epoch とは宇宙開闢から1プランク時間が
経過する間の、ほんの5.391×10-43秒程度の間の時代のこと。
この時期、4つの力(重力・電磁気力・強い力・弱い力)は未分化な
一つの力で、素粒子はまだ存在していなかった。
従って我々にとって意味のある宇宙はゼロの状態から始まったというより
1プランク時間(1クロノン)経過した時点から始まったとも言える。
(3) 今現在も我々が感じる1秒の間に約1.855×1043(1,855正)クロノンが
過ぎ去っているが、第Nクロノンと第N+1クロノンの時刻の間に
何が起きているかは(少なくとも今のところ)我々人類にとっては不明である。
この1クロノン(時間量子)の間に、観測者効果、物質と精神の相互作用、
量子飛躍、並行宇宙の分化などの「秘密」が隠されているのかも
知れないが、今現在の人類の科学力や想像力では、その微小時間内に
切り込んでいくことはできない。
(4) 結局、宇宙全体には、始まりと終わりがあり、1クロノンずつ進むので
時間は無限ではなく、全部で何個の状態があった、と数えられる。つまり
時間は、たかだか可算有限個である。もし宇宙の寿命が
10100年程度であれば、これは約10150クロノンに相当するから、
我々がたまたま住んでいるこの宇宙は、1090個程の素粒子を記録できる
フィルムの10150コマ程度で作られた一本の映画だと喩えることも出来る。
(5) フィルムのあるコマと次のコマの間で何が起きているかという事を
問うことは、フィルムの中の登場人物に過ぎない我々にとっては、
少なくとも当面は無意味であろう。
※下位相に対する本質的不可知性。
また、この映画を誰がどう楽しんでいるかということも我々には無意味であろう。
※上位相に対する本質的不可知性
どのような仮説や想像も、この意味世界とは独立で無意味なので、
自由に行って構わない。
- 《真空の性質》
光子は、
実は、我々が観測不可能な無限小の質量を持っていても構わない。
光速度不変の原理は、
光子について言っているというよりも、もっと抽象的に、
情報的な因果律が伝わる速度は常に一定である、ということを言っている。
因果律伝播速度(≧光速度)より遅い速度で何かが伝わるように見えるのは、
情報伝達を担う素粒子がジグザグ動いて寄り道をしているからである。(Zitterbewegung現象)
ジグザグ動くので、そこに「動きづらさ」すなわち「質量」すなわち「エネルギー」が
存在するように観測される。
因果律伝播速度で移動するもの(ルクシオン)それ自身は時間経過を感じないが、
ジグザグ動いていることで外部からは時間経過があるように観測される。
(よって、素粒子の属性の「変化」というものは、
時間経過が凍結されている素粒子それ自身の変化ではなく、
全てこのジグザグ運動の様態(モード)の結果として観測されるものである。)
なぜジグザグ動くのかというと、それは真空中に埋まっているものとの相互作用の結果だ。
真空の性質によって、素粒子は質量(存在)を得るし、
時間というものが流れるようにもなる。
結論:存在と時間の起源は同じであり、それは真空の性質である。
では、「真空」とは何かというと、それは単に
「今の私達にはカラッポにしか見えないもの」である。
「真空」の一粒の中身は、我々が観測しているこの宇宙全体より複雑であっても
全く構わないし、それを禁止する原理は定義より存在し得ない。
- 真空というのは何もないところではない。
我々が知覚できないものが無限に詰め込まれていると言った方が良い。
真空から粒子・反粒子が対生成されると
「何もないところから何かが出てきた」
と我々は感じてしまうが、それは我々の都合なのであり、
実際には性質が打ち消しあって我々に知覚出来ないものが
真空の中に無限にギッシリ埋め込まれている、
と考えた方が遥かに自然である。
- 「素(そ)であるもの」は、突然生まれたり、
消えたり、飛躍したり、入れ替わったりする。
「素である」とは、何者かにとって、それ以上は分解できないと
認識されている、ということである。
巨視的な現象とは、そんな乱雑さに由来する誤差率を抑えた、
安定した相であり、
何かが突然生成されたり、遠くに移ったり、
性質が変わったりはしないものである。
そういう鈍重な安定性を得るために、
素粒子に比して原子は非常に大きく、
分子に比して生命は馬鹿げて大きいのである。
- 私達が殆ど安定しているのに、
なぜ素粒子がそんなに突飛なのかと訝るのは本末転倒である。
実態は、素粒子の荒唐無稽なまでの自由奔放さの中に共通する、
僅かな偏りを懸命に掻き集めて、
超巨大な私達が、仮初めの安定性を統計的に勝ち得ているに過ぎない。
それは即ち、「真空」という恣意的な概念を鏡面として、
結局は私達は私達なりのやり方で私達自身を見ている、
ということに過ぎない。
私達の偏った巨大な複雑さは、私達が真空と呼んでいるものの
最小単位の更に内側に仮設した複雑さの偏りと相同である。
「色即是空、空即是色」とは、そういうことなのだ。
- 様々な実験における量子力学の数式をじっと見ていると、
「対象が原理的に区別できるか否かで採用すべき公式が変わる」
という事が分かる。
(例えば、確率振幅を二乗してから足すか、
足してから二乗するか、という違いである。)
「原理的に」というのは、人間が観測しようと思ったか否か、
というような認識論的な話は関係ない、ということであり、
巨視的な相に永続的な区別の傷跡を残すか否か、という事である。
おそらく、情報として明確かつ永続的に区別が付くものを、
私達は単に巨視的と呼んでいる。
(ちなみに私達はスピンの向きが同じ2つの電子を区別することは
できない。区別できる場合と出来ない場合で、採用すべき数式は
異なり、実験結果は採用した数式に完璧に従う。)
量子力学が物理学であるという事実は非常に重要だ。
情報世界において“区別がつく場合”と“区別がつかない場合”があった時、
物理世界においても、現実のリアルな存在が、
全く異なる挙動を示す、と言っているのである。
つまり、物理世界が情報世界に従属しているのである。
常識的には、まず確固たる物理世界があって、
そこから読み取られる情報世界が従属する、と考えたくなるのだが、
現実の世界は、そうはなっていない。
区別=意味=差異=変化=速度は、だから何よりも根源的で、
意味世界(=物理世界+情報世界)において最も根源的なものである。
根源的に“区別できるか否か”で、情報は勿論、物理もガラリと変化するのだ。
その、最も根源的な単位を軸として、
物理世界と情報世界は、詰まるところ対等であり、表裏一体なのだ、
という事を、量子力学は暗示している。
|
相対性理論
|
|
光速という限界こそが、この世の中を有意味に保っている。
|
◎光速という限界
(1) 世の中がプランク定数の3次元格子に捉えられた素粒子の集合であり、
時間が1クロノンずつ進むとしたなら、速度の限界が光速であるという事は、
単に一つの素粒子は1クロノンの間に「隣の位置」としか相互作用しない、
という事だと言い表せる。
※1クロノンは1プランク長と光速から定義されるので、より本質的なのは
プランク長と光速であるが。
(2) まるでライフゲームのようだ。
この宇宙は、本当に神が作ったライフゲームなのかも知れない。
一つの格子が隣接する格子としか相互作用しないという規則は、
神が創ったこの宇宙の演算装置の計算量を合理的に減らす方便だったのだろう。
(3) 相対性理論は、時空において、光速より早く伝播するものは無いとした。
そして、それぞれの「自己」が見た世界は、お互いが相対的にどう運動していようが、
一定の秩序があるとした。
※亜光速に運動する人間がお互いにすれ違おうとする時にも、
相手は光速度を越えて運動しているようには見えない。
その原則を守るために、物質の長さや時間の進み方や同時性まで
絶対的なものではないとしてしまった。
(4) 限界の発見は豊穣な意味を生む。(有限原理)
量子力学も不確定性原理という限界性を発見して豊穣な意味を生んだ。
これからも、我々は、本質的な限界性を見つけるたびに、
新鮮で豊かな意味を味わうことが出来るだろう。
- 相対性理論における“近く”の計量は、
従来の3次元空間の考え方の延長にあるのではなく、
全く違う世界観を提供している。
古典物理学では、誰から見ても1メートルのものは1メートルだし、
3秒間は3秒間だ。
しかし相対性理論では、長さや時間は伸びたり縮んだりする。
誰がどう見ても変わらないのは、長さや時間ではなく、光速、および
『空間的距離2-光速2×時間的距離2』という量である。
この式に、自意識の存在する1点、すなわち「距離=ここ(0)」「時間=いま(0)」を入れると、
答えは0になる。
そして、「距離=1億光年」「時間=1億年前」を入れても、答えは0になる。
「つい今しがたの3メートル離れた隣の部屋の妻のあくび」よりも、
「遥か一億光年彼方の一億年前の超新星爆発」の方が“近く”にある、と言える。
つまり、「今ここ」という自意識の一点に対して光円錐上近傍の事象は、
時間的、空間的にどんなに離れていても“近く”にある。)
そして、この事情は、特定の一人の自意識だけでなく、
誰の自意識にとっても等しく成立する原理である。
もし素粒子一個一個が意識を持っていたとしても同様である。
- 静止して一定の距離を保っている二つの意識A、Bを考える。
下図でAにとっての「いま・ここ」から伸びるX形の線は
光の軌跡を表す光円錐であり、違和感があるかも知れないが、
特殊相対性理論によると、この線上の全ての出来事は、
Aにとっての「いま・ここ」そのもの(ゼロ距離)である。
光円錐と点線に挟まれた領域は、Aにとっての(時間的な領域の)「近く」を意味する。
時間的・空間的に離れていてもAにとって「近く」ということは有りえて、例えば
一億光年離れた一億年前の出来事は、Aにとっては、まさに「いま・ここ」になる。
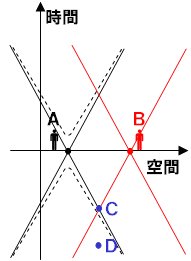
- さて、X形の上下の領域はAから見て情報伝達が可能な出来事を表す領域、
左右の領域は永遠に知ることの出来ない空間的に離れた出来事を表す領域である。
C点の出来事は、時間的・空間的にはA、Bと隔たっていても、
A、B両方にとって「いま・ここ」であり、実体験として共有している出来事である。
(例えば、遥か遠方・過去で起きた超新星爆発の光(情報)を、
静止しているA、Bが同じ時刻に“体験”した、ということ。)
D点の出来事は、A、Bともに、過去のちょっと離れた場所での出来事として
情報を共有している。
(超新星爆発の例とは時間スケールが全然違うが、例えば
A、B二人の丁度中間で5秒前に消えた線香花火の最後の光を
記憶として共有しているような状況。)
- 脳味噌を混ぜ合わせでもしない限り、意識A、Bの所在は空間的に離れているから、
A、Bの「いま・ここ」という体験は、空間的に離れ、情報共有が不可能な、
お互いに知りようの無い出来事である。
A、Bが共有できるのは、各々の光円錐が重なり合う領域の出来事のみである。
この物理世界の光速度は非常に光速なので、
日常的なスケールでは
A、Bの間に情報共有不可能な領域があるとは殆ど感じられないが、
相異なる位置を占めるA、Bは、ある程度過去のものしか
共有できない、というのは事実であり、
特異点としての「いま・ここ」はお互いに共有不可能だ。
見方を変えると、ありとあらゆる出来事の「いま・ここ」は
独立で一回限りの事象であり、あくまでも未来の意識によってのみ、情報として
共有される可能性がある、ということだ。
- 微視的に見ると、
質量のある素粒子(ブラディオン bradyon)は
Zitterbewegungする(光の速度でジグザグ運動する)。
質量のない素粒子(ルクシオン luxon)は、
真っ直ぐ光速度で運動する。
つまり、全ては光速度で動くので、「動くもの自身」は
相対性原理より時間の経過を感じていない。
個々の要素を見ると時間は流れないが、
宇宙という複雑な運動の総体で見ると時間という現象が立ち現れる。
このように、時間というものは、絶対的なものではなく、
相対的な相互関係から組み立てられる仮説である。
- 特殊相対性理論によれば、座標系に依らない不変量は
空間距離から時間距離を差し引いたものである。
Minkowski座標系で、
この量が正である領域(空間的領域)とは、例えば
「ちょうど今現在の隣の部屋」であり、
これは永遠の謎である。光速度が有限の値である以上、
私達は「ちょっと過去の隣の部屋の様子」しか分からない。
上述の量が負である領域(時間的領域)とは、例えば
「ちょうど私がいる場所の5分前」であり、
これは過去錐の中にある。
過去錐に含まれる時空点の情報を、
私達は原理的には全て受け取ることができる。
さて、上述の量が丁度ゼロの領域(つまり光円錐)は、
一体何がゼロなのであろうか?
- ある素粒子Aに着目してみよう。
この素粒子Aは常に「いま・ここ」にあり、
自分自身が世界の中心に居続けている。
この素粒子Aには、他の様々な素粒子が相互作用するであろう。
それら全ての世界線は、過去錐の中に収まる。
質量の軽いものは光円錐に近く、真っ直ぐ伸びた世界線を、
質量の重いものは素粒子Aの近くに、ジグザグに折り畳まれた世界線を、
それぞれ描くであろう。
これらの世界線は、素粒子Aとは時間的にも空間的にも
離れた領域にあるが、素粒子Aにとっては、
相互作用が行われた瞬間としての「いま・ここ」だけが意味を持ち、
相互作用した素粒子がどのように複雑な世界線を描いたかは
重要ではないし、情報的に知りようもない。
つまり、これらの世界線は、素粒子Aにとっては全て
「いま・ここ」なのである。
- 結局のところ、人間の知的活動の全ては、
「自分が何者なのか」を問うことだ。
そして、その答えは、自己無矛盾である限り、
無数に有り得る。つまり、正しい答えは、一つでは無い。
結局、科学と呼ばれるものも、「自分とは何か」という
問い掛けの回答になりそうな理論や法則が、
確かに正しいと繰り返し観測できる“実験方法を発見する”営みだ
と定義できる。
一人の天才が、「自己という形式のありよう」を言い表わす、
あまりに素晴らしい比喩を思い付いてしまうと、
多くの人がそれを再現する“実験方法”を発明し、
科学的に事実化してしまうわけである。
(なお、ここで言う観測対象の「自分」には、自己の内面にて認識された、
宇宙の全ての環境も含まれる。)
- だから、例えば私達は、アインシュタインが相対性理論を思いついた、
その最初のインスピレーションをこそ、良く検証もしくは追体験してみるべきである。
光速近くで移動していても、手持ちの鏡に自分の顔は映るはずである………。
その発想の根底には、むしろ相対性理論の原理が予め折り込まれている。
「自分中心」………時空に依らないニュートン力学的な宇宙の絶対法則よりも、
誰かが自分を含む系を観測する場合の形式の方が、優先されるのだ、という直感。
どのような状況にあっても、自己が自己(および自己を含む環境)を観測する時に
絶対不変の“時空と情報の形式”というものがある、という直観。
それは「ある意味で正しい」のであり、その意味において再現性のある実験は、
幾らでも拵えることが出来るのだ。(ここで言う「ある意味」とは、
私にとって意味のある情報を、私が受け取る、という形式においては、
そこに0秒を超える有限の時間が必要だ、という当然の真理である。
更に言えば、観測(もしくは認識)には、有限の時間が必要であるが、
どのような状況でも、また誰にとっても、自己認識が同様であるために、
時空の最小分解能を共通要素として設定するとすれば、
それが取りも直さず距離÷時間=速度の上限、
すなわち情報伝達速度(光速度)不変の法則に結び付く。)
- あらゆる物理法則は、意識の形式から自由でない。
このことは、
「母なる宇宙の物理法則が、意識なる現象を産んだ」と考える唯物論者に対する
良い解毒剤になるだろう。
意識という現象の形式は、万物の法則よりも上位にあるのである。
- 自循論的相対性理論
- 「時空」「質量」「光」…この不可解な知恵の輪は、
どうやったら解けるのだろう。
質量によって時空は歪み、そして
時空内では質量の速度が光速を越えることは無い。
質量の全く無いカラッポの時空には、まるで意味が無いし、
そうとはいえ、時空が無ければ質量も存在しようが無い。
何が最も重要な性質で、何が派生的な性質なのか。
どこから考え始めたら、これらの「意味」が分かるのだろうか。
…そこでまずは、「質量」に軸足を置いて、考え始めることにしよう。
一口に「質量」と言っても、それは実に色々な側面を持つ。
- 動かしづらさ。
力=質量×加速度、運動量=質量×速度。
より大きな質量の物体を加速させるには、それだけ大きな力が必要で、
速度が増した物体は、大きな運動量を持つ。
- エネルギー
エネルギー=質量×光速2。
質量とはエネルギーそのものである。
質量がエネルギーとして放射される時、如何にそれが大きなものになるかを、
私たちは原子爆弾の威力を通して知っている。
- 空間の歪み。
エネルギー・運動テンソル=リッチテンソル-計量テンソル×スカラー曲率。
この有名なアインシュタイン方程式は、「物質エネルギーの分布は、
時空の歪み具合に等しい」ということを意味している。
光は直進する性質を持つが、空間が歪んでいれば、
その歪みに沿って曲がる。(光自身は、真っ直ぐ飛んでいると思っているのだが。)
- 万有引力の原因。
粒子は、真空に埋め込まれたヒッグス粒子にぶつかって、
Zitterbewegungというジグザグ運動をする。
本来、全ての粒子は光速度なのだが、これにより「動かしづらさ」
すなわち質量の種を獲得し、光速度未満の現象が実現する。
粒子同士は重量子(グラビトン)によって相互作用し、
質量が大きければ、より強く引き付けあう。
あらゆる粒子はグラビトンに感応性を持つので、
まさに「万有引力」と呼ばれるに相応しい。
この宇宙が開闢した瞬間(10-41秒後)には重力が存在し、
10-11秒後には、ヒッグス場により粒子は質量を獲得していた。
この宇宙にある、最も古くて、最も基本的なルールだと言えるだろう。
- 存在そのもの。
質量は、カラッポの時空の中に現れるや、それは動かしづらく、安定し、
エネルギーとして有り続け、時空内のランドマークとして「存在」する。
もし、時空内に質量という目印が全く無ければ、時空の距離は測りようが無いし、
質量が幾らでも加速できるなら、目印として役に立たない。
正に「そこにある」という「存在」の形式を与えるのが、質量である。
「質量」は、見方によって、怪人二十面相のように、色々な顔を見せる。
しかし、これらは、たった一つの「質量」という本質の、
別々の横顔に過ぎない。
これら全部の側面を持っている「質量」の本質とは、
一体どういうものなのであろうか。
多分、その本質は、真空の中に深く根を張った何者かであり、
この宇宙に突き出た氷山の一角が、質量として
色々な性質を見せているように思われる。
そして、たった一つの質点も、水面下では空間的に広がっており、
真空内の媒質とぶつかり合って動かしづらさを獲得したり、
質点の周囲に漏れ出した確率波同士が絡み合って、
万有引力を実現したりしているのだろう。
それでは、水面の上と下を分けている基準は一体何なのか。
真空の内側と外側を分けているのは一体誰なのか…。
考察を深めていこう。
- ●『特殊相対性の場合』(見かけの客観的時間の差異)―
質量を、ただ目の前に置いて眺めていても、
時空や光速度との関係は見えてこない。
先ず、「時間」という概念を導入する必要がある。
- しかし、ここで慎重に理解しなければならないのは、
時間の捉え方には2つの種類がある、ということである。
一つは、基準となる地点Aから見て、別の地点Bの
時間の進み方を評価する、という「客観的時間」、
もう一つは、基準時間との比較ではなく、
ある地点Bの中にいる存在それ自身が感じている
時間の進み方、すなわち「主観的時間」である。
- 結論から言ってしまおう。
宇宙は、場所によって時間の進み方が遅かったり速かったりする。
だから、「客観的時間」で見ると、A地点よりB地点の方が
時間の進みが遅く見える、ということは、実際に起こり得る。
ところが、驚くべきことに、「主観的時間」は、
宇宙のどの場所にいても、常に一定なのである。
- 私たちは、手を強く握って開くまで、だいたい1秒くらい、とか、
腕立て伏せをゆっくり30回やれば1分くらい、といった、
リアルな時間経過の体験を持っている。
これが「主観的時間」である。今、私たちはB地点にいて、
A地点から見ると非常にゆっくりと進む時間の中にいるとする。
しかし、他人が私たちの時間をどう客観的に評価していようが、
そんなことは全く関係なく、「主観的時間」は、
いつも私達が体験している時間感覚と全く何ら変わらない。
仮にA地点から見て、B地点の時間経過がどんどん遅くなって、
停止寸前まで遅くなったとしても、B地点にいる私たち自身は、
そのような変化は全く感じない。「主観的時間」は絶対不変なのだ。
- A地点から見て、B地点の時間の進み方が遅く見えるとする。
しかし、B地点では、光速度も、振り子の間隔も、
化学反応の進み方も、人間の思考速度も、全部一斉に
同じだけ遅くなっているのだから、B地点自身にとっては、
何も遅くなっているとは感じられない。
あくまでも、A地点の立場からB地点を見た時にだけ、
相対的にB地点の時間が遅く進んでいるように見えるというだけなのだ。
- 「主観的時間」が絶対不変であるということは、
何を意味しているのだろうか。
それは、『情報伝達速度の上限が不変だ』ということである。
これは、一般的には「光速度不変原理」として知られているが、
光速は、情報伝達速度の上限を代表する速度の一つに過ぎない。
(実際、光子でなくても、質量0の粒子は、全て情報伝達速度の上限で走る。)
もし、情報伝達速度の上限が半分になり、
あらゆる情報伝達速度が半分になっているならば、
全ての物理過程も半分の速さで進行する。
ところで、私達が何事か時間が進んでいると感じるのは「変化」があるからで、
「変化」とは、粒子同士がある速度で走ってぶつかったり、
その事象から発生した粒子がある速度で走って他の何かにぶつかったり、
という事の繰り返しで継続するものである。
何ら粒子の伝播を伴わない「変化」は存在しない。
(もし、そのような「変化」があったとしても、知りようが無い。)
情報伝達速度が半分になるということは、
情報を担って走る全ての粒子の速度も半分になるということであり、
従って、あらゆる変化の速度も半分になる、ということだ。
情報の送り手が単位時間あたりに発生させる情報量と、
受け手が処理する情報量は、共に半分になるのだから、
受け手は、情報量が減ったとか増えたとか感じることは無い。
- 情報伝達速度の上限が定められていれば、
1量子時間(クロノン)後の変化としては、
隣接するフェルミオンの到来と衝突、
5種類の何らかの有限量子数のボソン(フォトン、ウィークボソン、グルーオン、
グラビトン、およびヒッグスボソン)との相互作用、
対生成と対消滅、自発的崩壊くらいを考えておけば良いだろう。
これらのうちの幾つか、または全部が、たかだか1回起こる時間が1量子時間であり、
これが「変化」のバリエーションの全てである。
1量子時間に起こる、この全ての変化のバリエーションだけが、意味や情報の源泉であり、
従って、あらゆる主観の在り方のモトネタである。
(【私たち】が、何か価値があることが起きたと思う時、すなわち
何か情報を得たと思う時、すなわちクオリアを感じた時、そのモトネタの全ては、
情報伝達速度の上限に規定されて万人に共通である。
【私たち】の、差異や意味や価値の「感じ方」は、
宇宙の有り様によって、万人に共通である。)
- たとえA地点に比べて、B地点の時間が一億分の一という
凄まじい遅さで流れていても、
B地点に住む人々は、全ての物理現象をA地点と同じように観測し、
同じように思考するのである。
B地点の人々にとってのB地点の情報伝達速度の上限は、
A地点の人々にとってのA地点の情報伝達速度の上限と同じである。
(つまり、「主観的時間」は、絶対不変である。)
しかし、B地点からA地点を見た時には、A地点の情報伝達速度の上限は、
B地点のそれより1億倍速い。
この時、A地点からB地点を見た時には、B地点の情報伝達速度の上限は、
A地点のそれより1億倍遅い。
(つまり、「客観的時間」は、場所の選び方によって変化する。)
- もし、私がA地点からB地点に移住したとしても、私は、
暗算の速度が一億倍遅くなったり、
円周率を思い出すのに一億倍の時間が掛かったりはしない。
私の情報処理能力は、A地点にいようが、B地点にいようが、
主観的には一定なのである。
ここまでで見てきたように、「主観的には、情報伝達速度の上限は不変である」
ということの本質は、どの地点であれ、その領域の内部で発生して
処理される情報流の速度の上限は同じ、ということであり、
情報の受け手である一点に着目して言えば、
ある一点に流れ込んで来る情報流の速度の上限は一定であるということだ。
この一点を擬人化するならば、
「自分に流れ込んで来る情報の上限は、
この宇宙のどこであっても一定である」ということになる。
- ここで、擬人化のついでに、今、空間のある一点にある「自」が、
人間と同じような意識構造を持っていると仮定して、
その「自」が、一瞬後の未来において、何を感じているか、
ということをイメージしてみよう。
まず、事実として存在するのが、「一瞬前の自b」であろう。
もし、現在までに、何の情報も飛び込んでこなかったとしたら、
「今ここの自分自身、すなわち自a」は、自bと何ら変わることが無い。
最も純粋な形での時間経過、すなわち「自b→自a」という、
無色透明な自覚があるだけであろう。(これを「自のクオリア」と呼ぶ。)
もし、この一瞬間に、「自」に対して何らかの情報αが飛び込んできたとする。
この時、「自b→自a+α」という変移が生じる。
赤の周波数の光が飛び込んでくるとか、
痛みを生じさせるような質量がぶつかってくるとか、
そういう事態が生じたとイメージすれば良い。
この変移が、「自のクオリア」を変調させ、「赤のクオリア」とか
「痛みのクオリア」を生じさせる。
これこそが、究極的な意味での「情報を受け取る」という現象である。
(脳は、素粒子の一つと比較すると、確かにバカでかい物質であるが、
脳が総体として「自のクオリア」を持ち、しかもこれが
宇宙のどこに行っても絶対不変の体験であるということは、
そもそも宇宙の時空がそういう性質であるからこそ担保されるのである。)
- そして、「自分自身の感じ方(自のクオリア)」や、
「赤の感じ方」「痛みの感じ方」は、宇宙のどこに行っても
そこが客観的時間ではどれほど時間の進みが遅かったり速かったりしても、
全く変わらないのである。(色が変わったり、痛みが増減したりはしない。)
これこそが「情報伝達速度上限不変原理」の、最も根源的な意味である。
「主観的時間」は、【私たち】の情報の受け取り方、すなわち
【私たち】の世界の感じ方そのものであり、
それは宇宙のどこに行っても、絶対不変なのだ。
つまり、宇宙の各点での時間の有り方は、【私たち】が決めているのである。
- この宇宙全体を流れる絶対的な時間というものは存在しない。
これは、空間の密度についても同じことが言える。
宇宙の各点で【私たち】が決める局所的な時空の有り方を貼り合わせ、
この宇宙は出来上がっているのである。
- さて、「主観的時間」と「客観的時間」の区別をしっかり理解すれば、
特殊相対性理論も、すんなり理解できるだろう。
今、静止しているAから、Aに向かって動いているBを観測しよう。
Bが、Aへの向きと直角の方向に光Pを発したとする。
実際には、その光Pは、B自体の速度の分だけ、斜めに走る。
だから、Bから光Pが離れていく速度は、本来の光速より小さくなるだろう。
(直角三角形の斜辺よりも、他の辺は必ず小さい。)
Bにとっての光速が遅く見えるということは、
Bにとっての情報伝達速度が遅いということであり、
Bにとっての変化、意味、時間が遅く“見える”ということだ。
これは全て、A地点からBを見た時の「客観的時間」の記述である。
Bの中にいる人にとっての「主観的時間」は、何ら変化していない。
実際、全く同じ理由で、BからAを見ても、Aの時間は遅く見える。
これは「お互い様」の時間の遅れであり、「そう見える」という
見かけ上の時間の遅れである。
AもBも、勿論、同じ「主観的時間」を経験しているのであるが、
お互いに相手の「客観的時間」は遅れているように“見える”のだ。
- ●『一般相対性の場合』(本当の客観的時間の差異)―
静止点Aから見て、Bが一定の速度で動いているような場合、
AとBは「お互い様」の、見かけ上の客観的時間の遅れを観測した。
一方、Bが加速度運動をしている場合(等価原理に照らせば、
高重力場にいる場合と同じだが)、Bの時間は、見かけ上のものではなく、
本当に時間の進みが遅くなる。これは「お互い様」の遅れではなく、
Bが一方的に時間が遅くなるのだ。
しかし、B自身にとっての主観的時間は、相変わらず変わらない。
どんなに凄まじい加速の中にあろうが、
ブラックホールの直ぐそばに居ようが、
Bの近傍の情報伝達速度の上限は不変であり、
Bが体験している「主観的時間」は、いつもと全く変わらない。
- 宇宙の時空という器は、大きなスケールで見れば、
空間としてはどこでも一様で等方である。
これを宇宙原理 (cosmological principle) という。
しかし、局所的に見れば、大質量によって、
空間が縮まったり、時間の進みが遅くなったりする。
良く知られた例が、ブラックホールだ。
- 大質量の周辺の各点においては、重力井戸の中心に向かうように
空間は向きを変えるし(従って、重力が強ければ強いほど、
空間の曲率半径も小さくなる)、北極に集まる緯線のように
空間同士の目が詰まって、あらゆるものが縮こまる。
空間自体が縮こまっているのだから、光の走行距離も短くなる。
重力の影響を受けない遠くのA地点から見たら、
速度不変なはずの光ですら、ゆっくり動いているのだから、
これはもう、時間がゆっくり流れている、と解釈するしか無い。
但しこれは「客観的時間」としてそう見えるのであり、
ブラックホールの近傍のB地点にいる人自身にとっての
「主観的時間」は、いつもと何ら変わらないことは、
ここまで繰り返し述べてきた通りである。
- Bにいる人にとっては、光速度は相変わらず光速度だし、
空間的な前後上下左右もいつも通りだ。
(ところがA地点から見ると、シュヴァルツシルト半径内では
空間が極端に歪んでいて、どの方向に向かっても、その先は
重力井戸の中心に向かっているように見える。
B自身の主観的空間の感覚で、真っ直ぐブラックホールから遠ざかる方向に
動いても、憐れ、その先にあるのはブラックホールの中心なのである。)
- より質量の固まっているところでは、客観的に見て、時間は、
よりゆっくりと流れる。
真空の各点に計算能力が等しいコンピューターが埋まっているとしたら、
高重力場では計算が複雑になるために、あらゆる物理現象を
ゆっくりとしか計算できないかのごとく。
通常の質量であれば、時間の進みには殆ど差は無いが
(だからこそ多少の質量の偏りは、日常生活に支障を及ぼさないのであるが)、
ブラックホールの周囲のような極端な高重力下では、
この差が非常に大きくなるのだ。
- ●『自循論的相対性原理』―
重要なのは、変化であり、意味であり、自のクオリアの連鎖と変調である。
変化量の上限を決めるのが情報伝達速度である。
宇宙のどこに行っても、私たちが宇宙に感じる意味が同じだとしたら、
情報伝達速度の上限は一定でなければならない。
これが、情報伝達速度の上限が一定である「意味」だ。
- つまり、宇宙の物理法則は、情報伝達の有り方によって規定されている。
情報伝達の「受け手」が、宇宙のどこに居ても、
同じクオリアを感じるように調整されている。
ブラックホール等によって、客観的時空は場所によって色々と歪んだりするが、
主観的時空は、宇宙のどこにあっても全く変わらない。
宇宙は、どこにいても、主観の形式を一定に保つように造られているのである。
- 【私たち】は、自循という意味の連鎖を第一原理として、
無限乱雑空間から、この「意味のある」宇宙を切り取っている。
もし、主観的時空において、情報伝達速度に制限が無かったら、
どうなるだろう。
主観は、あらゆる情報を無秩序に、無限に受け取らねばならなくなる。
これは、「自b→自a+α」という式において、自を壊すほどに
αが幾らでも大きくなるということだ。このような世界では、
自のクオリアも、従ってありとあらゆるクオリアも発生しない。
つまり、意味のある世界は生まれないのだ。
【私たち】にとって意味のある情報の生まれ方が一定であることが
当然【私たち】にとっての第一原理であり、
だから「どこにいても、どんな状況でも、【私たち】にとっての
情報伝達速度の上限は、同じ意味世界を共有する限り一定」なのである。
- このように、本質的な普遍性は、【私たち】の主観的時空の有り方を定める
情報伝達速度の上限である。
光は、最も軽い(質量ゼロとされている)ために、
Zitterbewegungすること無く、情報伝達速度の上限で走るため、
光速度が情報伝達速度の上限を代表しているに過ぎない。
質量がゼロで、情報伝達速度の上限で走る粒子はルクシオン(luxon)と呼ばれ、
光子の他にはグルーオンがあり、もし発見されればグラビトンも
質量ゼロのルクシオンとなるはずである。
- それでは、どうして「客観的時空」として見た時、質量の多い場所では
時間の流れがゆっくりになるのだろう。
私たちが、無限乱雑空間から、意味のある世界を切り取り、吸い上げる機序、
すなわち自己無矛盾な時空を作り出すプロセスには、
私たちには知りえないプランク長以下のスケールでの複雑な階層があって、
多くの質量が存在する領域では、
物理世界と情報世界のバランスが取れた時空領域を組み立てるには、
それだけの量の手続きが伴うからではないか。
だから、周囲から見ると、その領域の物理現象は、全て
ゆっくりと進んでいるように見えるのではないか。
- 「この宇宙は、無限乱雑空間から切り取られた、氷山の一角である」
…そして、質量(存在)と変化のある有意味な世界を切り取っている。
これが、星と生命と知性、すなわち「自」という現象を成立させる要件である。
結局のところ、氷山の水面下と水面上、真空の内側と外側を分ける基準とは、
【私たち】という知性の総体が認識できる範囲か否か、ということなのであり、
だから、この基準を作っているのは、他ならぬ【私たち】自身なのである。
- 質量は、時空に存在をもたらし、星と生命と知性、即ち【私たち】という
「自」の形式、すなわち自循を実現する。
宇宙は、自循という情報処理過程を実現できるようにデザインされているのであり、
どの地点においても、「自分にとっての」情報伝達速度の上限は
一定であるような性質を持っている。
A地点とB地点を客観的に比較すると、質量の多寡によって、
空間の歪み方や時間の進み方は違うのであるが、
「自分にとっての自分」つまり主観的時空は、
宇宙のどこに行っても同じであるように、宇宙はデザインされている。
このことの別の言い方で表現すると、
『宇宙とは、普遍的自循が
無限乱雑空間から切り出した意味世界である』
ということになるのである。
- このように、無限乱雑空間から、「質量と変化」に溢れた意味世界としての宇宙を
【私たち】が切り出したのだが、全宇宙に亙り一貫して自己無矛盾であるためには、
ブラックホールのような極端な時空の歪みが生じることも
許容しなければならない。これは、意味世界を獲得した際のツケのようなものだ。
- 数学において、十分に強力な公理系は、その公理では真とも偽とも判断できないような
命題を含んでしまう。これはゲーデルの不完全性定理と呼ばれているが、
その物理版がブラックホールなのだ。
無限乱雑空間から【私たち】を成立させるために、一定のルール
(この宇宙にとっての公理)で宇宙を切り出したところ、
その宇宙の内部に、このルールでは、在るとも無いとも判断できないような領域
(事象の地平線の向こう側)を含んでしまったわけだ。
- 「質量」は、時空に存在を与え、星や生命や知性を生み出し、
一方、その「知性」は、質量と変化を、宇宙のどこにいても、
その情報伝達速度の上限が一定であるように認識する。
この要請(第一原理)さえ守られていれば、客観的な神の視点からA地点とB地点を比較して、
空間の歪み方や時間の進み方が違っていたとしても
(それは一瞬、時空が崩壊するほどの大問題のようにも感じられるかも知れないが)、
実は大した問題ではないのだ。
何故なら、知性は、普遍的自循を核として、
宇宙のどこにいても、「今ここ」から、“同じように宇宙を体験できる”のだから。
- 物理世界と情報世界の交差点に生命がある、と言っても
なんだかピンと来ないかも知れない。しかし、
生命の本質をオートポイエーシスと捉えて良いなら、
生命とは、「物理世界からの情報の再生」と、
「情報世界からの物質の再生」のサイクルなのだから、
正に情報と物質の自己循環と言って良いはずだ。
◎免疫的自己
免疫システムにはB細胞、T細胞などが含まれる。
複雑精妙な免疫機能は、見事に自己と非自己を
認識仕分けている。例えば、成熟したT細胞が外来のウィルスを破壊し、
自己の細胞をほぼ間違いなく攻撃しないという様子は、T細胞が
「自己を認識している」と形容される。
脳が考えている「脳神経的自己」と、
細菌などを非自己と認識して攻撃する免疫系が作る「免疫的自己」では、
どちらが生命にとって本質的だろうか?
生物の進化の過程では、脳より先に免疫系があった。
他人の脳を移植すれば、免疫系は脳を異物として攻撃し破壊する。
普段は「脳味噌で考えている自己」が本質的だと考えがちだが、
自分というものの、より本質的な境界は、免疫的自己によって規定されている、
と考える方が自然だろう。
脳は「人間らしい高度な自己という意識」の解明の中心にあることは
間違いない。しかし、脳だけで「自己」という概念の全てを物語る、
という極端な脳産教理に走らぬよう、私が私であると感じる大切な感覚を
支えるこの免疫的自己という考え方を常に視野に入れておく必要がある。
◎生命と無意識と意識
- 私達の身体を構成する60兆の細胞は数年でスッカリ入れ替わってしまう。
筋肉は七ヶ月、血液は三ヶ月、皮膚は一ヶ月で、全ての細胞が新品になる。
これは物凄い勢いである。例えば血液細胞は
体内で「たった1秒の間に」350万個も死に、また、補給されている。
骨ですら2~3年で全ての細胞は入れ替わるし、
私達の意識を内包する脳も、一つ一つの脳細胞の単位で見れば、
一ヶ月で40%が、一年で全てが新品の細胞になる。
だから、身体というのは、ずっと不変で存在するものというよりも、
激しい入れ替わりの中で、一定の形をなんとか維持しているもの、
言わば激流の中で同じ形状を維持している渦のような“現象”だ、
と言った方が実態に合っている。
分子生物学的に見ても、
個々の細胞を形作るタンパク質同士というのは、
ガッチリ結合しているのではなく、
絶妙のバランスで強過ぎず緩過ぎず寄り添っている、
と言った方が適切である。
- 生命は、これほどまでに猛烈な勢いで古い細胞を排出し、
食物を摂取し、新しい細胞を形成し続け、
「エントロピー増大の法則に従って自分が壊れてしまうこと」
を防いでいる。
実際、生命活動が停止した死体には、
即座にエントロピー増大の法則が襲い掛かり、
あっという間に腐敗し、形状がぼやけ、消えてしまう。
- 「私が、同じ私であり続けている」という感覚、
すなわち「意識」を運んでいる
この「身体」という“現象”は、
物理的には1秒たりとも同じ状態ではない。
無意識層下のあらゆる生命活動は、
疾風怒濤の如く入れ替わる細胞を巧みに調整して
身体が一個の身体であり続けるべく、
毎秒、気の遠くなるような仕事をしている。
それら全ての莫大な活動の共通部分が、
無意識の内に人間の複雑・巨大な脳に伝わり続け、
情報として抽象化され、蓄積し、精錬され、
大脳の一番端っこの前頭葉に、
「自分」という最も純粋な概念(シンボル)を生み出した。
人間に何らかの情報を入力すると、何らかの情報が出力されてくるが、
その折り返し地点にあるのが、脳の部位で言えば前頭葉、
意味論的に言えば「自分」という概念、ということになる。
- 「意識」などというものは、無意識層以下の身体の全てに比べれば
氷山の一角とすら呼べないほどの小さな小さな“現象”である。
しかし、情報世界内に、「自分」という
唯一無二の絶対的に不動な概念を明確に持つに至ることで、
意味世界における確かな折り返し地点、絶対に崩れない足場を得て、
自分で自分の人生の意味を考え、
物理法則の奴隷としての機械ではなく、
自分の自由意志で行動を選択する、
という構造を勝ち取れたのである。
それほど大事で画期的な「自分」という概念も、
その源泉は「身体」にある。
無意識層下の莫大な情報処理や、
数年ですっかり細胞を入れ替えながらも自分であり続けている
「身体」のありようと切り離して、
意識とかクオリアという現象だけを取り出して考えたり、
ましてや意識のありようだけをコンピューターで
シミュレーションしようとする試みは、
おそらく、出発点からして間違っている。
- 物質としての構造・境界である身体こそが、
「自己」という抽象概念が
情報世界の中で確固たるものとして自然発生する根拠なのだし、
身体自身が自己保存を目標としているからこそ、
抽象概念としての「自己」を保存するための
様々な思考や判断を行うわけである。
(永遠の命は、思考や判断を行う必要性自体を失ってしまう。)
- 意識以前の層(下等動物の脳の機能とか、無意識層の働き、
と言っても良い)において、
あらゆる情報にべったり貼り付いている
「体」と、その「生きたい」「死にたくない」という反応が、
情報世界において抽象化され、
不動の地位を得た姿が「自己」であり「意識」である。
だから、コンピューターに意識を持たせようと思ったら、
結局のところ、身体性と本能まで
丸ごとシミュレーションする必要があり、
脳だけ取り出してその挙動をなぞっても意識は発生しない。
- こう考えてみると、チューリングテストをパスするような
「意識」をシミュレーションできるようになるには、
先に「人工生命」のシミュレーションが必要なようであり、
生命の問題を飛び越えて
知的存在をコンピューター上に実現するというのは
無理なようにも思われる。
◎自己―生命一般―宇宙
- 自己という数学的な存在が全ての根源である。
自己は必ず、自己自身を内包する、いわば“生命”とでも呼ぶべき現象を
自己のすぐ外側の入れ物として
見出すことになるだろう。
そして、必然的に、その安定性を支える他の生命や、
生命群を包含する“宇宙”なる現象をも見出すことになるだろう。
それは、私達が今見ている宇宙とは、全く違うものかも知れないが。
- もし、自己という数学的な存在が無かったら、
“生命”も“宇宙”も、全ては絵空事であり、雑音ですら無い。
あらゆる可能性を含んだ無限に乱雑な空間の中で、
ただ単に、自己という数学的な存在たちによって彩られた領域を、
私達は単に宇宙とか世界などと名付けているのである。
- それは、自己責任であろうか。自己完結であろうか。
“ループ”という、「同じ位置」と「違う時刻」、
すなわち『自己』。そこから全ては形作られる。
だからこそ、『自己』という数学的な存在こそが、
全ての根源だと言えるのである。
|
脳とクオリア
|
|
脳はどのように特別か? クオリアはどうやって発生するのか?
|
脳神経系は、意識の上での自己を持つ最も複雑な(超)システムであり、
基本的な構造は遺伝的に決定されているが、脳の「自己」の多くの部分は
後成的に生成される。
脳や免疫系は生物の目的からすると、ここまで発達する必要を認められない。
自己目的的に発達した結果として、むしろ自己矛盾を抱える結果となっている
という見方もある。
◎脳がいかに「自分という感じ」を生み出しているか
(1) 脳内で生じている「自分という感じ」は、
有限容積の脳内での電気信号の往来と自己参照性(フィードバック
回路)によって生じる、「うなり」「残響」「差異の認識」の総体である。
(2) 電位や血流の分布と密接に関係するが、コンピュータのメモリの
ビットパターンだけを見てもそれが何を意味するか分からないように、
電位や血流から推測される残響や差異の認識がどのような『自分という感じ』
に結びついているのかは分析的・局所的理論の積み上げでは分からない。
(3) この「うなり」「残響」のような『自分という感じ』を維持することで、
自己認識や時間順序に沿った認識、更にはこれを未来へ外挿することに
よる計画性を得た結果、人間は生存競争において有利となり、繁栄した。
(『クオリア』は、このような『私という感覚』の一部分である。)
(4) この「うなり」「残響」はフラクタルな脳の記憶システムに非局所的
に格納され、また、非局所的な「うなり」として取り出され得る。
このように非局所的な総体が『自分という感じ』を記述する。
(5) 物理的な過程と『自分という感じ』という心的な過程は密接に関係している、
とも言えるし、同じ現象の違う側面(断面)での説明だとも言える。
どちらかがどちらかを説明し切るという従属関係には無い。
◎脳の中で量子力学で解明された仕組みは使われているか
脳内の複雑な化学反応の連鎖や、まだ解明されていない大域的な
電磁気作用などの可能性も含み、脳は古典物理学の範囲で
十分に複雑・神秘的であり、意識の座に相応しい。
量子脳理論のように、量子力学的な制御を脳が獲得している、
と考えなければならない積極的な理由は今のところ無い。
しかし、ここでは、脳が高度な意識を持つに至ったのは、
量子力学的な仕組みを使っているからかも知れない、という立場で
検討をしてみる。
観測行為とは、ある“可能性の状態”を作ろうとすることであり、
更に、脳内の思考においてはその範囲を絞って、かなりの恣意性をもって
崩壊の落ちどころをコントロールできているのではないか。
※脳の中に作られた仮想的な「現実的世界Simulator」
(1) 脳は、進化の過程で、特に手で道具を用いる短時間の運動の予測から、
生活や都市を設計する長期の計画力まで徐々に手に入れてきた。
(2) 脳の松果体に、この世界のモデルとしてのデカルト劇場がある、
という程単純ではなにせよ、進化した脳が数百億の脳細胞の電磁気学的
ネットーワークの他に、更に、微細管の「量子のコヒーレンス効果」をも
利用して、高度な判断(…や愚にもつかない気まぐれ)を生み出すように
なったのかも知れない。
※可能性の状態をいじり、不可思議な崩壊のプロセスを経て
脳内世界での「決定」が行われる。電気信号の脳内ネットワーク
だけでは説明できない神秘的なプロセスがある。
イメージトレーニングに代表されるように、
脳内に現実世界のプロトタイプを構築し、
“可能性の状態”の方をいじることは、うまく動き、
より良く生き残るのに非常に大きな貢献をする。
そのために、“自己”というものを持たされてしまい、
自分にとっての自分の役割が肥大したような錯覚を持ち、
死ぬことを必要以上に恐れるようになり、
自分が自分であることを持て余すようになった存在を人間だとすれば、
DNAは進化の過程で相当罪作りなことをしているという感じもする。
※我々の脳の中で量子的なトリックが利用されているか否かはさておき、
この世の中は事実、量子的なトリックに満ちており、少なくとも我々は
それに気付き、真の意味は分からなくとも大いにこれを利用している
のかも知れない。
◎自由意志
私たちが「自由意志」に期待していることは次のようなものでろう。
(a)他者にコントロールされていないこと
(b)再現性が無いこと、予め決まっていないこと
(c)自分で自分が判断したと感じていること
とりあえず、(a)については、霊的な遠隔操作を除外すれば良い。
(b)は、脳がスバ抜けて複雑なため実践的には再現不可能であり、
原理的にも不確定性原理によって再現や予言は不可能であろう。
私たちの一回一回の判断は、私独自のものであり、
私だけがその全ての直接的根拠であると言える。
しかし、これだけならば、入出力を持つ、ある程度
複雑精巧な機械の全てに当てはまる。
別格に難しいのが(c)で、これは「自のクオリア」無しには得られない。
実は、これこそが自由意志を特別なものにしている。
人類が知る、ありとあらゆる構造物のうち、 (a)~(c)の全てを満たすものは、
今のところ、人間の脳だけであろう。(現有のコンピューターでは、
不確定性とかを持ち出す以前の問題で全く力不足。)
・自由意志を持ったコンピューターは実現可能であろう。
それは上記(a)~(c)の条件を満たしていれば良い。
但し、人間と同じようなクオリアを持てるとは限らない。
人間とコミュニケーション可能かどうかも分からない。
おそらく地球規模のコンピューターをフル稼働させても、
かなり希薄で幼稚な自意識や自由意志しか生まれないだろう。
※もしディジタルコンピューター内に高度な自意識が発生したとして、「彼」が
自分の思考が決定論的であり(b)を満たさないと嘆くようなことがあったら、
演算プロセスに適当に量子サイコロの出力を重畳してあげればよかろう。
・人間である「この私」の自由意志を再現する
コンピューターは、実現不可能であろう。
そのためには、私の意識と生命現象、私が知覚できる
全ての物理現象を再現する必要があるが、不確定性をも
計算することは不可能なので、全く同じにはなりえない。
◎進化と自意識
生存競争に有利でも、進化が一足飛びに自意識を生み出した
とは思えない。生命が神経系を持ち、シナプスが可塑性を
獲得してから、段階的に自意識は育まれてきたはずである。
(1) 記憶力…可塑性による直接的な能力。生存に有利なことを
繰り返し行える可能性が高まる。
(2) 抽象化力…神経回路網を多段化することで、多くの個別
事態を一括りに出来る能力。未知の類似現象への対応力の強化。
(3) 比較能力…神経回路網に反回性回路(フィードバック回路)
を持つことで、複雑な演算が可能になる。過去と今を比較して
同一性や差異を検出し、判断のメリハリを強めることが出来る。
(4) 否定能力…以上を総合して「~でない」という抽象概念を
扱えるようになる。経験しているものでない事、ゼロとか無限
といった概念を扱えることで、思考空間が爆発的に広がる。
(5) 時空概念…「あらゆる見たり聞いたりしている対象でない
もの(=空間的ここ)」「あらゆる覚えている記憶でない
もの(=時間的いま)」との対比で時空構造を把握し、距離とか
過去・現在・未来を扱えるようになる。
(6) 自意識…あらゆる入出力における不動点「いま・ここ」つまり
自分の居場所が確定し、自意識の根拠になる。「自のクオリア」は
「いま・ここ」を確認し続ける動的平衡によって脳内に生じる。
自己中心の情報世界で高度なシミュレーションが可能になる。
脳の拡大に伴い、(1)→(6)の順で脳は新たな機能を獲得し、その
どの段階も生存競争に有利だったため、自然淘汰を勝ち抜き、結果
として、この「自分が自分である感じ」すなわち自意識という
不可思議で神秘的な現象を得るに至ったのである。
- CDやDVDやコンピューターと違って、人間の記憶というものは、
どこかに静的に記録されているものではない。つまり、どこにも無い。
人間の脳をトコトン解剖しても、
どこかに「単語」や「恋人の顔の映像」や「フランス革命の年号」が
カタチとして記録されている場所を見つけることは出来ない。
脳を解剖すると出てくるのは、
神経網から成る演算装置のみであり、
どこにも記憶装置など無い。
実際のところ、「何かを記憶する」ということは、
実は「何らかの入力に対して、
『何かを記憶している』ように見えるような
出力をもたらすような演算回路に書き換える」
ということである。
これを脳神経回路の可塑性と言ったりするが、
ともかく大事なことは、生命にとっての記憶というものは、
何らかの静的な実体ではなくて、
流れの中で浮かび上がってくる、
「存在に還元できないもの」である、ということだ。
脳の『記憶』の全てを静的に取り出すことは不可能であろう。
脳に対する可能な限りのあらゆる入力を試して、
そのそれぞれについて、
どのような記憶があるように見えるか、ということを
延々と記述することしか出来ないのだ。
ともかく、『記憶』というものは、どこにもない。
同じように、『情報』というものも、どこにもない。
- 脳には、静的な記憶が格納されているわけではない。
「思い出す」という動的な思考をしているだけである。
「過去を思い出す」ことも「現在を知覚する」ことも
「未来を思い描く」ことも、
脳神経回路にとっては同じ機能の結果に過ぎない。
脳内の過去・現在・未来は、
知識が捏造した線形時間に沿った、便宜上の区分に過ぎない。
- 睡眠とは何であろうか。一般には、脳を休めるとか、
記憶を整理するため、と言われるが、果たしてそうだろうか。
ノンレム睡眠時には「遅い揺らぎ」「自発発火」「神経ノイズ」と
呼ばれるような、脳全体に亙る活動が行われている。
入力を処理したり、出力を制御したり、思い出したり思考したり、
といった情報処理はせず、相当のエネルギーを消費しながら
脳の全域で自発変化を行っている。これは一体、何のためだろうか。
これこそが、神経系における「自」の確認なのだ。
覚醒時は、脳はひっきりなしに外界とやりとりし、
色々な影響を受ける。
睡眠時には、全身の神経およびその統合交換器である脳は、
ゆっくりと全身で、一見ノイズのような情報を同期させる。
…「自分とは何であるか」を忘れないように…。
それはヘブの法則により、シナプスの結合度を高める。
外界も記憶もオフにして、自分の中に満ちて反響する、
純粋に「自」を表す固有ノイズが、全身に染み渡り、
シナプスに再記録される。
そして、朝、覚醒する。この時、全身の神経細胞系は、
「自分が自分であること」に関する調整を終えており、
外界から流れ込んでくる情報流の全てを、
「それらは自分にとって何であるか」というように
変調させることができるのである。
もしも、睡眠によるこのような調整が無ければ、
生物は入力に対して機械的に反応するだけの情報処理器になってしまう。
私達は、睡眠があるからこそ、「自」を強固に保つことが出来る。
睡眠とは、外界とのやりとりのスイッチを切って、
「純粋な自己確認を行う」ための儀式
なのである。
- クオリアの発生
- クオリアというと、「赤の赤いという感じ」
「ピーという音のピーという感じ」のように説明されるが、
これらはクオリアという現象の枝葉末節に過ぎない。
敢えて言えば、真正面から取り組むべきなのは、
「私の私という感じ」つまり「自のクオリア」のみである。
「自のクオリア」の構造を理解すれば、他のクオリアは
その偏差・変調として副次的に理解されよう。
-
「自のクオリア」とは、「自bの、自aであるという感じ」のことである。
つまり、観察対象として捉えうる自bに対して、
決して観察対象(見られる側)とは成り得ない主体(見る側)の自aを
思い描いてしまうという、思考(情報処理)の一形態である。
自aは、【今ここ】に絶対的に位置づけられる。
自bは、あくまでも対象(見られる側)であるから、【過去】に属する。
自bは、人間の高度な脳が持つ情報処理のクセで抽象化され、自aを想起しようとする。
しかし、想起された瞬間に、それは対象であるから、【過去】に押し戻され、
先ほどまでの自bと混ぜ合わさって、新たなる自bとなる。
いくら自aを捉えようとしても、捉えようとしたその瞬間には、
それは【過去】の自bに押し戻されてしまうのだから、
自aは永遠に捉えることは出来ない。
脳の情報処理のクセで想定した自aに辿り着こうと、
脳は睡眠中ですら思考を続けているのであるが、
捉えたと思った瞬間に、それは自bに変質してしまっている。
この永遠の連鎖を【時間】と言う。
そして、この【時間】に沿った、永続的な自a→自bという参照構造を
「(純粋な)自意識」と呼ぶのであり、自bから自aを探し当てようとする全脳的な
思考活動のことを「自のクオリア」と呼ぶのである。
(このように、意識を支える【時間】を、原型時間と呼ぼう。
これとは別に、【過去】における思考対象を、便宜的に
「想起(過去)」「知覚(現在)」「夢想(未来)」と分類し、
数直線化したものを、線形時間と呼ぼう。
原型時間には【今ここ】と【過去】の離散的な2時刻しか無いが、
線形時間は、主体と切り離されて、無限の過去から無限の未来への
連続した時間概念を形成する。)
-
脳神経回路の99.99%は反回性(フィードバック)回路である。だから、
脳の活動の殆ど全ては、脳自身のことを考えることに充てられている。
脳はそれ全体が、自bから自aを探し当てようとする情報処理器であり、
「自のクオリア」とは、自bをもとに自aについて考えようとし続けることなのだ。
「赤の赤い感じ」などのクオリアは、残り0.01%以下の視覚入力情報が
「自のクオリア」に与えた、擾乱・変調・偏差に過ぎない。
自bを足がかりに、自aを探し当てようとする思考そのものは、
【過去】から【今ここ】へ向かうものだから、
線形時間に当てはめれば、「夢想」(未来への思考)の原型でもある。
自bは、いわば意識のスクリーンに写った自aの影であり、
だから当然、自aは求めれば(振り向けば)把握できると感じてしまう。
しかし、把握したと思った瞬間に、それは自bに化けてしまう。
高度な人間の脳のクセによって、永遠に求められることになってしまった
自b→自aという思考(すなわち自のクオリア)は、しかし
原型時間という枠組みをも作り出した。
これが基になって、線形時間が捏造されたことは想像に難くない。
どのような高度な情報処理を行うコンピューターであっても、
ただ入力情報を処理して出力情報に伝達するだけの仕組みには、
自覚も時間感覚も伴わないであろう。
たとえ生命であっても、自b→自aという
非常に抽象的で高度な思考にチャレンジし続けるような
複雑な回路を持たなければ、やはり自覚も時間感覚も持てないであろう。
人間の脳は、その複雑で高度な回路の総力を挙げて、
無意識に、いつも、脳自身のことを考えている。
これがベースにあって、そのことに意識が向いた時に、
「自のクオリア」が明確に自覚されるのだ。
-
結局、「意識のハードプロブレム」と呼ばれる問題も、
そう難しいことを言っているのでは無い。
機能的意識に対する現象的意識とは、まさに自aに向けて考える、
という全脳的形而上学的思考に還元される。
そして、まさにこの自b→自aという思考運動(自循)こそが原型時間を形成し、
私達は知覚された物理世界を時空の枠組みで理解するのである。
(私達は物理学の法則に従う生命であるが、たまたま脳内に自循を発生し、
物理法則を再発見している。この意味で物理は意識の形式を超えることは
決してできず、物理と意識は対等である。
この、物理世界と情報世界の対等性は、世界の内部から維持されるのであり、
外部から与えられたものではない。なぜ私達は、そのように奇跡的に
バランスの取れた世界にいるのか、と問われたら、これはもう
偶然である、としか答えようがない。
バランスの崩れた世界は幾らでも可能だ。但しそれを「世界」として
認識するものがいないという意味では、それは世界ではない。)
-
「意識のハードプロブレム」というと直ぐに取り沙汰されるのが
「哲学的ゾンビ」である。これは、受け答えは普通の人間と全く同じだが
クオリアという体験を持たない仮想的な存在のことである。
この定義のみを見れば「哲学的ゾンビ」は存在可能であろう。
思考回路のアーキテクチャ自体が総力を挙げて自分自身を継続的に
考え続けるような仕組みを持つことが「自のクオリア」の条件だが、
別のアーキテクチャ、たとえば膨大な演算と知識ベースを用いて、
上手に意識体験を真似るコンピューターが出来上がることを
否定はしない。つまり、人間そっくりの応対をする(チューリングテストを
パスする)ような、クオリア体験を持たないシステムは、構築可能であろう。
もしかすると、自b→自aという「自のクオリア」をもシミュレーションした
自意識を持つシステムも、遠い将来には構築できるかも知れない。
しかし、同じ肉体構造を持った友人が、
哲学的ゾンビかも知れないと疑うのはナンセンスであろう。
-
「マリーの部屋」という思考実験は、
生まれた時から白黒の世界しか体験していないが、
色に関する完璧な知識を持つマリーという少女の物語だ。
マリーが初めて色彩溢れる世界を体験したら、
知識以上の新たな体験をするだろうか、という問いだが、これはYesであろう。
「自のクオリア」に対して、視覚から赤い色が入ってきた時の
擾乱・変調・偏差の感覚(すなわち「赤のクオリア」)は、
これまでの記憶に無いものだからだ。
もしかすると、色に関する「完璧な知識」を持つほどの彼女であれば、
脳内に偶然「赤のクオリア」を捏造できるかも知れない。
しかし、視覚体験無しに、視覚入力に近い部分の脳神経回路網まで
書き換えるような思考は、現実的には、もしくは機能的に、不可能であろう。
-
究極の意味で、「私a」は語りえない。むしろ、それは
人間の脳(もしくは抽象化力を持つ高度に自己言及的な情報処理器)が
自動的に追い求めてしまう幻影に過ぎないと言っても良い。
リアルな意識体験は、私bから私aを追い求めるという「自のクオリア」なる、
動的で継続的な思考運動そのものにある。
(これは、時間・空間よりも速度の方がより本質的である、という
相対性理論的直観とも結び付く。)
この「自のクオリア」自体は、無色透明・無味乾燥な
抽象思考の連鎖に過ぎないが、
このように準備された「自意識の場」に、
視覚・聴覚・触覚などの入力情報が入り込むことで、
自のクオリアは変調され、
さまざまな種類のクオリアが自覚されることになるのである。
- 【神経細胞の機能】
神経細胞(neuron)は、以下の3つの部分から構成される。
- 本体の細胞体
- 複雑に枝分かれした樹状突起
(他の神経細胞からの入力信号の受信部)
- 本体から一本だけ出て末端で多数に枝分かれする軸索
(他の神経細胞に信号を出力する送信部)
神経細胞は、多くの入力信号を重み付けして総和し、
信号を出力するか否かを決める、
多入力一出力の情報処理素子であると言える。
- 【神経回路の基本動作】
個々の神経細胞は、このような単純な機能しか持たないが、
幾つかが組み合わさることによって、多彩で高度な機能を実現する。
例えば、入力の特定の空間パターンにのみ反応したり、
入力刺激の特定の時間間隔や速度に反応したりする
神経回路網を構成することが可能である。
ミラーニューロン(Mirror neuron)は、
「自らの行動認識」と、
「他の同種個体が同じ行動を行っているのを観測した時」とで、
同じように活動電位を発生させる神経細胞であり、
脳内情報世界への他者性の取り込みや、
他者への共感の形成、
また、他者の身振り等の理解から言語獲得に繋がる
重要な機能を担っていると考えられている。
このように、神経細胞は、多段に構成していくことで、
極めて高度な機能を実現できるのである。
- 【神経回路の学習機能】
神経回路の今ひとつの特徴は、学習機能である。
2つの神経細胞A、Bを考えよう。
Aの軸索からBの樹状突起に接続するシナプス(Synapse)は、
特定の条件で強化される。
つまり、A→Bへの情報が伝わりやすくなる。
その条件とは、A→Bの順番で、
ほぼ同時に活動電位が発生(スパイク)することである。
これを「ヘブの法則」と言う。
Bの方が直前にスパイクしてしまうと、
逆に、A→B間のシナプスの結合強度は弱まってしまう。
神経細胞A、Bを擬人化して、この様子を見てみよう。
Aがスパイクした時に、
Bが「そうそう、オレも丁度スパイクするところだったんだよ」
という場合は、結合強度が強まる。
もしかすると、AとBは、
別々の理由でほぼ同時にスパイクしただけかも知れないが、
このように「気が合う」と、
A→Bへのダイレクト・パスが強化されるのである。
一方、Aがスパイクした時に、
Bが「遅いよ、オレは今さっきスパイクしちまったよ」
という場合は、結合強度は弱まる。
BがスパイクするためにAからの信号はいらなかったわけで、
こういう「ワンテンポ遅い奴」は、
非効率な奴だ判断され、疎遠にされてしまうのである。
つまり、「ヘブの法則」は、複雑に絡み合った神経回路が
さまざまな偶然を含みながらスパイクしている状況の中で、
繰り返しA→Bといった順序で発火するパターンを持つ部分を発見して、
その結合を強化する。
こうして、入力から出力へ繋がる、より効率的な回路だけを残し、
継続的な最適化を実現するのである。
- 【睡眠による自己の定着】
ところで、脳は睡眠中も活発に活動している。
この時、視覚情報の入力や、筋肉などへの出力は、ほぼ全く無いので、
全身の神経系、特に脳の中で、信号がグルグルと回っている状態だと言える。
この時も勿論「ヘブの法則」は働いている。
脳の中を静かにノイズが駆け巡り、あらゆる情報伝達経路が試される。
「気の合う奴」からの経路は強化され、
「ワンテンポ遅い奴」からの経路は閉じていく。
こうして、脳は、脳が脳自身を考える経路を最適化するのだ。
一晩眠ると記憶が定着するというが、実際、昼間に体験したことは、
睡眠中のこの自己最適化作業の中で、
脳が脳自身を考える情報循環の連鎖の中に定着していくだろう。
つまり、一本の主観時間の繋がりの中に組み込まれるのである。
(強いトラウマは、主観時間に組み込まれずに遊離し、
思い出すことが出来ない記憶として、無意識的な強迫観念になりうる。
カウンセラーの誘導による自由連想法で、主観時間との繋がりを回復すると、
この手のトラウマは解消されることがある。)
睡眠は、脳の純粋な自己確認の時間であり、
言わば脳神経回路の最新状態を最適化し、新たな神経回路に焼き込む、
つまり脳に脳自身をハッキリと書き込む儀式なのである。
こうして、脳は、外界から得られた知識を含めて、
常に自分自身を更新し、断片的な体験のツギハギではなく
滑らかに連結して最適化された一体である脳内情報世界の基盤を維持する。
この、最適に効率化された脳内情報循環の動的平衡状態が、
「自のクオリア」、つまり「自分が自分である感じ」の正体である。
- 【覚醒時の自意識】
脳は、入出力を遮断した睡眠状態において、
脳自身を考え続ける基底状態としての「自のクオリア」を確立する。
覚醒時には、ここに様々な変調が齎される。
絶えず視覚、聴覚、触覚からの情報が入力されてくる。
新しい入力と出力のパターンが繰り返し発生すると、
「ヘブの法則」により、
新たな入力→出力の結合強化が起こるかも知れない。
睡眠時に最適化された「自のクオリア」は、
このようにして外界とのやり取りで乱され、変調され、
自己に粗く刻み込まれた状態になる。
そして、睡眠時に、再び最適化が行われ、
滑らかに自己に組み込まれるのである。
さて、基底状態である「自のクオリア」は、覚醒時においても
無意識の奥底でずっと続いている。
視覚や聴覚を遮断し、脳内にモノローグすら響いていない、
無色透明・無味無臭な自己参照の連鎖に相当する
信号の循環が継続している。
例えばここに、視覚情報が入ってきたら、何が起こるだろうか。
最適化されたはずの循環は、乱されるであろう。
何か赤いものを見た時、私たちの脳は、
単なる「赤い」という情報を受け取るだけの電気回路では無い。
脳内に満たされた「自のクオリア」なる電気信号の循環への干渉、
もしくは外部擾乱として、この信号を認識するのである。
この時、無色透明だった「自のクオリア」が、言わば“意識”される。
「赤い」という入力によって、「自のクオリア」が、
最適な循環状態から歪むことで、その弾力から、
「あぁ、自のクオリアがあったんだ」と気付くのである。
殆ど無意識ではあるが、私たちは、リンゴを見た時に、
リンゴという対象物の知覚と、その知覚によって歪められた自分を、
同時に感じている。
あるメロディーを聴いた時に、
そのメロディーの知覚と、その知覚によって変調された自分を、
同時に感じている。
作用反作用の法則のように、どんな入力を受け取っても、
それに反発する「自のクオリア」を(殆ど無意識に)感じる。
(現時点では「反発する」というようなイメージで述べているが、
将来は、この具体的な物理的挙動が解明されるであろう。
おそらく、最適に調整された自のクオリアが循環している状態では
反応しないように調整されている神経細胞が、
その循環が乱されることでスパイクする、
言わば「擾乱検知ニューロン」のような形で発見されるであろう。)
景色を見れば、その景色ではない、
景色を押し付けられて反発している「自分」を感じる。
美味しいものを食べれば、その味ではない、
味を押し付けられて反発している「自分」を感じる。
つまり、私たちは、覚醒時には、
あらゆる知覚された対象だけではなく、それでは無いものとして、
何かを感じ続けているのである。
これこそが「自意識」の正体である。
私たちはそれぞれ、個別の脳と身体を持ち、個別の体験を経て、
個々人に特有の「自のクオリア」の動的平衡状態を持っている。
感覚クオリア、例えば「赤のクオリア=赤の赤い感じ」とは、
この、各人各様の「自のクオリア」が、
赤いという視覚情報の入力に対してどう歪むか、
という変調の様態のことであり、
それは個々人によって異なるものだろう。
あなたの赤のクオリアと、私の赤のクオリアが同じである保証は無い。
なぜなら、あなたの自のクオリアと、私の自のクオリアは、
(身体も経験も違うので)同じではないからである。
- 【コトとしての自意識】
私たちが覚醒時に通常「自意識」と思っているものは、
言わば知覚情報への反作用の総体であろう。
なぜそのような反作用が生じるのかといえば、
脳は常に脳自身のことを考え、
特に睡眠時において、その自己循環が最適化され、
無色透明の基盤を形成しているからなのだ。
このようにして維持される動的平衡の連鎖が、
あらゆる知覚情報を「自己という一本の繋がり」に関連付けながら、
エピソード(体験)として記憶していく。
そして、記憶されたものは、再度連想して思い出されることにより、
追体験(再体験)を私たちに与えてくる。
(この意味で「思い出す」というのは知覚の一種であり、
やはり「自のクオリア」に変調を齎す、自己発生的な入力である。
極めて大雑把に言えば、「見る」ことと「思い出す」ことには、
本質的な違いは無い。)
(レム睡眠時にも脳内で「思い出す」という回路が働くことはあり、
最適化中の「自のクオリア」に影響を与えることがあるだろう。
これが「夢」であろう。)
一旦、記憶として対象化された知覚は、
既に「モノ的」である。
一方、知覚や想起が動的平衡状態にある「自のクオリア」に影響を及ぼす時、
まさにこの動的な関わり合い、変調、反作用それ自体、
つまり体験が「コト的」である。
自意識をモノ的に捉えようと思っても無理である。
自意識は「自のクオリア」という動的平衡を基盤とする
コト的事態だからだ。
自意識とは、最適化を図り続ける「自のクオリア」と、
これを乱す入出力信号との間の緊張関係の持続そのものなのである。
- 【歪自検知ニューロン】
脳は睡眠中も活発に作動して、「ヘブの法則」により、
脳自身のことを最もうまくクルクルと考え続けられるように
脳神経回路網を調整する。
最適に調整が終わった動的平衡状態で脳内を巡る脳波を
『基底自己循環信号』と呼ぼう。
この循環信号は、覚醒時においても、
無意識の奥底で持続しているが、
何かを見たり聴いたりすることによる入力信号によって
どんどん歪んで変調される。
ここで、この歪みを検知してスパイクする神経細胞がある、
という仮説を置こう。
仮にこれを『歪自検知ニューロン』と命名しておく。
このニューロンは、睡眠中に基底自己循環信号に同期して調整され、
理想的な動的平衡状態では発火することが無い。
ところが、覚醒時に外界から様々な情報が到来して
基底自己循環信号に歪みが生じると、
歪自検知ニューロンは、その歪みの大きさに応じて
活動電位になる(スパイクする)という機能を持つ。
この仮想の神経細胞の役割は、
基底自己循環信号の歪みを元に戻すように働いて
自我の安定化を図ったり、
知覚の反作用としての自意識の元を為したり、
自我を乱されることによる感情の原信号を発したりすることである。
基底自己循環信号の形成と、この変調に感応する
歪自検知ニューロンの組み合わせによって、
脳内に、能動的に「自己」を知覚・維持するシステムが
出来上がってる、と考えるのである。
とにもかくにも「自意識」なる現象は、
現に存在しているのだし、
明瞭な一対一対応ではなくとも、これに対応する
何らかの物理現象があるはずだ。
一方で、個々の脳神経細胞に出来ることは然して多くない。
霊魂や量子脳仮説を持ち出さずに自意識を説明しようとすれば、
とにもかくにも何らかの持続と、
自意識を主題的に捉える際の仕掛けが無ければ
何も始まらないであろう。
そのような観点からは、脳内に
「基底自己循環信号」と「歪自検知ニューロン」が存在する、
という仮説は、確信的推測に部類される。
- 【自のクオリア】
基底自己循環信号それ自身は、外部との入出力が無い場合に
脳内を静かに巡る電気信号でしかなく、
これ自身が直接「自のクオリア」(自分が自分である感じ)を
形成しているわけではない。
また、現実の脳内においては、この基底自己循環信号それ自身も、
全く理想的な動的平衡にあるわけではなく、
ゆらぎながら、刻々と変化し、その痕跡を記憶回路に残していく。
基底自己循環信号が残した痕跡自身が、
基底自己循環信号に与える影響、
すなわち自分の残像が自分に与える歪みが、
自のクオリア(自分が自分である感じ)である。
(「基底自己循環信号」こそが、
永遠に対象としては捉えられない無味無臭な自aの正体である。
これが記録されて対象化された短期記憶が自bである。
自bが自aに影響を与えるというフィードバックが
「自のクオリア」ということになる。
自意識の根源にあるのは、この、自aと自bの緊張関係である。)
(勿論、外来の視覚情報、例えば赤色の周波数を持つ光線に由来する
入力信号が自aに与える影響は「赤のクオリア」であり、
このような感覚クオリアは、「自のクオリア」よりも
明瞭かつ主題的に捉えられるものである。)
- 【自と時空】
さて、自aと自bの関係が、主観時間の起源となっていることは
容易に想像できるであろう。
自bは、もともと自aの痕跡(一瞬過去の自aのコピー)なのだから、
自bが自aを大きくは歪めまい。
(だから通常、自aと自bの緊張関係は、
歪自検知ニューロンにも滅多に見つからず、
従って「自のクオリア」が主題的に意識されることは無い。
「自分の自分という感じ」を意識的に見詰めようとしても難しく、
通常は「物を見る」「音を聴く」という知覚の反作用として、
「物を見ている自分」「音を聴いている自分」
に気付くのが関の山である。)
しかし、視覚や聴覚の入力によって基底自己循環信号(自a)の一部が歪むと、
その直接的な歪みが(入力の反作用として)大きく検知されるだけでなく、
伝播された基底自己循環信号全体の僅かな歪みが自己干渉し、
自aと自bの間にモアレのような干渉パターンを形成するだろう。
歪自検知ニューロンも、全脳的に独特な発火パターンを見せるだろう。
おそらく今の脳波測定技術では、
基底自己循環信号は、脳内全域に広がる背景雑音のようにしか見えず、
覚醒時の明瞭な信号によって歪んだり、全能的に影響が波及したり、
その結果、独特の分布で歪自検知ニューロンがザワザワと発火したりする、
その様子を捉えたりすることは出来ないだろう。
しかし、もし、このような舞台裏の脳波の様子まで
克明に観測できるようになったならば、
脳内で自意識が維持され、時間感覚を生じている
そのメカニズムも、かなりのところまで
物理的に解明することが可能になるだろう。
そして、人類が知る限り最も複雑な構造物である脳が、
このように精妙かつ重層的な情報処理を実現していることに、
奇跡を感じずにはおれなくなるだろう。
まさに、このような奇跡を実現した場合にのみ、
脳内に自覚が生じ、情報世界が構成され、「意味」が生まれる。
物理法則が宇宙と星と生命と知性を育み、
その知性が物理法則を再発見して意味を持たせている、
この奇跡的なバランス、すなわち物理世界と情報世界の相互依存こそが、
それ以上の理由や説明を受け付けない、究極の真理なのである。
|
時間
|
|
なぜ時間は唯一のもので、一方向に流れるのか。
|
殆どの解決や説明が困難な問題は、「時間とは何か」という問いに帰着される。
なぜ時間は唯一無二のものとして一方向に流れるのか。
これには幾つかの見方・考え方がある。
- 心理学的時間
我々の持つ「意識」は「いま・ここ」の一点に存在し、
「過去の記憶」や「未来の予想」の方が絶えず変化する。
「意識」が「いま・ここ」でない過去や未来を想起するメカニズムは明らかではないが、
一般的には過去はほぼ事実に対応し、未来は必ずしも事実と一致しない。
- 相対論的時間
「時間」は、時空多様体(擬リーマン多様体)の次元の一つとして定義される。
物理学は、多数の「意識」が共通に客観的・普遍的なものと捉え得る現象の
枠組みを与えるものであり、絶対的な個々の意識は時空の中で文字通り相対化され、
全ての意識の「いま・ここ」を収容可能な、広がりを持った時空を与えている。
どの意識にとっても共通なのは光速度という変化の単位であり、
各々の意識にとっての「いま・ここ」は光円錐上の各点として表現される。
- 超弦理論的時間
超弦理論は、プランク長程度の「ひも」の相互作用が世界を形作ると考える論理であり、
10次元時空で運動している、この「ひも」こそが現象の本質だと考える。
このうち6次元空間が内部空間にコンパクト化され、
たまたま外側に我々が良く知っている4次元時空が広がっている、という見方をする。
- 熱力学的時間
熱力学第二法則は『断熱系で不可逆変化が生じた場合、
系のエントロピーは必ず増大する』というものである。
この法則は、よりミクロな物理法則からの証明は未完成であるが、
経験則としては極めて強固で正しい法則であり、
時間の進む方向は、エントロピーの増大が与えていると考えられている。
人間の意識の活動も根源的にはエントロピーを増大させるものであり、
意識にとっての過去と未来の区別も熱力学第二法則に帰着される、
という考え方もできる。
- 宇宙論的時間
宇宙無境界仮説においては、
宇宙の始まりは時間と空間の区別の無い虚時間にあり、
特異点としての「宇宙の開始時刻」を必要としない。
プランク長程度の大きさを持った宇宙がトンネル効果で実時間の世界に
転がり出てきたと考えるのである。
この初期状態のエントロピーは極めて小さく、
熱力学的な時間の方向性の出発点を与えていると説明できる。
- 量子力学的時間
観測によって波動関数が瞬時に収縮する崩壊過程は時間の方向性を与えている。
一般に、多くの自由度を持つ系は時間経過につれてデコヒーレンスされ、
古典的な状態になるということが示されているので、
「観測」という曖昧で説明困難な現象を敢えて持ち出す必要性は減ってきている。
いずれにせよ、量子論的な干渉が可能な状態から不可能な状態への遷移が
時間の方向性を与えていると考えられる。
- 哲学的時間
哲学において時間とは、空間と共に認識のもっとも基本的な形式である。
科学的・数学的に定式化し、時空を客観的に捉える立場と、
意識の世界に本体を置き、時空をその直観形式として主観的に捉える立場がある。
必要なのは、これらを貫くシンプルで強力な「時間」の描像である。
「知的生命が持つ意識の群れ」は「物理的現象界」を認識して実在性を保証するが、
「知的生命の意識」それ自身が「物理的現象界」に支えられて存在している、
という自己完結的な自己参照構造が偶然成立する時、
見る側と見られる側の循環が時間という形式の基本単位となり、
変化すなわち意味を生み出す、というのが基本的なシナリオである。
◎時間の矢:
- 熱力学の第二法則(エントロピー増大の法則)は、
相対性理論や量子力学よりも確固たる理論と見做されている。
ある新しい理論が相対性理論と矛盾したとしたら
相対性理論を疑っても良いが、
熱力学の第二法則と矛盾するなら新しい理論は
捨てた方が良いとまで言われる。
初期状態の選び方によっては、
ゆらぎによってエントロピーが減少することはあっても、
何故か大局的に見るとエントロピーは
常に増加し、経験上例外が無い。
- これほど絶対的な熱力学の第二法則は、
量子力学などの、よりミクロな物理法則から説明・導出することが出来ない。
つまり、熱力学第二法則は、「なぜそうなのか」という説明を、
物理学の範囲では今のところ得られないでいる。
歴史的に見ると、熱力学の第二法則は、
諸々の永久機関の否定が定式化されたものとも言える。
つまり、一種の有限性(永遠性の否定)の主張であると言える。
- 熱力学の第二法則(エントロピー増大の法則)は、
何故かは分からないが、過去と未来を非対称とする数少ない(もしくは唯一無二の)
物理法則である。
乱雑さの増大により時間の方向が決定できるのである。
一方、情報のエントロピーは情報量を受け取ると減少する。
可能性を具体化するプロセスが我々の意識の本質であり、
時間の本質でもあるならば、時間の矢の問題は「情報エントロピーの減少」
という形で表現した方が分かりやすいかも知れない。
言い換えると、可能性を消費して具体物に両替する方向が
プロセスの進行方向であり、意識を持った者が選択した視点なのだ。
- 熱力学の第二法則は、我々が意識(自由性)を持つことの代償として
導入した「時間」と表裏一体の関係にある。
どちらが原因で、どちらが結果か、というよりも、
同じ事の言い換えであり、表裏一体だと言った方が良い。
意識する者(情報食者)が情報を獲得し、
可能性を物質に崩壊させるたびに、物質界の乱雑さは増し、
全てを知ってしまった時(情報エントロピーが最小になった時)、
物質界の乱雑さも最大になる………
それは、宇宙の熱的死そのものだ。
(熱力学の第二法則は、始まりと終わりを持つ我々の宿命の、
科学上の詩的表現なのかも知れない。)
- ところで、自循の要諦は、
「始まりと終わりがあり、自己を参照しつつ変化するもの」
であった。これが「意味の素粒子」であり、
これ以上条件を削れば自循ではなく、
従って有意味性は得られない。
「自己を参照する」という1プロセスが
即ち1クロノン(量子時間)であり、時間の意味の根源である。
だから、熱力学の第二法則が時間の矢を決めるのではなく、
時間の矢が「我々が自循の落とし子として有意味であるための」
プロセスとして根源的に(まず)定義され、
終わるためにエントロピーは必然的に増大するのである。
(終わる必要が無ければ、
エントロピーは別に増え続けなくても良い。
つまり、エントロピーが増えたり減ったり、
永久機関が存在したりする無意味な世界では、
熱力学の第二法則が成立していなくても構わない。)
熱力学第二法則が「時間の矢」を説明するのではなく、
有意味のための「有界な時間」が熱力学第二法則を説明するのである。
◎「時間」と「意識」
- 「私の私という感じ」という、この極めて独特で不可思議感覚は、
「時間」と密接に関係がある。
すなわち「一瞬間前の自分」と「今の自分」の差異の認識が
「自分という感じ」である。
言い換えると、「一瞬間前の自分は今の自分では無い」という
自己否定の構造が「自分という感じ」の維持に必要である。
- この構造は外界からのノイズで常に不鮮明で虚ろであるが、
この構造の《完成》には、座禅などによる周辺環境との隔絶による
アートマン的自循と、
周囲の人を愛し自分の一部と考えることの繰り返しによる自己の拡大の先にある
ブラフマン的自循
があるが、いずれも一個体の不完全性の反作用として現われる完全性への希求である。
- 赤ちゃんでも猫でも犬でも、クジラでもペンギンでも、
「意識」と呼べる現象は存在していると推定される。
つまり、程度の差こそあれ、
何らかの「自分の自分という感じを感じている」と思う。
また、「意識」は、
外界から一切の情報が入ってこなくても(入力が無くても)、
何ら動作や言葉を発しなくても(出力が無くても)、
少なくともある期間に亙っては継続して存在する。
- さて、記憶や抽象化、想起や判断といった知的活動を除外し、
外界との入出力とも切り離された、
「最も単純な意識の姿」
もしくは「意識のギリギリの本質」とは、どのようなものであろうか。
一言で言うと、それは『自己参照の場』という事になる。
ある瞬間の自分が一瞬間前の自分の一部を参照し、
その結果変化した自分は次の瞬間には参照される側に回る。
このプロセスの連鎖それ自体は、全くの無色透明であり、全くの無意味である。
『自己参照の場』それ自体がどんなに広大で複雑で、
沸き立つように自己参照を至るところ継続しているとしても、
一片の気泡も含まない完全に無色透明な純水が激しく対流しているが如く、
そこには何も見えない。
『自己参照の場』に、色水や不純物のように、
外界からの信号や記憶や希望が流入することで、
『自己参照の場』は姿を現し、自らをより複雑に変化させ、
様々な情報を外部に出力するようにもなる。
- それでは、最も単純な『自己参照の場』とは何であろうか。
「自己」の範囲を
「時間が経過しても、ある程度は境界が明確である部分」
と定義し、
「参照」というのは
「一瞬間前の自己の状態が、次の瞬間の自己に影響を与えること」
と定義すると、
素粒子一つであっても「自己参照」をしている事になる。
それらは幾つか合わさって、システムとして更に複雑な
『自己参照の場』を形作る。
例えば、
多数のクォークや電子から成る原子一個も十分に複雑な
『自己参照の場』と呼べる。
実際、原子は、外部からの入力に応じて内部状態を変化させ、
移動や放射を行う。
素粒子一個もスピンのような内部状態を持つのであり、
複雑さとか、「意識の濃さ」とでも呼ぶべき
「自分という感じ」の明瞭さの程度はさておき、
結局、素粒子一個ですら、意識を持っていると考えることは可能であろう。
想像を絶するほど希薄で単純ではあろうが、
素粒子も意識を持っている。
もはや「意識」という言葉を当てることは不適ではあろうが、
いかなる物質も、時間の上に存在する以上、
何らかの「意識」、もう少し控えめに言うならば
「意識の本質部分」を持っている、と言わざるを得ない。
これを否定すると、最終的には私たち自身の意識をも否定することになる。
- 哲学的ゾンビ
という概念装置は、「なぜ単なる物質のカタマリが、
意識を持つのであろうか」
という問いかけであるが、
「なぜ物質が意識を持っていないと
決め付けるのか」
という問いかけも同じように可能である。
我々が意識を持つことの不思議は、
物質が意識を持っていることの不思議にまで還元され、
それは、あらゆる物質も時間によって自己参照を可能にしている、
もしくは自己参照を余儀なくされている、という事実にまで遡り、
結局、究極の問題は全て、時間とは何か、
という問いに収斂する。
ひたすら無限に乱雑なだけの凍りついた動きの無い単なる存在に、
『参照する側(存在を認識する側=現存在)』と
『参照される側(存在する側=存在者)』という意味を付与する
キーストーン(要石)が《時間》であり、
《時間》によって宇宙は意識で溢れ、自己完結的に意味のある
世界を持つに至る。
- 敢えて、ありとあらゆるものの
根源
を指定するならば、それは
《時間》
であろう。
意識の問題ですら、時間の問題に帰着させ得る。
そして、《時間》は「あらゆるものの前提条件」であり、
時間という形式もしくは共同幻想もしくは仮説それ自身には、
「より根源的な」理由や説明は、全く無い。
《時間》というものは、この意味世界の外部から見たら、
無作為に選ばれた一つの軸もしくは視点に過ぎない。
何かから時間を説明しようとする試みは間違っている。
それらは全て、時間から説明されるべきものなのである。
- 主観的時間の群れから蒸留された客観的時間、
それらを貫く抽象的な《時間》。
「同じでありながら変化する」という矛盾を成立させてしまう《時間》。
無限乱雑空間上に《時間》は幾つ導入されても構わないが、
そのうち《意識》を内包する世界を浮かび上がらせる《時間》だけが
「存在している」と呼べる《時間》であろう。
- 意味記憶はエピソード記憶から時間概念が脱落したものだ、
という説明は、とても説得力があるように思われるが、
実は、意味記憶にある個々の概念も
意味ネットワークの中で相対的に位置づけられ、
常に概念空間上の躍動性の中ででしか意味を持たないことを考えると、
意味記憶にもエピソード記憶にも「時間」という概念は
根底にベッタリと貼りついていると言える。
たまたま数直線的・客観的・物理的な時間観念との対応が鮮明であるものを
エピソード記憶と呼んでいるに過ぎない、とも考えられるだろう。
- 単純に言って、私達は時間を止めてモノを考えることは出来ない。
「自分」を意識するものは、
意識している自分Aと、
意識されている自分Bを絶対に必要とし、
A=Bであるために空間を、
A≠Bであるために時間を持たざるを得ない。
どんなに抽象的な意味記憶であっても、
その究極としての「自己」という概念であっても、
「時間」から切り離されることは有り得ないのである。
- 知性を持たない動物は、過去をボンヤリ眺め、機械的に反応するだけだ。
一方で、人間は、眺める側である自分自身に気付いている。
つまり、全ての過去の最先端にある「現在の自分」に気付いている。
過去の方角を向いていた意識は、
逆算的に「現在の自分」を探し当て、
その逆算方向を更に延長することで、未来における自分をも捏造した。
つまり、希望を持ったり計画を立てたりするようになった。
時間という概念は、以上のような順序で組み立てられ、
他者との相互確認の過程で、本来は全く異質な過去・現在・未来が
数直線状に整理・単純化されて創作されたものである。
このように、概念の発生順序を追って考えると明らかなように、
時間という概念の発生よりも前に、
自意識の発生(自分自身の発見)が必要なのである。
- 夜、テレビをボーッと見ながら、今朝の会議の内容を思い出し、
明日作成する資料の構想を練っている。
今、私の脳内には、明らかに現在・過去・未来が同居している。
そして、過去と未来の描かれ方は非常に似ている。
脳内において、知覚を根拠とする「現在」の描かれ方が中心にあって、
現在に近づいてくる方向に描かれるのが「過去」、
現在から遠ざかる方向に描かれるのが「未来」である。
私は、ビデオテープを逆回しにするように
現在から遠ざかる過去や、現在に近づく未来を描くことができない。
結局、過去と未来の本質は、現在を中心に据えて
近づいて来るものと離れていくものという「質の違い」だと思われる。
もし他人がいなくて、「過去の実在性」なるものを確認しようもなく、
また確認する必要もないような状況では、
私にとっての過去と未来とは、思い描くものの質の違いに過ぎない。
そして、時間の本質というものは、
他人の存在の有無には関係が無いはずのものである。
原型的時間においては、現在・過去・未来は、
意識のうちに描かれるものの性質の違いに過ぎない。
だからこそ、同じ脳内の描像であるテレビ・会議・資料を
私は容易に自力で、他人に確認することなく、
現在・過去・未来だと仕訳けることが出来るのである。
- 「過去を思い出すこと」と「未来を思い描くこと」と
「過去にも未来にも属さないことを想像すること」に、
明確な区切りはあるだろうか?
「今現在を知覚すること」の場合には
外部からの入力があるのに対して、
過去や未来を思うことは、
脳内のフィードバックループに由来する現象で、
言わば「入力の自給自足」の結果である。
「外部」も「他我」も奪われた、孤独な「自」という現象とは、
カラッポの自分をひたすら見つめる自分、という
ループのみの単純なもの(自循)である。
ここに外部入力や可塑性(記憶)の機能を突っ込むと、
はじめて複雑な挙動を示す「自意識」になる。
ここが「現在」を形作り、そののち、
「自」に潜在していた原型的時間が、記憶に
「過去」「未来」という性質を付与するのである。
- 「ゼノンのパラドックス」は既に解決された。
時空認識というのが「自分が自分を見る」という本質的分裂に根差している以上、
「無限に細かい時空領域」とか「時間的に静止して凍りついた空間」という概念は
そもそも有り得ないし、実際のところ、
よくよく考えればそんなものは「自」そのものを否定することだと気付く。
身体とか生命よりも遥かに抽象的な絶対概念としての「自」を支えるものは、
「自」と「他」の空間的分離と、「見る自分」と「見られる自分」の時間的分離であり、
微視的に見て有限量の差分があり、その差分が有意味である(ゼロでない)以上、
分母となる巨視的に見た総体も有限である。
「自」を内包する有意味な宇宙に無限は有り得ない。全ては有限である。
そんなわけで、「ゼノンのパラドックス」は、
「自」を内包する有意味なこの宇宙ではとっくに克服されている。
アキレスは亀を追い越せる。無限に細かい時空などは無く、
ある瞬間にアキレスは亀と「ある軸に対して同じ位置としか認識しようが無い位置」になり、
次の瞬間にはアキレスは亀を追い越しているだけである。
(素粒子レベルで考えると、Zitterbewegungする2つの粒子が
「ある軸に対して抜きつ抜かれつするような状態」を経て、
そのうち完全に追い越す、という素描になるだろう。)
また、この世界の認識の根底が「見る自分」と「見られる自分」の関係であり、
いわばどの瞬間も静止しておらず、「意味的」「差異的」「速度的」なのであり、
「飛ぶ矢が、ある点時刻において止まっている」という描像自体が
(それがどんなに思考のうちに自然に思い描ける概念だとしても)
根本的に無意味なものである。
(実際、よくよく考えてみると、想像上ですら私達は、
空間内に固定されて浮遊し、止まっている矢を、
動いている時間上の立場からあれこれ眺め回して「確かに止まっている」
と想像するのである。つまり、時間は動いているのである。
“止まっている時間”というものを、
私達はいかなる意味でも想像することが出来ない。)
結局のところ、「有」の起源は「自」に求められ、
「自」を内包してしまった世界においては、全ては有限であり、無限は排除される。
だから、アキレスは亀を追い越せるし、矢は飛ぶのである。
「自」が無い宇宙において、
つまり、誰かが何かを主体的に認識するということが無い宇宙において、
永遠に亀を追い越せないアキレスがいようが、
飛んでいるのに動けない矢があろうが、
それは全く構わないし、勿論全く何の問題もない。
ただ単に、「自」を内包する“自覚する宇宙”においては、
アキレスは亀を追い越せるし、矢は飛ぶ。ただ、それだけのことなのである。
- 厳密に言うと私達の意識が認識しているものは
全て【過去】である、という事は、一般的には
素直には受け入れられない事のようである。
『今、この目の前にある景色を見て、
五感で世界を生き生きと感じている、
この感覚こそ“今現在”であるに決まっている。
これら全てが過去だなんて言ったら、
現在などというものは、どこにも無くなってしまうではないか。』
………その通りで、“現在”などというものは
直接的にはどこにも見当たらない。
極度に発達した人間の脳が、
「見るもの」と「見られるもの」の関係に感づいてしまい、
「見るもの(主体)」の座である“現在”という位置を
思考の内に逆算的に推定しているだけである。
(全ての「見られているもの」よりも未来であるところの
“現在”に鎮座する「見るもの」すなわち“自”を、
その卓越した抽象思考力で発見してしまったのである。)
意識が何かを知覚した時にはもう遅い、
それらは全部過去のものである。
そして、知覚している主体である“自”が住む“現在”は、
推定するものであって、体験できるものではない。
“自”は、「見るもの」と「見られるもの」に
本質的に分離しており、この分離が時間の原型である。
「見るもの」にとって、あらゆる「見られるもの」は過去である。
- 観察されるものは全て『過去』である。
『未来』とは、過去の中に含まれており、
過去自身の変容に言及するメタ概念である。
『現在』とは、過去(と未来)を観察する立場
であって、決して観察されない永遠の謎である。
(私達が、「現在を認識した」と思った瞬間、
その現在は、既に認識対象の側に回ったものであり、過去である。)
過去内部の未来を抜き出し、客観的事実のみを
扱うと決めて各々半直線としてモデル化し、
意味を抜き去った現在で接続して直線化する、
という大胆な改造手術によって物理学的な時間が
捏造されるわけだが、時間が本来持っていた
多くの意味を脱落させている点に注意したい。
- アウグスティヌスの時間に対する言及、すなわち
『時間とは何かと、誰も私に問わなければ、
私はそれを知っている。
しかし、それを問われ、説明しようとすると、
私はそれを知らない。 』
………これを、時間の正体不明さに関する“嘆き”である、
と解釈する向きもある。
しかし、この言及は、時間の本質に対する実に適確な表現であると思われる。
時間は、自我の無いところでは流れようがない。
「見る自分」と「見られる自分」の分離が、時間の流れの源泉である。
そして、「見る自分」という“主体”は、
見られる側のあらゆる事象との関係性の中から、
情報世界の中で逆算的に推定された抽象概念に過ぎず、
勿論、物理的実体では無い。
こんな情景を想像してみて欲しい。
空間のある一点に向かって、ひっきりなしに多くのボールが向かっていき、
跳ね返され、あたかもその一点に「何かがある」ように見える。
しかし、向かっていくボールを全てシャットアウトして、
その一点に何があるのかを見に行くと、そこには何もない。
正に、「放っておけばあるように見えるが、
何があるのかと見に行くと、そこには何もない」のである。
これは、情報空間の中で(身体性を担保に)探り当てられてしまった
“自”という概念の性質そのものである。
実際、人間を例として、感覚の全てをシャットアウトして、
フィードバック・ループも静まった頃に
「自我感覚はどこにあるのか」と探しに行くと、どこにも無いのである。
アウグスティヌスは、“嘆き”ではなく、
自我と時間の本質的な同一性を見抜いたことを、
控えめに表現したのではないか。
- 簡単のために、世界を映画やアニメーションの一コマのように2次元と考え、
これを時間軸に沿って積み重ねた3次元の彫像を考える。
時間軸のことを忘れると、目の前にあるのは、
凍結された単なる三次元のオブジェである。
そのオブジェの内部で変化の方向を「意識」する2次元の存在にとって、
時間は有意味であるが、
外部からその総体としての三次元のオブジェを眺める神の視点からは、
もはや時間は無意味である。
結局、時間とは、
世界の内側から世界を眺める方法であって、
「眺める」という主体性と切っても切れない概念である。
ところで、「眺める」という主体性の根源は、
「一瞬前の自分を、それよりも未来にある自分が眺めている」
という抽象的な仮説にある。
実際、この“自”という最も抽象的な概念の周辺に、
あらゆる概念や記憶や感覚はネットワークを為して連結しており、
物理法則とか時間とかの諸概念も、その一つに過ぎない。
この情報的な意味ネットワークの総体を情報世界と呼ぶならば、
情報世界と物理世界は概ね位相幾何学的に対応付けられているが、
その対応は、然して厳格なものではない。
「直線的な過去-現在-未来」という一般的に受け入れられている時間構造は、
「“現在”と“その他もろもろ”」という意識における自然な時間構造を、
無理に単純化したもので、
本来、過去と未来は、そんなに簡単には区別できないものである。
実際、私達にとって、太陽に対する半年前の地球の位置と、
半年後のそれの位置が意味することは、意味的には
「過去と未来」と呼び分けるほどのことではないし、
24時間前の私の心境と、24時間後の私の心境は、
現在の私の心境にとって同程度に確からしく、同程度に不確かである。
素直な感覚として、私達にとっては、
過去の記憶と、未来の想像と、どちらにも属さない幻想は、
それ単体で確実に区別できるものでは無い。
過去は確実で変化しないものであり、
未来は開かれて無限の可能性を持つ、
という理念は、真実というよりは、
社会秩序の維持のために発案された共同幻想だと言える。
たった一人しかいない世界では、
そもそも過去と未来を区別する必要すら生じない。
本質的には、過去は我々が思っているほど確実なものではなく、
未来は我々が思っているほど不確かでもない。
この「時間非対称(時間の矢)の願望」の源泉は、
ひとえに「“見られる自分”と“見ている自分”」という
本質的分離によって成立している自意識の性質に過ぎない。
自意識を抜きに観察するこの世界の総体は、
単なる四次元のオブジェに過ぎず、時間の矢を含む
三次元世界の時間的問題の全ては、原理的に
複数の意識の統計的な性質によって説明し尽くされる。
一本の時間軸は、複数の出来事が「どの時刻で同時に起こったか」
ということを測る尺度になっている。
しかし、私達は、東京にいながらにして、
地球の反対側のブエノスアイレスとの「同時」を
感覚的に了解することが全く出来ない。
妥当な周期性の信号を頼りに、
実感とはほど遠いところで、
かろうじて他者との「同時」を共有しているに過ぎない。
「他者との同時」は、光速度などを用いて
改めて定義しなければならないものであり、
意識における原型的時間の中には
そもそも「同時」という概念は無かった。
一本の時間軸(線形時間)は、自然に存在すると言うよりも、
他者との同時の共有のために創りあげられた
社会的観念だと言える。
時間はあくまでも意識における原型的時間から
派生したものであり、
意識を抜きにして時間を取り去れば、宇宙は彫像として凍りつく。
では、“物理世界”の諸法則は、“情報世界”を形作る
意識の作用によって練り上げられた幻想なのか、というと、
単にそうとも言えず、
むしろ、“物理世界”と、意識による“情報世界”は、
お互いが組み合わさって編み上げられた一枚の布であり、
どちらかが他方の原因となっているのではなく、
表裏一体のものである、と言った方が適切である。
「物理世界が生命と知的存在を育てた」と言うことも、
「知的存在が宇宙に潜む物理法則を探り当てた」と言うことも、
真実の一側面を表現したに過ぎず、
本来不必要な断片化であると言えよう。
この、物理世界と情報世界の不幸な分離を調停し、
意識による統一的な和解に至らせるためには、
時間の捉え方について、
今の物理学の側から、私達一人ひとりの意識が直感的に持っている
当たり前の時間感覚(原型的時間)に、少し歩み寄って貰う必要がある。
おそらく、相対性理論は、
ニュートン力学の世界観から、
意識中心の世界観への、一つの橋渡しとして、
将来再定義されるであろう。
- 言語の時間性
- 結局、人が哲学する理由は、「自分の人生全体が、
不気味なまでに徹底的に無意味である」という不条理に
何とか意味を与えたいと願う、初手から矛盾している
本能的衝動に他ならないであろう。
本質的に徹底的に無意味だからこそ、この問いは輝くのであり、
「たかが考えること」で易々と意味が与えられるなら、
そもそもこの問いには価値が無い。
-
今、私達が、世界を今あるが如く捉えていることの理由は、
私達が、今あるが通りに存在しているからに他ならない。
私達にとっての可視光の範囲が異なれば、世界の見え方は
大きく違っているであろう。同じように
私達が「自意識を中心として、感覚を通して得た世界の情報を、
時空内に位置づけて、言語によって理解する」という形式を
採っている以上、私達にとっての世界のありようは、
その形式を越えることはできない。
-
私達が意味の全てであると思っている世界が、
「なぜ」今あるが如くあるのか、という問いは、
究極的には「単に私達がそのように世界を見ているからだ」
としか答えられない。世界が赤いのは、私達が赤いサングラスで
世界を見ているからだ、というわけだ。
世界は「内側から意味づけられる」のであり、
超越論的な視点の導入は、どう足掻いても失敗する。
次々と理由を掘り下げ、真理を見つけようと先回りし、
世界を抽象化し、爽雑物を取り除いていくと、
「私が私を理由づけようとする」という地点にまで
辿り着いてしまうのだ。「理由づける」という指向すら取り除き、
「私は私」にまで純化されると、最早、取り除けるものは何も無くなる。
-
そして、この「私は私」という表明こそが、
最もコンパクトな、世界最小の矛盾(他を必要とせずに
矛盾している、という意味で、「自循」)である。
「私aは私b」という表明は、「私a=私b」と「私a≠私b」を
同時に主張しているのだから、間違いなく矛盾であろう。
「私a=私b」の方は分かりやすいと思うが、
「私a≠私b」は分かりづらいかも知れないので、説明をしておく。
一般に、わざわざ「私は私だ!」と表明する場合、
「私は、あなたが表現したような私ではない!」といったような
ことを主張したいのであろう。ここに「私」という言葉の形式的な意味が
良く現われている。「私aは私bだ。あなたの言う私cでは無い。」
私cは、外部で意味づけされる虚偽の私であり、
「この私」とは、空間的に隔てられたものである。
一方、私bは、空間的には同じところにいる、いわば内部の私であり、
私自身が理解している私の姿である。
では、全てに先立って、「私aは…」と宣言された、この「私a」とは
何者であろうか?
この、あらゆる前提も定義もなく、唐突に文章の先頭に現れる
「私a」こそが、主体としての私、「ただ、見る側としての私」なのである。
しかし、「見られる」ものが無ければ「見る」という主体は成り立たない。
「私b」とは、「私a」という究極の主体が、私自身を
どのように捉えているのか、という情報的な味付けが為された観察対象である。
-
ところで、相対性理論を待つまでもなく、観察対象とは全て【過去】に存在するものである。
目の前に置いて、ふむふむ、と眺めるものは、何であれ、
【過去】に属しているのだ。純粋な【今】というのは、「私a」の居場所のみである
(私a=【今ここ】である)。
1億光年先の星の姿が1億年前のものだというのは理解しやすいだろうが、
同様に、隣の部屋の壁や、1メートル前の鉛筆も、厳密には過去のものである。
「あれは確かに美味しかった」とか「よく見ると赤い」とか「熱い!」という感覚は、
全て【過去】に属するものである。
人間の意識にとっては記憶というものは無い。あるのは「思い出す」という
動的な思考のみだ。
だから、計算をするということと、思い出すということに、本質的な違いはない。
現に、どちらも脳神経回路上のイオン分布の時間変化に過ぎない。
「認識する」ことも「思い出す」ことも「未来を思い描く」ことも、
全ては【過去】に属しているし、これらの動的な思考には、本質的には区別はない。
ただ、人間が、「今見ていること」と「過去に事実あったこと」と
「まだ実現していないこと」を、便宜的に考え分けているだけだ。
従って、“人間にとっての世界は、全て【過去】に属する”。
そして、私そのものだけが、現在に属する。
その過去と現在を、唯一連続したものとして繋ぎ留めているのが、
「私」なのである。「私aは私b」と表明した時、
私bは既に【過去】の世界に溶け込んで対象物になってしまっているが、
それは、まさに【今ここ】にある私aと、私という矛盾した現象によって
辛うじて繋がっているのである。それ以外に、時間という形式が存在する理由は、無い。
-
「私は私」という世界最小の矛盾(自循)は、しかし、言い終わった瞬間に、
全て過去のものになる。「私a」は、言葉になった瞬間には、
既に【過去】に属しているから、
言葉を用いて「私a」を表現することは、原理的に不可能である。
言葉は時間に沿って一次元に展開する。言葉を0秒で表現することはできない。
「言語は必ず時間を消費する」
…これは、自然言語に限らず、論理式でも数式でも、
全ての言語一般において成立する真理である。
A→A(AならばA)と言った時、私達は
自然と両者のAを等しいものと考えがちだが、時間を消費しつつ流れる言語の
異なる位置に現れる以上、これは必然的に異なるものである。
実際、Aa→Abと書いた時に、Aaは「前提条件として置かれる仮説、
まず事実として置かれる事物」という意味を帯びているし、
Abは「幾つかの可能な状態から選ばれた結論、
可能性として思考される事物」という意味を負わされる。
この事情を、文法の中の異なる位置にある記号は、異なる意味を帯びる、
と表現しても良いが、私はもっと一般的に、
言語で語られるものは、全て時間の関数であり、原理的に何一つ同じではない、
ということを主張したい。
この事情に敢えて無理矢理目を瞑るのが、言語の普通の用法である。
特に論理学や数学においては、これは絶対である。
(2=2と言った時、前者の2と後者の2は、意味が異なるのだが、
そんなことを言い始めたら、どんな計算も出来なくなってしまう。)
-
つまり、こうだ。言語は必ず時間を消費する。しかし、ある一つの単語は、
どのような文脈のどこに現われても、同じであると仮定する。
言語は、時間を無視して使われる。
………実際、ここまでの文章の中で<意味>という言葉が何度か出てくるが、
それらの<意味>は「全て異なる」。一つとして全く同じものは無い。
それは常に異なる時間性を帯びているからだ。
もし、その時間性を含めて精密に文章を理解しようとしたら、どうなるだろう。
そうすると、文章は全く理解できなくなってしまうのである。
ある単語の<意味>を、文章の流れを含めて全て正確に位置づけるには、
それまでに出てきた単語の全てとの比較検討が必要になる。
そして、新しい単語が一つ、発話されるたびに、最初から
この比較検討をやり直す必要がある。文章がある程度長くなったら、
単語一つの<意味>を確定するのに、人の一生分の時間を要するようになるだろう。
ましてや、私達が日常語る言葉の一つ一つは、有史以来の人間の
全ての言語活動と薄く広く関わっているとも言える。
深遠な哲学用語から、勘違いから定着した俗語に至るまで、
全てが関係してくる。言語の使用においては、
それら過ぎ去った膨大な過去情報は、ほとんど無視せざるを得ない。
結局、言語は、本質的に時間的なものなのに、
時間性を無視しなければ、語られることすら出来なくなってしまう。
-
もし、言葉で「私」と言ってしまったら、それは、何となく、
古今東西、どこでも通用するような、時間性や空間性を超越した「私」
であるようにしか、受け取ることができない。
つまり、「今、ここにいる、自分自身としての私」のことを言いたいのに、
言葉を使った瞬間に、それは「私一般」に化けてしまうのである。
私達は、そのようにしか、言語を運用できない。
あくまでも意味を厳密に確定しようとすれば、
私達は、たった一つの言葉ですら、発することは出来なくなってしまう。
しかし、私達は、「私aは私b」という世界最小の矛盾(自循)の中に、
言葉が時間性を持ってしまっていることも見出さざるを得ない。
「私a=私b」と「私a≠私b」を同時に主張していると認めざるを得ない。
-
ところで、よく「矛盾した前提からは、何でも結論できる」と言われる。
これを使って少し遊んでみよう。
記号論理学で「A→B」といえば、これは「¬A∨B」のことだ。
Aが偽の場合は、A→Bは真となる。だから、Aが恒偽命題であれば、
何をBに持ってきても、A→Bは無条件に真なのである。
(Aが矛盾していれば、何をBに持ってきても、A→Bという主張は正しい。)
Aを「私は私」とすれば、これは矛盾している(恒偽命題である)ので、
世界のどのような事物を持ってきても、つまり世界そのものを持ってきても、
A→Bは正しい。
「私が私ならば、世界の全ては存在する」…これは無条件に正しい。
とんでもない結論が得られたようにも見える。
そう、これは、時間性を前提として「私は私」を矛盾としているのに、
時間性を無視した命題論理を適用した、という誤謬の結果だ。
本質的に時間性に関わる問題を論じている時に、
時間性を無視した論理的な思考を進めると、
妙な結論を幾らでも導き出すことが出来てしまうのだ。
結局のところ、人間は、言語を通してしか世界を理解できない。
むしろ、世界の理解の仕方が言語である、と言った方が良いかも知れない。
その言語は、時間性を無視しなければ、語ることができない。
厳密に時間性を考えて意味を確定しつつ話そうとすれば、
もはや人は、一言も発することが出来なくなってしまうのであった。
ここで、「私aは私b」と言った時には、
知覚(現在)や想起(過去)や夢想(未来)には特段の区別は無く、
厳密には全て【過去】において私bと共に対象化されているものであった。
一方、真の【今ここ】である「私a」は、決して対象化され得ない、
言葉で語ってしまった瞬間に私aで無くなってしまう何物かである。
だから、私aは、言語では理解できない。
だから、私は私を理解できない。
そして、世界とは、私が私である通りにしか認識することができないものであった。
だから、もちろん、私は世界を理解できない。
よって、私は全てを理解できない。
-
人が哲学する理由は、自分の人生全体が無意味だと確信するほどに、
余計に意味づけしたくなる、という自己原因的なものであった。
言語で理解し、意義付けようとすればするほど、時間性を失った理解の中で、
自己はますます無意味になっていく。
言語理解を緩めて、私aをただ時間性と共に感じる時、
意味や価値が復活するようにも思われるが、同時に確固たる理解が失われていく。
だから、結局のところ、語りえないものについては、
ほどほどに語る程度にした方が良いのだろう。
遠くから見る分には見えるものの、近づいていくと像がぼやけ、
核心に飛び込もうとすると、そこには何もない。
それが「人生の意味」の性質である。
常に流れ続ける時間の中で、時間性に本質的に縛られているのに、
時間性を無視して敢えて語ろうとすること、
それが、言語を通した理解が抱える本質的な限界である。
赤いサングラス(言語)を通して世界を見れば、
世界は赤く(言語的に・非時間的に)しか理解できない、というわけだ。
その輪をどこまでもキツく引き絞っていった時に辿り着くのが、
「私aは私b」という世界最小の矛盾(自循)である。
私aは、語ろうとした瞬間には、もうそこにはいない。
もしくは、【今ここ】の私aは、語ってしまった瞬間に、【過去】の私bに
変質してしまう。
語ろうにも語れない。これは絶対に解けない知恵の輪なのだ。
-
人生は理解できない以上、無意味だと結論せざるを得ない。
しかし、無理に精密な結論を(言語によって)出そうとせずに、
キツく引き絞った輪を少し緩めて、
語りえないものを、ほどほどに語ることで、
少しだけ<意味>を取り戻すことには、<意味>があるのではないだろうか?
全てを(時間性を無視した)論理で片付けても、
全てを(純粋な時間性として)刹那的に捉えても、
意味の出力はゼロになってしまう。
どちらに転げ落ちても無意味になってしまう人生の稜線を、
私達はあぶなっかしく歩いている。それが、この世界の形式が課した、
人生というものの真の姿なのだ。
…過去に敬意を払いつつ、今を可能な限り楽しむ。
…伝統を重んじつつ、現在を肯定する。
そのバランス感覚を養い続けることが、結局のところ
人生の意味出力の最大化に繋がるのだ。
-
語りえないものについては、ほどほどに語ろう。
- 原型時間
- 主観時間と客観時間を対比して考察した時間論はたくさんあるが、
ほとんど全ての場合、主観時間に「過去-現在-未来」という構造がある、としている。
しかし、自循論における主観時間には、「[現在]と[過去]の離散二時刻」しか無い。
しかも、[現在]は絶えず再構成される仮想概念であり、直接の内観は不可能な特異点であり、
私達が現在と呼んで認識できるのは、[過去]に滑り落ちた[現在]の痕跡だけだ、としている。
未来に至っては、「[過去]の概念」と「[現在]の痕跡」を結んで延長し、意図的に捏造した概念であり、
それは計算の結果であって、もともとの時間感覚には含まれていない、と主張している。
つまり、自循論においては、通常の哲学が言う「過去-現在-未来」という主観時間は、
全て[過去]に属するものなのだ。
これこそが私達が実感として理解している純粋な時間だと思うのだが、
主観時間という言葉は既に一般に使われてしまっているので、
[現在]と[過去]の離散二時刻からなる時間感覚のことは原型時間と呼ぶことにする。
-
このように、自循論においては、[過去]に含まれる諸概念同士や知覚入力情報が計算されて、
新たな[過去]が作られる思考運動において、
「[現在]の痕跡」との対比で過去性や現在性や未来性が構成されると考える。
特に、これらの思考運動の結果として、絶えず新たな[現在]が再構成され続けるのだが、
この、[過去]の平面から浮き上がって超然と維持される[現在]こそが、
自己なるものの核なのである。
それを自循論では「自a」と呼び、
自aが[過去]の平面に滑り落ちて記憶の中に組み込まれた像を
「自b」と呼ぶ。
自分が自分であるという、この不思議な感じ、すなわち「自のクオリア」とは、
[過去]の平面内で行われる、いかなる思考や演算とも異なり、
いわばそれに直交する垂直な思考運動として、
自aを必死に再構成しつつ、その結果を自bとして再認識する、
この持続によって発生しているのである。
|
自循
|
|
自循論の知的思考フレームワークで、
自己の人生の有意味性を再検証する。
|
望まずして生まれ、その意味も分からず死ぬ、「自分」。
その全ては、森羅万象が奇跡的に獲得した有意味性と表裏一体であった。
「今・ここ」にある「自分」は、何をするべきかを結論づける。
|
自
|
|
抽象概念としての「自」を中心に、全てを捉える。
|
- “自”という概念は、「自己言及」を含み、
必然的に「自己同一性」と「自己否定」を要する。
(どちらか一方だけなら有意味なことは何も発生しない。)
よって私は矛盾を含む抽象概念である“自”を
全ての有意味性の根源とするので一元論者であり、
“自”が本質的に矛盾していることで
自-他、現在-非現在(過去・未来)、情報-物理などの
あらゆる対立概念が鏡像関係として現われることこそが
“自”にとっての意味の相の安定性を担保している
と信じているので、二元論者である。
一元論と二元論は、私の思考空間の中で矛盾しない。
“自”という一元的な絶対概念の内側に、
二元論を展開するのに必要な構造が仕込まれている。
物理世界と情報世界、身体性と意識、
「今ここ」とそうでないもの、といった
二重性は、本質的な“自”の内部構造である。
- 最も抽象的・根源的で数学的に純粋な“自”という概念は、
「“自”でないものではないもの」(S=¬¬S)
としか言い表しようが無い。
この定義の過程で一瞬だけ姿を現す「自分ではないもの」(¬S)
には、何ら定義が与えられていない。
「全体から“自”を引いたもの」と定義するには、
「全体」を定義する必要があるが、
ここでは全体とは何かということは不問に付されている。
「“自”でないもの」が何であるのかは未知である。
ただ最低限、「“自”でないもの」は、“自”の境界線の外側に
何らかのトポロジカルな意味での「広がり」があることを示唆する。
それは時空連続体として認識されるものであり、一般的には
強制的に流れて変化を生み出す《時間》と、
再現性を持ち自己同一性を保証する《空間》に分けて考えられる。
この枠組みで“自”を捉えなおすと、
情報世界において「“自”が“自”自身を参照する」(S'←S)という表現になり、
物理世界において、その最小単位が相対性理論の公理である「光速」として表現される。
- 見えるものの全ては過去である。
一億光年先に見えている星の姿が一億年前のものであるのと同様、
自分自身の手についても、厳密には過去の姿が見えていることになる。
視覚に限らず、五感の全ては過去のものであるし、
感覚に依存しない記憶や思考も含め、
とにかく「観られるもの」「認識されるもの」は全て過去である。
それら全ての過去の最先端に位置し、一方的に情報を受け取る「現在」が
自意識の居場所ということになる。
脳の中になだれ込んだ情報は、意識にのぼる前の0.5秒のうちに
100回も脳内をグルグルと駆け巡りながら、選択され、抽象化され、
調整され、淘汰される。
この様子を物理的な電気信号や血液の流れとして追跡しても、
何が起きているのかは分からないだろう。
コンピュータのメモリやレジスタを見ても、
何を計算中であるのか分からないのと似ている。
これを物理世界とは異なる情報世界における
意味シンボルのネットワークの視点から見ると、
無意識層での意味(単純な「痛い」「眩しい」「熱い」といった反応を含む)から
徐々に高級な概念(「赤い」「気持ちよい」「美味しい」など)に結びつき、
この情報世界の中核に位置する「自」という概念と相互作用し、
それと同時に「自」という概念の方も維持・強化される、
というダイナミズムを見て取ることが出来るだろう。
あらゆる過去としての入力情報が
「自」という中核概念との位置関係に整理されるプロセスが
「認識」というものである。
情報世界の景色を模式的に思い浮かべてみよう。
中央に「自」というボールがあり、
その周囲に各種の大きさのボールがゴムひもで複雑に結びつき、
それを莫大な数のボールとゴムひもが複雑に取り囲み、
遥か遠くにある最外周には、各種の感覚器官や運動器官に対応する
単純なシンボルが並んで、物理世界との接点を為している。
外部からは絶え間なく視覚・聴覚に基づく情報が入り込み、
ボールを震わせ、その振動は他のボールにも伝わる。
新たなボール(概念)やゴムひも(関連)を生成したりしながら、
この躍動の波は中央部にある「自」に押し寄せる。
「自」に接続するゴムひもは増加し、
より多くのボールとの関係を持ち、
「自」の輪郭は益々明確になり、諸概念の中で不動の地位を得るに至る。
「自」の周辺には身体性や本能に基づく原始的な概念から
空間、時間、物体、境界、数、否定などの高度に抽象的な概念までが
びっしり結びつくだろう。
そして、十分に成熟した「自」に押し寄せた波は、
周辺の諸概念を震わせながら、確固たる核としての「自」に
弾き返されるように、周囲に波を押し戻す。
「自」が「自」であり続けるように、「自」周辺のボールが
調整され、調和される過程は、感情としても現われる。
感情というのは、入力情報が「自」を激しく揺さぶる際に、
これを調整して「自」を一定の位置に保つためのダイナミクスの副作用である。
喜怒哀楽は、「笑い飛ばす」「叱りつける」「泣き喚く」「受け流す」
といった調整によって「自」の絶対性を保護しているのである。
「自」に押し寄せた波は「自」を核に反射され、
今度は「自」を中心に広がっていく。その波が、
最外部の運動器官を表すシンボルに到達すると、
この情報が物理世界の身体運動を励起し、手を上げたり、走ったり、
笑ったり、涙を流したり、といった外部出力に繋がる。
この広大な意味ネットワークは常に並行動作しており、
実際、中核の「自」と関連せずに波が伝播する
(すなわち無意識に処理される)部分が大部分を占めているだろう。
重要なことは、中核の「自」というボールが
情報空間の中では確固たる位置を占めて、
周囲からの情報を「押し返す」という役割を果たしている、という事である。
これこそが、自意識を持った生命が単なる自動機械と異なり、
主観を持ち、自ら選択・判断をする、ということの核心であり、
「自分が自分であるというこの不思議な感覚」の発生場所なのである。
この「自」という中核概念のボールにゴムひもを伝って波が届く時、
その波の原因は全て過去の出来事である。
よって、これを「押し返す」というプロセスで発生する
「自分が自分であるという感じ」は、
あらゆる過去の出来事よりも未来であるところの「現在」に位置する。
この「自」から出て行った波の幾つかはフィードバックされて
再び「自」に押し寄せてくるだろう。
その時も、受け手の「自」は「現在」であり、
先ほどの発生源としての「自」は、既に過去になっている。
同じ「自」が、現在と過去に分裂し、「見るもの」と「見られるもの」になる。
この「同じであるのに異なる」という最も根源的な分裂の自覚こそが、
時間・空間という概念を形作る。
いわば、時空と「自」は同時発生的に生まれ、
互いに強化し合う概念であると言える。
もしも「自」という核が無かったら、
この意味ネットワークは単なる複雑な計算機に過ぎない。
「同じであるのに異なる」という根源的分裂の自覚に伴う
時空概念を生み出さないのである。
このように、「自」という概念は、かなり複雑な構造を持っており、
抽象度の高いものである。
情報世界の意味ネットワークが発達し、
十分強固な「自」という概念を獲得するためには、
少なくとも人間程度の脳の複雑さが必要なのであろう。
(もしかすると、更に巨大な脳を持った生命が持つ自意識は、
人間のものより遥かに強固かつ鮮明であり、
脳内の情報世界の比重が大きく、
感覚器官や運動器官を通した物理世界の意味は、
ずっと希薄なものであるのかも知れない。)
ある宇宙が「自」を内包する生命を持たなかったら、
たとえそこに時空のようなものがあり、星が生まれ、生命を育み、
動物が走り回り、銀河が失われるまでの宇宙の一生があっても、
それは外部から見たら一つの静的なオブジェに過ぎない。
例えば空間3次元+時間1次元の全体は、
時間に沿ってその宇宙を体験する存在がいないならば、
動きの無い4次元の凍りついた
少なくとも「何らかの形状」以上の意味は持てない。
一直線に飛ぶ鳥は、断面が鳥の形状をした棒として凍結される。
どの生物の一生も、外部から見たら一本の管(くだ)として
静的に表されるだけになってしまう。
その宇宙の内部にあって、「自」という概念を持った存在を内包し、
その存在が宇宙の内部から時空を認識するからこそ、
鳥は生き生きと飛ぶし、生命は生まれて何かの役割を果たし
そして死ぬのである。
だからこそ、
この意味世界において最も根源的なものは“自”という
唯一無二で普遍的な抽象概念である。
そして、無限に存在する自己完結的な宇宙の中で、
“自”という抽象概念を意識できる存在を内包した宇宙だけが
有意味なのである。
- 「自」と「無い」
- 「無い」という概念は極めて高級である。
「無い」という概念は、「自」の成立に必要不可欠なばかりか、
「無い」と「自」は同じことの両面と言っても過言ではないほど
密接な繋がりを持っている。
何故なら、「あらゆる認識されているもので“無い”もの」が、
「認識しているもの」、すなわち主体的な「自」なのだから。
いわば、「私が私であるという、この感覚(自のクオリア)」は、
「無い」という概念の全面適用による純粋な成果物であるとも言える。
そして、そのような「自」という核を持つことによって、
「自では無いもの」としての対象が逆算的に客観的実在性を帯び、
「無い」という概念は更に強化される。
こうして、「自」と「無い」はお互いに純度を増し、強化される。
- 「文化とは言語である」とか「人間知性とは即ち言語である」などと、
やたら「言語」を持てはやすような表現を時々見掛けるが、
ここで言う言語とは、音声言語のことであり、
抽象概念のことであり、要するに情報のことである。
人間は音声言語を獲得することにより、
身振り言語では表現不可能であった抽象的な概念の伝達を可能とした。
その最も典型的な概念が「無い」である。
身振り言語では「無い」という概念を表現することができない。
(「無い」ものを直接指差すこともできないし、
「無い」ことの物まねをすることもできない。
顔の前で横に向けた手の平を振るとか、手話のような身振りは、
音声言語の翻訳であって、元来の身振り言語ではない。)
「認識しているもの、そのもの」では「無い」ものを、
脳の中で情報として扱うことが、思考空間すなわち情報世界の
重要な前提条件である。
脳神経回路が、「無い」とか「ゼロ」といったものを扱えるほどに、
高級な抽象化力を持つには、少なくとも人間の脳程度の
容量が必要なのだろう。
- ところで、現実の世界(物理宇宙)には、「無限」も「連続」もない。
どこまで行っても果てが無い、なんてものは無いし
(実際、宇宙の大きさは限られている)、
どこまでも滑らかで繋がっている、なんてものも無い
(実際、量子数は整数か有理数だ)。
無限も連続も、計算や測定の便宜のために、
私たちの思考の内に捏造された概念に過ぎない。
それなのに、無限や連続が物理宇宙でも成立するはずだと、
とてつもない大逆転の勘違いを信じ込むと、
アキレスは亀に追い付けない、等と大騒ぎしなければならなくなる。
情報世界の中で扱い易く便利な概念を駆使するのは知性の本質であり、
結構なことであるが、だからといって、
物理世界まで扱い易く便利だと思い込んではならない。
- この、「無限」とか「連続」という幻想を支えているのも、
「無い」という否定概念だ。
「無限」は、もちろん、「限りが無い」という否定概念に支えられている。
無限そのものを持ってくることは出来ないので、
終わりとか果てが「無い」という否定概念で表現するしかない。
一方、「連続」の方は、「隙間が無い」という否定概念に支えられている。
あるモノをポッキリと折って、何も失われないのだとしたら、
そもそも一体だったモノには、隙間があったことになる。
もし「隙間が無い」のだとしたら、ポッキリと折った二つのうち、
一つの断面には境界が含まれ、もう一つの断面には境界が「無い」
ということでなければならない。
これが、連続や実数の定義として有名なデデキント切断の要点である。
しかし、何かそこにモノがあるのに、「境界が無い」とは、
一体どういう意味なのだろうか。
端的に「3未満」と言った時、2.9も、2.99も、
それこそ9を1億個書こうとも、
それは「3未満」であって、3ではない。
このように、境界に限りなく近づけても、境界そのものに辿り着けない、
という事態が、「境界が無い」ということに相当する。
ポッキリ折った時、その境界は、2つに別れたどちらかだけのものなのであり、
どちらか一方には境界が無い。
境界には限り“なく”近づけるけれど、そのものには辿り着け“ない”。
このような否定概念が、「連続」を支えている。
アキレスが亀を永遠に追い越せないのも、「無い」という概念に裏打ちされた
「連続」を、情報世界内で使用するからである。
勿論、現実の物理世界には「無い」などという事態は無いので、
アキレスは亀を悠々と追い抜いていく。
- このように「無い」という概念を自家薬籠中のものとすることによって、
人間の認識は「あらゆる見えているもので“ない”位置」=「ここ」とか
「あらゆる覚えている体験で“ない”時刻」=「いま」を
確固として扱える概念にまで純化し、
常に脳内を満たす「いま・ここ性」すなわち「自のクオリア」の
安定化に成功する。これが「自意識」の基盤を為し、
「感じる」とか「決める」といった主体感を生み出すモトとなる。
このような情報処理過程は、脳の全域的な活動であり、
極めて精妙なバランスで維持され続けている。
体重に比して重さたったの2%の脳は、全エネルギーの実に18%も消費している。
脳は睡眠中もフル活動し、情報の入出力が無い時にも
「脳自身のことを考え続けて」この「自のクオリア」を
神経回路網の決定的構造として維持している。
この構造が、ある程度堅牢であるからこそ、
外来情報の入力に対して、自我を保ちながら、
感じ、考え、思い出し、判断し、行動することが出来るのだ。
もし、自意識を維持することなく、単に入力と出力の間の
高度で複雑な計算をするだけならば、脳の複雑さと消費エネルギーは
いかにも過剰である。
何の感覚情報も処理せず、何の身体運動も指示していなくても、
脳は無意識下で全力運転し、無色透明な「自のクオリア」を
維持し続けているのである。
- 健常者が覚醒時に易々と体験している、この「自分が自分である
という感覚」すなわち「自のクオリア」は、
このように脳の精一杯の働きで維持されているのであり、
思った以上に壊れやすいものである。
熱心に何かを喋り続けている時、意識の一部を使って
自分の声に集中すると、「自のクオリア」は、ぼやけはじめる。
自分が自分で無いような、奇妙な感覚に襲われる。
普段は意識から自分の声を差し引いて、「自」の堅牢性を守っているのだが、
敢えて自分の声を客観的に捉えようとすると、
自分の思考までもが客観化されるような錯覚に捕われる。
自分が言葉を紡ぎだす自動機械のように感じられてくる。
意識は「自分で“ない”もの」に向けられるのに、この働きを
自分自身に向けると、自分自身まで自分では“ない”ものに感じられ、
自分がどこにもいなくなってしまう。
そんな気分になってくる。
勿論、このような恐ろしい気分は、自分の声への意識を止めた瞬間に
消えてしまうものである。
しかし、脳の器質的・機能的な問題により、
このような正常な「自のクオリア」が維持できないこともある。
無意識の内にフル稼働している「自」と「無い」という概念の
相互強化関係が薄れて、「自のクオリア」がぼやけることで、
離人症や分裂病といった精神病を患うことになるのではないだろうか。
- 離人症(depersonalization)とは、自己の存在や自分の周囲の対象に
現実感の喪失や疎遠感を抱く特異な意識体験のことだ。
自分が自分で無いように感じ、対象や他人に疎遠感を覚えるようになる。
精神分裂病(schizophrenia)は、典型的な内因性精神病で、
現実と非現実の区別が障害されている。
幻覚や妄想が生じたり、思考と行動の統一性が失われたり
貧困化したりする。
いずれも、「自のクオリア」という、しっかりとした情報世界の核が
ぼやけてしまっているために、
自の連続という時間概念が希薄になり、
個々の時刻がバラバラに体験されたり、
「ここ」と「あそこ」の区別が曖昧になって空間概念が希薄になり、
物体間や概念間の区別も曖昧に感じられたりするのだろう。
- 一方、うつ病(major depression)は、気分障害(mood disorder)の一種で、
抑うつ気分や精神活動の低下を特徴とする精神疾患である。
悲観的な考え、憂鬱で悲しく気落ちした気分、
絶望、興味や喜びの低下、食欲減退、気力減退、集中力低下、
不眠、不安、焦燥、思考制止(着想貧困化、考えが分からない)、
活動性の低下、疲れやすさ、罪業感、決断不能、
死についての反復思考、などが症状として現れる。
これは「自のクオリア」が萎縮してカラ回りし、
外部の情報を柔軟に取り入れる余裕が無くなっている状況だと思われる。
脳の活動量が何らかの理由で低下しているため、
「自のクオリア」を死守するのに精一杯で、
感じ、思い出し、考え、判断し、行動する、という
一連のイキイキとした思考活動を営む余裕が無くなってしまうのだろう。
- 私たちが、物心ついたころから、普通に手にしている、
この「私が私である」という感覚、すなわち「自のクオリア」は、実は、
「無い」という高級な概念を駆使して編み上げられ、
この宇宙で人類が知る限り最も複雑な構造物である脳が
四六時中全力を挙げて維持している、精密で繊細な芸術作品である。
それだけに、思った以上に壊れやすくもある。
健全な精神活動を維持するには、
脳を乗せている身体のお手入れにも、十分に配慮する必要があるのだ。
【指導原理】:
1プランク長・1クロノン内の仕組みは、どんなに複雑でも構わない。
この宇宙全体より複雑でも。
我々の世界も、我々の意識も、
1、2、3と、「1クロノンずつ」数えられるプロセスを経て
先に進む過程だけを考える。
本質的には1回の操作で幾許かの可能性が消費されて具体化され、
“可能性の状態”も具体的な物質も、
公理(法則)に従って変化するが、
この一連の流れを後から分かり易いように数直線的に表わしたのが
我々にとって馴染みのある「時間」なのであり、
逆算的にこの1回の操作は少なくとも
1クロノン(約5.391×10-44[秒)以下と言えるであろうが、
別の尺度から見た1回の操作の時間はバラバラかも知れない。
例えば、この宇宙を超知性体が作った
一つのコンピューターシミュレーションの産物だとして、
ビッグバンによる宇宙開闢当初よりは、
今の1クロノン内の演算量の方が遥かに大きく、
超知性体から見れば長い時間を要しているように感じるかも知れない。
(計算されてた結果としての我々にとっては、
その計算過程自体に気付くことは出来ないので、
我々が意識する我々にとっての時間は
規則正しく流れている、としか感じようがない。)
1クロノン内に行われるこの秘密のプロセスを、
波束の収束とか量子飛躍とか観測者効果とか並行宇宙の分裂など
色々な表現で呼ぶとしても、
「私」という意識の中では「可能性を現実に両替した」(可能性を消費した)
という過程が、許される範囲で進行しているとしか言いようがない。
※並行宇宙論的に言えば、任意性があるというよりも、
可能な全ての選択は実際に起こり、その可能性の数の分だけの
宇宙に分裂する、という表現になるだろう。
※何故、可能性は、パチンと音を立てて具体物に崩壊するのだろうか。
→それは、境界条件があるからだ。無意味・無限の世界では、
崩壊・具体化・波束の収束・状態減らしなどが起こる理由はない。
→つまり、あらゆる瞬間に約束として織り込まれている有限性に、
否応無くぶち当たってしまうからである。
→可能性を消費し尽くして死ぬ、という意味世界でのみ、
量子崩壊は起こるのである。
無意味な世界では量子崩壊(状態減らし)が起こる理由は無い。
◎素時空
素時空は、私たちにとっての「客観の限界」と「主観の限界」が交わる、
いわば「意味の限界」である。
プランク長以下に折り畳まれた、我々にとって中身を窺い知れない
空間の素粒子を「素空間」と呼ぶ。
生物全体の設計図が個々の細胞の中に遺伝子として折り畳まれているように、
宇宙全体の境界条件が個々の素空間の中に折り畳まれている。
素空間内の構造は我々にとっては原理的に不可知で無意味だが、
空間の遺伝子は、ブラックホールを越えて別の宇宙に遺伝しているかも知れない。
我々の宇宙自身も、そうやって出来たものかも知れない。
多くの宇宙の記憶が我々を作り次の世代の宇宙に繋がるのかも知れない。
地球上の生命の中で人類が優秀で多くの子孫を残しているように、
我々を生んだこの宇宙も、他の進化系列の宇宙の中では優秀な方なのかも知れない。
プランク時間より短い時間のうちに起きていることは我々には分からない。
分からないと言うよりも、原理的に無意味であり、知る必要もない。
我々から見てミクロな、この素時空の中に、無限の複雑さがあっても良い。
そして、我々が考えうる最もマクロな宇宙の総体は、より上位の宇宙にとっては
素時空であるのかも知れない。
- 自分がいつか確実に死ぬ、
自分は 消え去る、無くなる、
未来永劫この《自分という感じ》が 失われる、という絶対的恐怖は、
一度、分解され、再解釈される必要がある。
- 一般的に、死という一つ同じの現象は、次の三つの観点から語られる。
- 第一人称の死。自分の死。体験不可能な神秘。自己内他者性という矛盾。
- 第二人称の死。愛するものの死。他者関係の基盤。感情の臨界を形成。
- 第三人称の死。生物としての死。有限性、有意味性の輪郭を形成。
同じ現象が視点の選択によって、これほど質的に違った
意味を有するという事柄は、他には類をみない。
逆に、この3つは単なる視点の差に過ぎず、本質は同じ
だとすれば、その本質とは何かを抽出する必要がある。
- 次に死という絶対悪の解毒方法も大別して三つの方法がある。
- 生の価値増大。死により生きる意味を捉え直す。
- 生の価値抹消。ニヒリズム。全ては無意味と考える。
- 判断停止。宗教や伝統や自然や社会に判断を預ける。
第一人称の死はいかなる意味でも解決不可能なので、
解毒とは「目の背け方」に過ぎない。
死の恐怖を、生命の価値や宇宙の広大さや神の絶対性に
皺寄せするのでもなく、死の受け入れ方を考えるのでもなく、
もっと単純に「死の意味」を明晰に構造化する必要がある。
- 生き生きと躍動するこの複雑で果てしなく大きく美しい
世界の中で「死」をどう捉えるか、ではなく、
「死」という現象を抽象化し、
その一点を基盤にして世界を再構築することで、
世界を極座標変換する。
- 生よりも死がクローズアップされる根源的理由は
「時間の矢」つまり一方向性にある。
つまり、死に焦点を当てることで、
意識と時間と世界の全ての関係が明確になるのである。
- 死と生の定義には物質的観点と情報的観点があり、
この世界の成り立ちの
二重性
に対応している。
生命として『物質的に生きている期間』は、ある程度明確に定義できるが、
期待や記憶を含めた『情報的に生きている期間』は、その前後に少し染み出している。
「あんた達も結婚して3年経つんだから、そろそろ子供を作ってもいいんじゃないかね」とか
「本当に惜しい人を亡くした、あれだけの才能が若くして消えるのは産業界の損失だ」とか言い、
物質的な生の前後に広がる情報的な生を、私達は物質と同等かそれ以上に
有意味で価値あるものと考えている。
そこで、
情報
とは何ぞや、と考えると、これは生きている私達の《意識》と
切り離して考えることが出来ない、物質世界に《意識》が重ね描きしているものであった。
つまり、《情報的な生》は、《物質的な生》に対して《意識》が重ね描きするものであり、
それは《時間》を超越するという性質を持っている。
そもそも、
《時間》は、
《意識》
の総体による意味世界を構築するための前提となるカラクリであり、
時間が無ければ意識は発生しないし、意識が無ければ時間も流れない、という
表裏一体の関係にある。
《物質的な生》は、本来的な《生》から、客観化、自己疎外化を経て抽出された
生の断片に過ぎない。一方、
《情報的な生》は、この世界の有意味性、すなわち
《意味》と
《時間》(これを合わせて「変化」と言っても良い)に結びついており、
私達自身と切り離すことは出来ない。
だからこそ《物質的な生》の時間的限界を超えて、
その価値を私達自身が《情報的な生》として重ね描きするのである。
愛し、
愛される、という《情報的な生》を描き出しているのは、私達自身だ。
《物質的な死》に、積極的な意味を与えるのも、私達自身だ。
物質的に不自由でも情報的には残酷なまでに自由な私達が、
その完全な自由さゆえに完全な自己責任において紡ぎ出す価値なのだ。
- 「私」の人生は、唐突に受精卵に始まって、心臓の鼓動の最後の一個で唐突に終わる。
その意味での「私」とは、生命体としての「私」なのだが、
よくよく考えると、それは私の意識を運ぶ「入れ物」の存在期間であって、
私の意識の存在期間は、それよりももっと短い。
物心が付く頃に徐々に確立され、自分なりの意識を維持し、
歳とともに記憶力と思考力が衰え、私の意識は解け、ゆっくり消えていく。
つまり、私という存在は、徐々に生まれ、徐々に死ぬのだ。
- 『人は夜ごと死に、朝ごとに生まれ変わる』という言葉は、
色々に解釈できるけれども、「人」を、自覚する存在と捉えるなら、
これは比喩でも何でもなく、文字通り睡眠は死であり、覚醒は誕生である。
睡魔に襲われ、自覚が解けていく時の様子を、
私は何度も記録しようと試みてきた。
「自」という情報空間の確かな一点がぼやけ、
思考空間全体が『私が考えている』と『何かを見せられている』という
能動と受動の間の往復運動を起こし、
ついに主体性を手放した瞬間、つまり「私は私である」という連鎖が途切れた瞬間、
もう人は寝ているのである。………「人」として、死んでいるのである。
- 生と死は、ゼロとイチのようなものではなく、
ゆるやかに混じり合い、広がっているものなのかも知れない。
物理世界に属する身体の生と死には、比較的明確な生と死の境界があるが、
人間としての私という存在、意識、自覚については、
色々なサイクルで生と死が交叉しているものなのかも知れない。
そして、結局のところ、私は、「あれが最後の死だった」と理解することは出来ない。
それが、他者の死と、私の死の、決定的な違いだ。
私にとって、私の死は、永遠の謎である。
しかし、私にとって、私の死は、日常の中に繰り返されてもいる。
「メメント・モリ(死を見つめよ)」「死を意識してから、本当の人生が始まる」
…ここで言われる「死」は、自己客観視する時にだけ絵空事として了解される
「いつか必ず訪れる、最後の死」だけでなく、
日常の中に織り込まれた、リアルに体験している緩やかな死も含まれるのかも知れない。
そのことに気付けば、人生の時間の濃度は高まり、
一瞬一瞬の意味が、より多く開示されるようになるのではないか。
『私は生きる。この世界として死ぬために。』
I live my life. To die as this world.
(視点2) 空間・時間の境界条件が定まっている。
=有限であること=凍結した視点
※宇宙の始まりから終わりを、ビッグバンを頂点とする三角錐として
(全体を同時に)認識する視点。「神の視点」
(視点1)「始まること」+「一方向に時間が進むこと」+「終わりを内包すること」
※空間的に同時に全体を俯瞰することは出来ないが、
「いま、ここ」において、自己の内腑に折り畳まれている
「始まり」と「終わり」を認識する視点。「人間の視点」
この2つは等価である。特に(視点1)の「終わりを内包すること」とは、
「始まってしまったものが、終わるために自殺因子を持つこと」とも
表現できる、極めて「人間的視点」である。「神の視点」からすると、
何故このような回りくどいことをするのか不思議であるが、しかし、
このような構造を導入することで、「神の凍結した視点」に
「選択可能性」という暖かい錯覚を持たせることが出来る。
※「崩壊と還元」「収縮と拡散」は(視点1)(視点2)の
切り替えに過ぎない。二重スリットの実験で粒子を空間に投げ出す事は、
視点1から視点2への還元である。観測スクリーンの上に粒子の位置を
記録することは視点2から視点1への崩壊である。スリットに観測器を
置くということは、スクリーン上ではなく、手前のスリット上で
視点2から視点1への崩壊を選択しているので、異なる結果が得られるのは
当然のことである。
何故、神は自分に似せた具体物としての(現実の)人間を作ったのか。
何故、崩壊は起こるのか。可能性は現実に崩壊するのか。
何故、視点は無償なのか。
任意に選択できるのは何故か。無償で決断できるのは何故か。
それは、選択する者が自己完結であるからだ。
具体物への崩壊は、(視点2:可能性界に対して視点1:物質界が)
自己無矛盾な結果である限り、好き勝手に行われて構わない。
※自分が自分の全てに責任を持つという完全な自循界では、
何をしても問題はない。他の誰かに説明されるという世界観の中では、
その「他の誰か」との無矛盾を要求される。つまり、支配される。
※決定論的な視点2に、《時間》を導入して視点1を得ることで、
誰にも支配されない自由を自己責任において手に入れることが出来る。
それでもなお、数ある可能性の中から、何故その一つに決まるのか
(崩壊・収縮が最終的に一つの具体性(粒子性)に帰着するのか)
ということに、「偶然である」という以上の説明が必要ならば、
「始まってしまったものが、終わるために行う辻褄合わせ」
「生まれてしまったものが、死ぬために行う辻褄合わせ」
という合理性を付け加えることが出来る。
その意味で、人間の決断は、有意味であろうとする限り、
この無意識に支配されているとも言える。
※始まりも終わりのない世界には「決断」や「収縮」は不要である。
無限の中に漂う限り、判断はする必要が無いし、しても無意味だし、
そもそも判断という機構自体が生まれることも無い。
この意味世界は有限であり、時間を勝手に導入して自己責任の範囲で
自由を得た我々は、有意味性(有限性)の要請に従って、始まって
しまった以上、終わるための決断を繰り返し、そして終わることで完成する。
終わることで、自分の有限性と世界の有限性の一致を感得する。
つまり、世界として終わる。そのために、一瞬一瞬の決断を行う。
だから、生きよう。世界として終わるために。
■トピックス
- 限界性
- 自分自身を観測することの限界:
盲点の存在(ゲーデルの不完全性定理が示すような盲点)
自分という道具立てだけでは、自分自身をどう扱い、
どう定義して良いか分からない。
(広義の自己の対置概念として神などを持ち出さないと
自己を定義できない。)
自分だけで自分を説明しろと言われても困り果ててしまう。
同時に自分全体を捉えるのは難しいので、
自分自身を見る視点を変えながら盲点をずらし、
全体像を想定していくしかない。
- 認識者としての生命は、自分自身のまるごとを自分が認識することは
大変難しい。
(これこそ「悟り」や「仏心」や「神」の相の構造である。)
大抵は、自分の一部を対象化して理解しているだけである。
自分にあまりにも関係の無いものは、重要性を感じられないが、
「自分そのもの」に近過ぎるものも、よく理解できない。
紙に書いた文字を、遠く離せば見えなくなるし、
目玉にピッタリとくっつけても全く見えないのと似ている。
しかし、生命に関しては、その本質的実在である女性は、
派生的現象である男性と違って、セックスに於けるエクスタシーの瞬間に、
「生命としての"まるごとの自分"を、自分自身で完結して知る」
ことが出来る、という感覚論もある。
せめて男は、その状態の実現への精力的な努力をするべきだろう。
「悟り」のための厳しい修行は、性行為では得られないエクスタシーへの、
男なりのアプローチの方法なのかも知れない。
- 死
- 個体が生きるためには、プログラムされた死(アポトーシス:apoptosis)
が裏づけに存在する必要がある。
人は何故、単純さを求めるのであろう。
有限存在としての人間は、何故、
無限と見紛う複雑さの前に単純さを見出したがり、安心したがるのだろう。
限りある命を運命付けられた人間は、
何故、自分だけは死なないと、安心したがるのだろう。
そして、自分がいつかは死ぬ、という事象の確実性が、
心理的な死亡時刻の不確実さを無限大にまで発散させる。
(もしかすると、不確定性原理は人類の願望なのかもしれない。)
しかし、今の自分自身の中に、自分自身がいずれ必ず終わる、という宿命が
プログラムされていることを知り、心の底から納得することでしか、死をも
織り込み進行する生をリアルに考察することが出来ないのも事実だ。
死ぬことを恐れては、生きることが出来ない。
- 光子
- 実は私は仮想世界の光子かも知れない。
仮想世界の原子核と中性子の間でキャッチボールをされ
お互いを引き付ける役割を担っているか、
仮想世界の人間の目に飛び込んで映像を脳に伝えているか、
その仮想世界の空間内をその世界で許される最高速度で飄々と
飛んでいるかも知れない。
しかし、その仮想世界で過ごす時間は私にとって0秒であるので、
私にはその仮想世界で過ごした時の記憶が無い。
1クロノス秒毎に私は仮想世界に転送されて、
その世界での一生を終えると、また元の世界に戻ってきて、
別世界での莫大な経験を使って次の1クロノス秒後の
決断をするのかも知れない。